FRB幹部は利下げを9月とみる市場観測けん制、11月以降に遠のく可能性も
年内のFOMC開催は6月、7月、9月、11月、12月のあと5回となります。今年末の政策金利見通しは3月のFOMC時点で4.6%となっています。現在は5.25~5.50%ですので、0.25%刻みで年内3回の利下げを行えば、年末に4.6%に達する見通しです。
この3月時点ではFRBと市場が年内に見込む利下げ回数は3回で一致しており、市場には6月にも利下げを開始するのではないかとの期待がありました。
しかし、4月の指標を受けて、市場が見込む年内利下げ回数は1~2回に減り、利下げ開始時期も6月から7月か9月に後ずれしました。5月の指標公表を受けて、年内2回利下げとの見方となり、利下げ開始を7月とする見方は少なくなり、9月とする見方が増えました。
この9月に利下げとする市場の見方に対し、FRB幹部からはインフレが2%目標に近づくまで雇用や物価のデータを数カ月見る必要があると利下げに慎重な発言が相次ぎ、市場の楽観をけん制しているのが現在の状況です。
次回6月11~12日のFOMCでタカ派姿勢が続くのかどうか、同時に公表される金利見通しがどの程度、上方修正されるのか注目です。金利見通しが3月時点の4.6%から5.1%に上方修正されれば、FRBは年内あと1回の利上げを見通しているということになります。修正幅によって、タカ派度合いがどの程度かを推測することができます。利下げ開始は9月が遠のき、11月か12月ということになるかもしれません。
日銀の追加利上げと米利下げ重なれば円高も、当面は振れ幅大きい地合いに
このようにFRBは、目標の物価2%の軌道に戻ることを確認するまでは、現在の高水準の政策金利を当面維持し、利下げの時期を模索する局面にありますが、日本銀行は逆の局面にあります。
日銀の物価目標はFRBと同じ2%ですが、デフレから脱却して物価目標の2%を安定的に定着させるため、金融緩和を当面維持する姿勢です。賃金と物価の好循環を背景とした基調的な物価上昇率が2%に達する可能性が高まっていくか見極めた上で追加利上げを判断するとしています。
日銀は基調的な物価上昇率は2%に近づきつつあるとしていますが、市場では追加利上げは9月以降との見方が多いようです。FRBも9月の利下げとなれば、この時はドル安円高に大きく反応する可能性があります。
しかし、逆にいうと、そのタイミングまでは、FRBの高金利を背景としたドル高、日銀の低金利を背景とした円安が続くということになりそうです。
ただ、米国の雇用や物価の弱い指標が相次げば、FRBの利下げ時期が早まり、この構図が変わってくる可能性があります。また、日本の追加利上げ期待で長期金利が上昇してくれば、円安が抑制されることもあり得ます。円安地合いが続くとしても、これまでとは違って上下に振れやすい相場地合いになりそうです。



















































![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)
![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)
![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)
![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

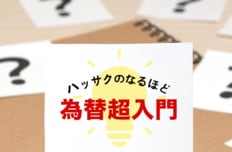



















![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)









![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)













![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)
![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)
![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)





