「老後に4,000万円」がいきなりバズるがトウシルではすでに予言済み?
先日、テレビにコメント動画が出ました。
物価上昇についての話題で、「物価上昇局面に入ったということは将来への備えも増額修正を迫られる」ということ、「物価上昇の影響でモノの値段が将来2倍になるとすれば、『老後に2,000万円は老後に4,000万円』を意識する必要がある」というコメントをしたのですが、放送後にYahoo!ニュースやYouTube動画にも配信され、ちょっとバズっていたようです。
「老後に4,000万円? どこかで聞いたような……」と思った人はトウシルマニアです。実はこの話、トウシル読者にはすでにお伝えしていたことだったからです。
2023年1月のコラム『物価上昇が10年続くと「老後に2,000万円から4,000万円に」年始は資産形成の目標を上方修正してみよう』がそうです。
2023年1月、物価上昇のサインが現れてきたタイミングで、将来的な物価上昇に投資家は備えようという話をしていました。似たような時期に日本経済新聞電子版にも書いていましたが、まさか1年のインターバルを置いて、ネットでバズるとは思いませんでした。
言ってみれば1年前の予言が、とうとう現実のものになり始めた、ということかもしれません。
「5年で2倍」と文句を言っていても始まらない。米国ならもはや「老後に2億円」
「老後に4,000万円」のネットの反応を見ていると「5年前に2,000万円と国は言っておいて、5年で2倍とかふざけるな」「老後に4,000万円に上方修正とは政権の課題が明らかになった」的なコメントがありました。もちろんミスリードです。
物価上昇が起きれば、未来の目標額をアップデートしていくことは当然の感覚です。G7諸国はおおむね20~25年で物価が倍になっています。特に近年の物価上昇が著しい米国では、老後に必要な金額が急激に増加しているそうです。
ブルームバーグの配信した記事「快適な老後には150万ドル必要と米国人、理想と現実の格差拡大-調査」によれば、ノースウェスタン・ミューチュアルの調査を紹介しており、この結果によるとたった4年で約100万ドルという老後に向けた目標額が約150万ドルに跳ね上がったそうです。
すなわち、1ドル150円換算すれば150万ドルは「老後に2億円超」ということになります。これはおそらく公的年金を考慮せず、かつ安心できる金額としてのイメージを聞く調査をしているためと思われます。
そして、日本でも生命保険文化センターの調査で「ゆとりある老後生活費」を聞くと月37.9万円となり30年で概算すれば「老後に1億3,644万円」になります(「老後の最低日常生活費」と「老後のゆとりのための上乗せ額」を合計)。
それよりも注目したいのは、近年の急激な物価上昇を踏まえて、米国人は「老後に必要な金額も普通に増えるよね」と判断しているということです。
投資家は未来の必要額がアップすることを織り込むべき
トウシル読者はそれなりの投資知識をお持ちの個人投資家であろうと思いますが、インフレ対応がマネープランに影響を及ぼすことについては、違和感をもうほとんど持たないのではないでしょうか。
「いつ2倍になるか」の議論はあっても、「いつかはそうなる」ことについて異論はない、と思います。だとすれば準備が必要なことは変わりません。
このとき必要となってくるのは「未来の必要額をアップデートしていく意識」と、「インフレ控除後のリターンの意識」です。どちらも徐々に変化していくので認識が難しいのですが、一番シンプルに考えると、
- 現状の資産額
- 今後の定期積立額
- 運用収益率
- 運用期間
- 最終的な受け取り額
が長期の資産形成の構成要素です(迷ったらExcelのFV関数などを使って考えてみるといい)。
このうち、「最終的な受け取り額」を上方修正させたいとすれば、「今後の定期積立額」を増額させることと「運用収益率」を物価上昇率以上にすることがカギとなります(「現状の資産額」と「運用期間」は変わらない場合。運用期間を延ばすことが可能ならこれは有意義)。
ところが「運用収益率」を私たちは資産増のために用いるものとして考えてきましたが、インフレ時には実質的なリターンは割り引いて考える必要があります。
つまり、「インフレ控除後のリターン」だけが実質的増加分であり、物価上昇率に達するまでの分は、すでにある資産の価値を減じないためのリターンでしかないと考えるわけです。
すると、リターンにのみ頼るインフレ対応は難しく、セットで考えるべきは「今後の定期積立額」の増額ということになります。
物価上昇時は目の前の家計もしんどくなりますが、それに応じた積立額の増額も意識しておきましょう。ほとんどの場合、毎月の積立額は物価上昇を意識して設定していないので、なおさら検討してみるべき、と思います。
改めて「老後に4,000万円」を考えておきたい
ところで、「老後に4,000万円」というのはiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)やNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)を活用した資産形成「以外」の議論を抜きにして語るわけにはいきません(そうする人が多いが)。
まず、(公的年金収入=日常生活費)というバランスがあっての「老後に2,000万円」ですが(月5.5万円足りないのは教養・娯楽費、交際費に相当)、会社員の標準的な厚生年金収入と夫婦2人分の国民年金収入があって成り立ちます。
自営業者やおひとりさまは固定収入のモデルが異なることに注意が必要です。逆にいえば、共働きの正社員夫婦は固定収入がアップし、老後の余裕が増します。
また、会社の退職金・企業年金制度から得られるリタイア時の収入の違いも大きく老後を左右します。そもそもいくらくらい退職金をもらえる会社なのか、今後インフレ見合いで退職金の増額交渉が行われるかはウオッチしたいところです。
ここも共働きの正社員夫婦はダブル退職金をもらうことでぐっと楽になります。こちらについては物価上昇に追いつく可能性はありますが、労使交渉で退職金の増額が実現する必要があります(制度設計による)。
そのほか、「住宅ローンは75歳完済予定」のようなケースでは、「退職金を使って残債を一括返済」のようなパターンになり、退職金が目の前で消えていくことがあります。マネープラン上は住宅ローンや教育ローンに注意です。
ここまでいくつかのポイントを整理してきましたが、少なくともこれくらいのお金の問題整理があって、初めて「投資で老後にいくらつくるか」の議論が成り立ちます。
物価上昇を織り込んだプランニングを考えるのはなかなか大変になってきました。
自分なりにしっかり考えてみたい、という人はぜひ参考にしてみてください。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)
















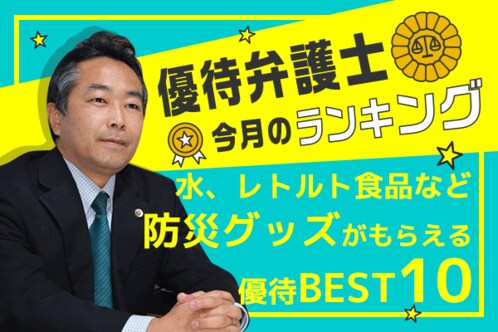
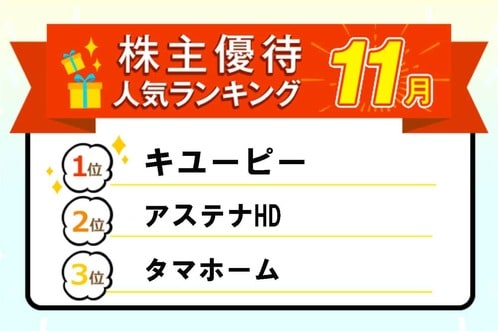























![[動画で解説]株価急騰を招いた金融政策発表から1カ月が過ぎた中国~財政政策への期待は報われるか?~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/a/498m/img_8a6c96cf4ead7b0268fe7f71a28c5fd174858.jpg)
![[動画で解説]「短期ドル/円の見通しは、「151円台をキープする限り、円安継続」!」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/498m/img_94157f1cc65cda079f19b67766ae663646051.jpg)
![[動画で解説]【日米株】年末ラリーへ 今そこにあるハードル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/6/498m/img_36b800bb6c24b2c67166a5873aae553259027.jpg)
![[動画で解説]中国GDP鈍化、デフレと不動産不況続く。それでも大規模な景気刺激策に慎重な理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/0/498m/img_505d64bd347e5f9efb94cdb4e523377b51921.jpg)


































![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)


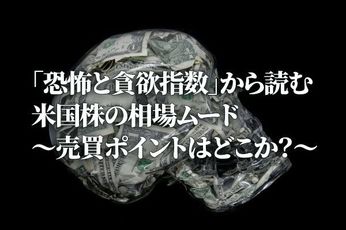


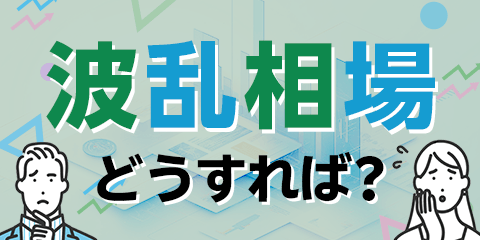



![[動画で解説]大激戦!米大統領選挙で世界分裂は直らない](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/e/160m/img_fe0df75b485762eaa90ed95b8238cdaf69929.jpg)

![[動画で解説]iDeCo(イデコ)ファースト!NISA(ニーサ)より節税メリット大!デメリットも理解して活用](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/2/160m/img_b2ffc423fe5754f6473aa1748346698d47085.jpg)
![[動画で解説]【S&P500の危機?】トランプショック到来...!?米大統領選挙の今後](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/160m/img_4d37c6668863c2c90260de7232facac5104960.gif)




