iDeCo改革、実現は少し先か
政府の新しい資本主義実現会議はこのほど、実行計画改定版の原案をまとめ、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に関して、掛け金の上限引き上げを検討すると明記しました。NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)に次ぐ第2の柱として、個人の資産形成を後押しする考えです。具体的な上限額に関してはまだ情報がありませんが、主要メディアの報道によると、政府は年内に結論を出したい考えを示しており、今月まとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にこれらの内容を盛り込む方針です。
iDeCoについては「70歳までの加入年齢の引き上げ」がすでにニュースになっています。厚生労働省の社会保障審議会 企業年金・個人年金部会で何度か議論が行われており、総論としては反対がなく、具体的な要件定義の可能性について検討している段階です。
加入年齢の引き上げはNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)の拡充と同様に資産所得倍増プランに盛り込まれていたため、検討されるのは当然です。実はこの資産所得倍増プランには、iDeCoの掛金額引き上げの検討も含まれていました。
「第二の柱:加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革」を読んでみると「iDeCoの拠出限度額の引上げ」の検討と書いてありますので、もともと検討されていた項目であったわけです。
そう考えると、資産所得倍増プランから骨太の方針までの記述がそろえば、iDeCo掛金上限引き上げの実現可能性は高いと考えられます。
ただ、実現となるのはもう少し先のことになりそうです。仮に来年の通常国会に法案が出てすぐに成立したとします(来年の与党の国会運営が安定的かは不透明で不安がある。年金関連法案はしばしば政争に巻き込まれると審議延長になる)。
2025年春に法案が成立した後に、具体的な準備がスタートしたとして、法令の整備はもちろんですが、金融機関の対応も必要です。確定拠出年金の場合はデータベース管理を担う記録関連運営機関のシステム対応が大前提で、ここにある程度の時間を要します。
過去の例を見る限り、法案の成立から1~1年半は考えておく必要があり、そうなると2025年春の法案成立だったとすれば、2027年1月からスタート、というあたりが考えられます。iDeCoの限度額管理は暦年ですから、切り替わりは1月になることでしょう(法律的には2026年12月の掛金設定が翌年1月の納付額に相当する)。
ここが無理だと2028年1月という可能性もありますが、これだとちょっと遅すぎる印象です。
物価高が将来の必要額を高める今、iDeCo限度額は早期の引き上げが必要
日本の確定拠出年金に相当する、米国の401(k)プランは、限度額が高いことで有名ですが、物価上昇を反映して毎年のように限度額を引き上げしていることでも知られています。これと比べると、何年も限度額を据え置いてきた日本のiDeCoと企業型確定拠出年金は、物価上昇を踏まえた限度額見直しが急務になっています。
物価上昇は将来の必要額の上昇を迫ります(私は「老後に2,000万円」ではなくもはや「老後に4,000万円」を意識するべき、と主張しています)。
このとき、あとから限度額を引き上げてもあまり意味がありません。むしろ早い段階で限度額を引き上げて、運用も合わせて将来の必要額を多く確保できる施策を考えるのが好ましいといえます。物価上昇と同率の引き上げ、資産形成時期での引き上げが重要なのです。
NISAの限度額が大幅に引き上げられたことは、将来の物価上昇を踏まえたとすれば、実はおかしな話ではない、ともいえます(経済が成長すれば株価も上がるので、枠が小さいままだと投資の自由度も下がっていく)。
そこで、iDeCoも月数千円程度の引き上げではなく月1万円あるいはそれ以上の引き上げを期待したいところ。できれば「おお、これはすごい!」とうならせるような大きな限度額アップを実現してほしいところです。
2024年12月にも掛け金引き上げ!対象者と上限は?
さて、「実現されても数年先」と聞くとガッカリしたiDeCo加入者も多いと思います。ところが、今年12月にも一部の対象者においては限度額の引き上げが実現するので、こちらを紹介しておきましょう。
現在、iDeCoの拠出上限は月1.2万円、2.0万円、2.3万円、6.8万円とかなり複雑です。このうち、「会社の企業年金(※)に加入している場合」に該当する人の上限は月1.2万円と月2.0万円に分かれていますが、12月からは「月2.0万円に統合」されます。
※確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済、公務員の年金払い退職給付(共済)を含む
つまり、月1.2万円が上限だった人は2.0万円まで増額できる可能性があるわけです。
ただし、別の上限管理ルールが加わります。それは会社の企業年金制度が充実している場合はiDeCoの枠が制限されるというものです。
企業年金およびiDeCoの限度額は「合計5.5万円」という大枠が設定されることになります(これは企業型の確定拠出年金だけを実施する会社の確定拠出年金制度の上限でもある)。
基本的には(月2.0万円:枠A)以下ということになりますが、もし
(上限5.5万円)-{(確定給付企業年金の掛金額:会社ごとに定まる)+(企業型の確定拠出年金掛金額:個人ごとに定まる)}=(iDeCoに拠出できる枠B)
上記を計算して(月2.0万円:枠A)より少ない場合は、(枠B)のほうが優先されることになります。つまり枠が小さくなる可能性があるわけです。
考え方としては、3つの制度を合計した非課税枠が月5.5万円で、企業年金が先行して枠を利用し、残りをiDeCoで使えるということです。
ちょっとややこしいですが、多くの場合は、月1.2万円より多く出せるチャンスになると思います。
例えば、公務員は月2.0万円になるとされています。これは確定給付企業年金に相当する分の掛金額が多くなく、企業型の確定拠出年金制度に相当する制度もないため、月2.0万円のiDeCoの枠が満額利用可能になるからです。
iDeCoの制限が生じやすいのは、会社が確定拠出年金制度を採用しており、あなたの掛金額が高めになっている場合、あるいは確定給付企業年金の水準が特別に手厚い場合などです。
このあたりは、社内の広報や人事部からのお知らせで確認することができます(確定給付企業年金の掛金額については「他制度掛金相当額」として社内に開示済みです。確定拠出年金の個人の掛金額はサポートHPにログインして確認できます)。
たくさんiDeCoに出せない人は、見方を変えれば会社の企業年金制度が極めて充実しているともいえるわけですから、その場合はNISAの活用を考えてみてください。
iDeCo、「月2.0万円は自分で手続き」が大原則
さて、この「iDeCo月2.0万円」のチャンスですが、あなたがもし対象となったとしても、自動的に2.0万円が引き落とされるわけではありません。自分で掛金増額をする必要があります。
このあたりは、自分が加入しているiDeCoの運営管理機関でアナウンスがありますのでそれぞれ確認し、手続きをしてください。
「月1.2万円が月2.0万円になるのはNISAと比べて大したことないかな……」と考えるのは禁物。年9.6万円相当ということは、税率が20%なら年1.92万円、30%なら2.88万円が、節税されてその分あなたの将来の財産に切り替わったことになります。
納税額を減らすチャンスは会社員にはほとんどありませんから、しっかり増額手続きをしておきましょう。年9.6万円の増額でも、20年も積み重ねれば192万円の元本増になり、年4.0%の利息が積み重なれば293万円ですから、これは決して小さくない金額です。
もちろん、数年先にiDeCoの枠が増額されたときも、増額手続きをお忘れなく。NISAも魅力的な制度ですが、基本的には「iDeCoファースト」で満額積み立てることが大切です。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

















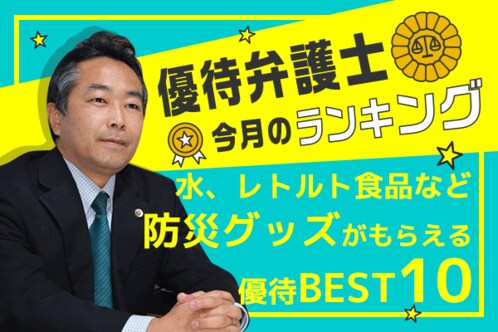
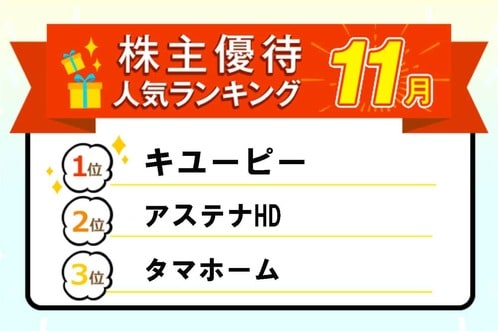





















![[今週の日本株]注目イベント控えるも、相場の行方は視界不良?~日本株の「迷い」と米国株の「強気」のはざまで~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が大幅減)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/4/498m/img_14b007ce9034324da88c6461b2cb4ac961389.jpg)
![[動画で解説]「お金持ち」は幸せか?FIREの方法?どうすればなれる?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/e/498m/img_6ece2aef258682c52604d4427bce2ff980698.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:TSMC(AI半導体の好調で大幅増収増益)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/498m/img_bc72a73e223e6f96675315f7ccc4f88865860.jpg)
![[動画で解説]10月21日【米国株は堅調、日本株は疑問符?~今週は日米企業の決算発表、27日に衆院選投開票を控える~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/7/498m/img_97549b5e9a56fb9e364e36b97d576b6690112.jpg)

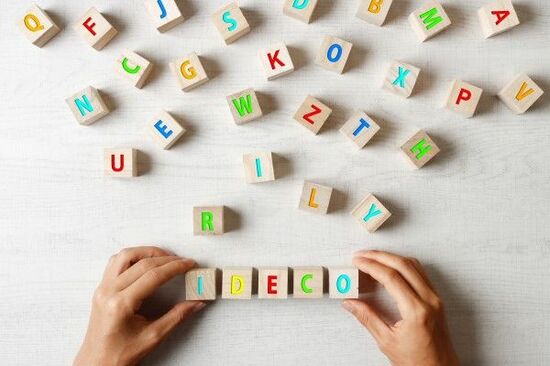























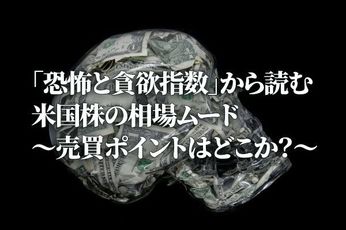







![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)







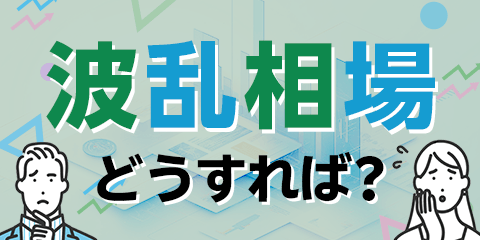



![[動画で解説]日銀、10月は利上げなし~最近の指標点検とワーキングペーパーの含意~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/160m/img_717a7a98769c2f7da8e16c8ae892451162445.jpg)
![[インタビュー] マグニフィセント・セブンが下落すれば、小型株が上昇](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/2/160m/img_d22eda29593bbc137d83f4b36948001f33849.jpg)





