「政策保有株」とは一体どんなもの?
最近よくニュースなどで目にするワードの1つに「政策保有株の売却」というものがあります。
政策保有株とは、取引先との関係の維持や強化のために保有するもので、お互いが株を保有し合う場合は「持ち合い株」とも呼ばれます。
会社四季報の大株主欄を見ると、大株主にグループ会社や金融機関が名を連ねているケースがよくありますが、これらの多くは政策保有株であると考えられます。
政策保有株は、安定株主の構築により敵対的買収を防ぐ効果も期待でき、以前は金融機関と取引先、グループ会社間などで株の持ち合いをすることが一般的でした。
しかし政策保有株は、企業の有する資産が有効活用されず、株のまま寝てしまっているという一面もあり、資産の有効活用により業績を向上すべきという声の高まりから、近年はこの政策保有株を売却する動きが高まっています。
政策保有株の売却が進んでいる
例えば日本経済新聞の記事を見ると、
- 損保ジャパンが政策保有株をゼロへ(2024年2月15日)
- 持ち合い株 7割が削減 東証プライム1,100社表明(2024年5月18日)
- 政策保有株を売却 デンソー、アイシン(2024年6月21日)
といったように、各社が政策保有株の売却を進めていたり、検討していることが分かります。
実際、政策保有株の残高は年々減少していますし、この動きは今後も続くでしょう。また、株価が大きく上昇している足元のような状況では、より高く売りたいというニーズにも合致しますから売却のスピードが増すことも考えられます。
政策保有株は「銀行とその取引先」「生命保険会社とその取引先」「損害保険会社とその取引先」「グループ会社間」で持ち合いの形で行われることが多いです。
そのため、持ち合いの片方が政策保有株を売却した場合は、もう片方も売却するケースが多いものと思われます。
政策保有株売却による株価への影響
政策保有株の売却により株価へどのような影響が考えられるでしょうか。保有株の売却によりマーケットに放出されるわけですから、やはり株価にはマイナスです。
需給バランスからみて売りの方が買いより強くなり、株価が下落したり、株価の上値が重くなったりすることが考えられます。
ただし、この株価へのマイナス要因はあくまで需給関係を要因とするものであり、政策保有株を売却される側の業績・ファンダメンタルには何ら影響を及ぼさない点に注目です。
もし政策保有株として保有されている株が多い銘柄を大量に取得したい投資家がいた場合、政策保有株の売却により株価が軟調気味に推移することは歓迎すべきことです。
政策保有株の売却がなければ買い進めるのにかなり株価の上昇を引き起こしてしまうところ、政策保有株の売却により比較的安く買い進めることが可能となるからです。
また、政策保有株の売却がひと段落すれば株価の上昇も期待できます。
私たち個人投資家としても、政策保有株の売却により株価が軟調に推移するのなら、欲しい株を安く手に入れることができます。
そのため、業績悪化の懸念がないにもかかわらず株価が軟調に推移している銘柄があれば、買いを検討してみるのも一考でしょう。
保有銘柄に政策保有株が多いことが分かったら?
では、自身が現在保有している銘柄に、銀行やグループ会社、取引先などから政策保有株として保有されている株が多いことが分かった場合はどうすればよいでしょうか。
少なくとも、政策保有株の存在を嫌気して、ただちに保有株の売却をする、という必要はありません。
実際、政策保有株が多い銘柄であっても株価が大きく上昇しているものも珍しくありません。
無論、流動性の低い銘柄などでは政策保有株の売却が株価にとって大きなマイナスインパクトを引き起こす恐れもありますし、株価の下落が政策保有株の売却とは異なる理由(業績の悪化など)で生じている可能性もあります。
従って、筆者がいつも行っているように、移動平均線を割り込んだらいったん売却するなど、どこまで下がったら売却するかのルールを設定し、それを遵守するのが一案です。
■【動画で学ぶ】足立武志さんの株投資テクニック満載!
≫新NISAの情報が多すぎて混乱している方へ、頭を整理する方法
≫投資のリスク勘違いしていませんか?「大きな利益を狙う」と「大きな損失を抑える」の違い











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)
















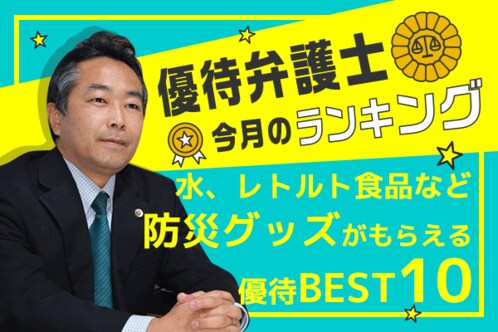
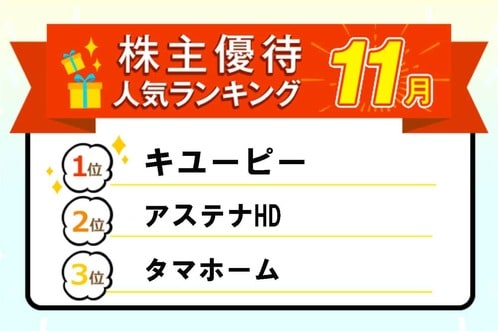























![[動画で解説]株価急騰を招いた金融政策発表から1カ月が過ぎた中国~財政政策への期待は報われるか?~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/a/498m/img_8a6c96cf4ead7b0268fe7f71a28c5fd174858.jpg)
![[動画で解説]「短期ドル/円の見通しは、「151円台をキープする限り、円安継続」!」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/498m/img_94157f1cc65cda079f19b67766ae663646051.jpg)
![[動画で解説]【日米株】年末ラリーへ 今そこにあるハードル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/6/498m/img_36b800bb6c24b2c67166a5873aae553259027.jpg)
![[動画で解説]中国GDP鈍化、デフレと不動産不況続く。それでも大規模な景気刺激策に慎重な理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/0/498m/img_505d64bd347e5f9efb94cdb4e523377b51921.jpg)


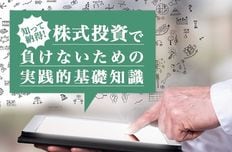































![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)


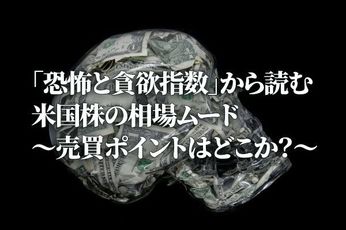


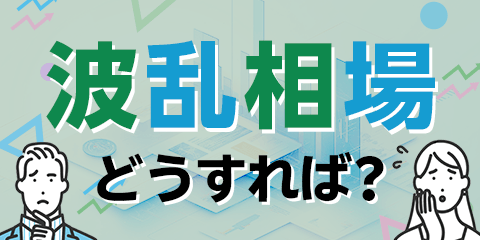



![[動画で解説]大激戦!米大統領選挙で世界分裂は直らない](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/e/160m/img_fe0df75b485762eaa90ed95b8238cdaf69929.jpg)

![[動画で解説]iDeCo(イデコ)ファースト!NISA(ニーサ)より節税メリット大!デメリットも理解して活用](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/2/160m/img_b2ffc423fe5754f6473aa1748346698d47085.jpg)
![[動画で解説]【S&P500の危機?】トランプショック到来...!?米大統領選挙の今後](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/160m/img_4d37c6668863c2c90260de7232facac5104960.gif)




