今日の為替ウォーキング
今日の一言
人生は後ろ向きしか理解できないが、前を向いて生きなくてはならない – キルケゴール
Heartbreaker
日本の物価は上昇している。6月の総合CPI(消費者物価指数)は前年同月比で3.3%上昇した。電気代の値上げが押し上げ、食品高も続いている。すでに米国の上昇率を上回っている。
この数字を見るかぎり日銀の物価目標はすでに達成されている。それなのに日銀が依然としてウルトラ金融緩和の継続に固執するのはなぜなのか。
日銀の目的が物価の安定ではなく「金融抑圧」だとすれば、納得できる。金融抑圧とは、インフレと低金利を組み合わせることによって、政府の債務を非常に低い金利でファイナンスし、究極的には膨張した政府の借金の棒引きを図ることを目的とする政策である。第2次世界大戦後、戦費調達で公的債務が膨張していた多くの国々でこの政策が採用されている。
インフレはモノの値段が上がることだが、相対的に円の価値が下がるということでもある。借金をしている人(政府)は、インフレになれば返済するお金が少なくなる。お金の貸し手側(投資家や預金者)から見ると、受け取るお金の価値が減るのが、その分金利上昇による運用益(利息)が増えるため、市場原理が正常に機能している市場においては、プラスマイナス・ゼロになる。
ところが日銀が人為的に国債利回りを低く抑えつつインフレを発生させることによって、借金をしている政府は、低利息で利払いを軽減させながら、お金の価値の減少させることによって債務残高を縮小することが可能になる。
インフレ率を2%以上にして、国債金利を0.25%に固定する状況を安定的に達成できたなら、日本政府の借金は30年後に実質的には半分近くまで減少するとの計算がある。これが緩和政策の究極の目的だといわれている。
金融抑圧は、借金を抱える政府にとっては、増税や歳出削減など痛みを伴う改革を行わずに済ませることができて良いことづくめである。しかし、そのしわ寄せは、貸し手である国民に来るのだ。ある調査によると、日銀の超低金利の20年間で国民が失った預貯金の利息収入は164兆円とも言われている。
緩和政策の副作用が、円安となって現れているのがはっきりしているのに、為替は管轄外だと日銀は見て見ぬふりをしている。政府も、問題なのは円安の「速度」であって、円安そのものが悪いとはひとことも言っていない。本音では、「もっと円安になれ」と願っているのではないか。
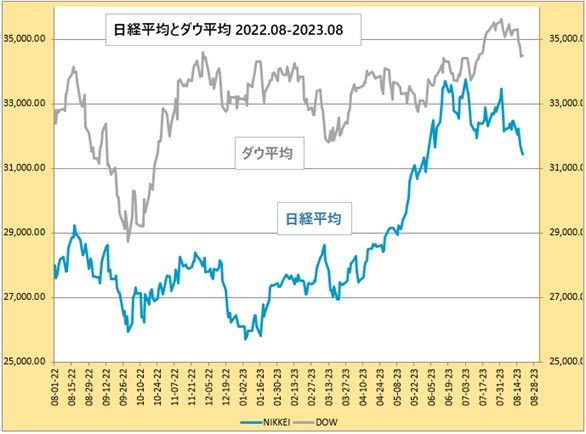

今週の注目経済指標



















































![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)
![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)
![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)
![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)


















![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/356m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)







![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)














![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)
![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)
![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)





