癌の費用と「がん保険」
※注:自分の癌について「癌」、「がん保険」について「がん」と書き分けている。
話題が癌となると、がん保険に興味を覚える読者がいらっしゃるだろう。また、そもそも筆者が選んだような治療には費用がどれくらい掛かるものなのか。
筆者が8月の下旬に食道癌だと診断されてから、病院や薬局などに支払った医療費はざっくり合計して200万円程度だ。過去に歯科医院に支払った金額を大幅に下回る。
抗癌剤の治療、比較的大規模な手術、合計約40日の入院が主な細目だが、手術や抗癌剤は健康保険の対象なので病院で支払った金額の上限は健康保険の高額療養費制度で決められた額が上限であり、200万円の大半は個室(シャワー付き)の費用だ。個室にした理由は、パソコンを持ち込んで原稿書きやメールのやりとりやオンライン会議などの仕事がしやすいことと、消灯時間が自由であることなどを考慮したものだ。部屋代を原稿料で稼げたというほど仕事をしたわけではないが、良かったと思っている。但し、4人一部屋を選んでいたら、医療費の支払いは前記の3分の1以下だったろう。
民間の保険会社のがん保険には入っていなかった(著書などで書いている通りでホッとしている)。振り返ると、かつて、若いサラリーマン時代に3、4年程度団体保険のがん保険に加入していたことがあるのだが、30年くらい前に解約しており、現在は健康保険だけだ。
がん保険に入っていたら、診断給付金○○万円、入院費一日×万円という調子で保険金が支払われて、かなりの助けになったはずだ。しかし、これは癌になってから振り返って計算する結果論であり、「意思決定として」がん保険に入っておく方が正しかったということを意味しない。また、想像上の結果論としても今回の癌に伴う給付が、過去に支払ったであろう保険料を十分上回るかどうかについては自信がない。
仮に時間を巻き戻すとして、或いは現在筆者が若いサラリーマンだと仮定して、がん保険に加入するか否かを考えると、筆者の発癌確率が平均並みから大きく外れないとすると、がん保険に入ることは「意思決定として損」だ(そうでないなら、保険会社が潰れてしまう!)。
問題は、筆者が癌を発症した時にその治療費を問題なく払えるか否かである。この点に関しては、今回もそうであったように健康保険の高額療養費制度があれば問題なく支払いが可能だと考えていいだろう。
だとすると、少なくとも損得の問題としては、がん保険に加入しないことが正しいと考えられる。
因みに筆者がこれまでに書いたり話したりしてきたこととの関連では、今回癌になってみて、公的年金の受け取り時期の問題が少々微妙になった。これまでは、世間の平均余命ベース(つまり生命表ベース)で考えると、公的年金の受給開始を遅らせて年金額を増やす方が(期待値としては得になるくらい長生きするので)得な決定のはずだったが、今回の発癌で筆者の余命の期待値は大幅に縮んでいるはずだから、公的年金はむしろ早く貰い始める方が得になる公算が大きい。但し、当面年金以外の所得がそこそこにあるので、税金を考えると、今から公的年金を受け取り始めるのは、やはり得ではないかも知れない。
髪の毛や酒の「真の損得勘定」
癌と診断されて意外に気になったのは髪の毛のことだった。髪が抜けたら人前に出る仕事がしにくくなるだろうし、外見の印象がすっかり変わってしまうということが、後から振り返ると過剰なくらい気になったのだ。手術が上手く行くかとか、抗癌剤が効くかといった問題については、自分で改善出来ることが殆どないので、髪の毛の問題をどうするかに意識が向いたということがあったかも知れない。
筆者が利用する抗癌剤では、髪の毛が抜けることがほぼ不可避で、また髪の毛が抜けるとしても頭皮がツルツルに見えるようにすっかり抜けて、その後に一斉に生えてくるといった「ドラマのような綺麗な抜け方・生え方はしない」(病院の某看護師の言)と想定しなければならなかった。
実際に髪が大量に抜けたのは、一回目の入院の数日後からで、抜け方は「まだら」で確かに綺麗とは言えない状態になった。事前に用意していたバリカンで残った毛をごくごく短く刈って、ニット帽を被ることにした。
髪の毛が抜ける前には、動画で撮りだめが利くものを数本撮った。「いつ復帰できるか、分からないな」とやや暗い気持ちになった。
しかし、坊主頭で過ごすうちに、次第に自分が坊主頭であることに慣れてきた。鏡を見慣れたのだと言っていいかも知れない。「これで不都合はないではないか」と思い始めた。
まだらに伸びてくる髪の毛を何度かバリカンで刈り揃えて時々坊主頭をリセットしていたのだが、毛が抜け始めてから4ヶ月程度経った本稿執筆時点では、「密度」がかなり回復してきたことが実感され、そろそろ元の状態を目指して毛を伸ばせるかと思える段階に至っている(現在毛足は1センチ平均程度)。
ところが、坊主頭である自分を徐々に不自然だと感じないようになってきた。そして、これでいいと割り切ると、大変便利だ。洗髪は簡単だし、寝癖もすぐに直るから手入れは不要だ。自分でバリカンを使うことに慣れたら、ヘアサロンや理髪店に行く必要もない。
ヘアサロンや理髪店は、直接支払う料金もさることながら、施術時の時間、前後の移動時間、予約する場合日時を固定されることによる不自由のコストなど、実は「時間」に掛けるコストが大きい。一年に250日働いて一日8時間労働とすると年収1千万円の人の時給は5千円であり、年収が2千万円なら1万円の計算だ。実感として「それほど根を詰めた時間の使い方はしていないから、散髪の時間に問題はない」と思うかも知れないが、時間が掛かっていて、潜在的なコストが発生している事情に変化はない。
筆者の場合だと、前後の時間も含めると散髪の時間で短い原稿が一本書ける計算だ。同じ時間に対して、お金を支払っているか、収入を得ているかの出入りの差はそれなりに大きい。
読者にとってどうでもいいはずの筆者の髪の毛の話を詳しく書いている理由は、筆者のかつてのヘアスタイルのコストに相当する支出や時間の無駄を、人はその他の分野でも多く行っているのではないかと思うからだ。
ビジネスの状況も広く含む「他人からの評価」を考えてみよう。筆者の髪の毛が、年老いた銀行員のような白髪半分の七三分けであろうと、アスリートでもないのに数ミリで揃えた坊主頭であろうと、筆者以外の人にとってはどちらでもいいことだろう。毛が多い方が書き物や話に説得力が生まれるわけでもないだろうし、まして書籍が余計に売れるわけでもない。
「実はどうでもいいこと」を意識しているのは、過剰な自意識と、社会的同調から逸脱することへの恐れ、加えてそれらを巧みに刺激する「マーケティングの魔術」の効果によるものだろう。
意識を変えて拘りを捨てることで、直接的にコストが節約できたり、時間が節約できたりするケースは少なくないはずだ。ヘアスタイルはその一例であり、他に、ファッションや各種の人付き合いのイベントへの参加などがあるだろう。対象は様々であり得るのだが、「実はどうでもいいこと」を見つけ出して捨てることの効果は実に大きい場合がある。
さて、筆者にとって、ヘアスタイルよりも費用的にたぶん一桁大きなお金と時間と両方の支出項目が「酒」だった。
常識的な推測として、酒だけが原因でないとしても、筆者の食道癌に過去の飲酒は関係していただろう。2022年の8月24日に「食道癌です。禁酒して下さい」との宣告を主治医から受けて以来、現在まで全く飲酒していない。
それまでに、「過去10年間で、全く飲酒していない日は3日あるかないかだ」と言えるくらいお酒を飲んでいた。近年では、新型コロナのワクチン接種一回目の当日に全く飲まなかった日があったことを想い出す程度だ。
お酒は、それ自体が楽しみだったし、過去に人間関係を拡大する上で大いに役立ったし、趣味的な満足もあった。また、広義のコンサルティングや営業的な活動にあって、飲酒や食事を十分に付き合えることはビジネス上有力な武器だ。
因みに、飲食の付き合いの効果は過小評価しない方がいい。一緒に飲めない、食べられない人物は、ビジネスなどの相手から見て「つまらない人」であり(たぶん恋愛の相手としても同様だろう)、これを十分にカバーするためには相当に高度な話術や練り込まれた人格が必要だ。相手が飲んだり食べたりに時間だけ付き合ってお金を払えばいいというものではない。美味しい食べ物の味が分かって一緒に食べられる人、お酒の味が分かって一緒に飲める人の価値は他の条件を一定とすると「分からない人」よりも有意に大きいのが現実だ。拙文を読んで禁酒しようとする読者がいたら、「よくよく考えてからにして下さい」と申し上げる。
しかし他方で、筆者にとって、お酒は、それなりに多大な支出につながっていたし、仕事の時間や体力を奪っていたことのコストも計算すると小さくないはずだった。
通算の損得はとても計算しきれるものではないが、近年の「飲酒関連評価損益」はマイナスに傾いていたように思う。お金も時間も使いすぎていた。
医師の指示による強制終了が切っ掛けだが、禁酒はそれなりに苦しいものだと思っていたのだが、それが殆ど苦しくなかったのは自分でも少々意外だった。
禁断症状的なものは全くなく、宣告を受けた翌日から飲酒を止めた。筆者にとって飲酒は、精神的には強い習慣になっていたが、肉体的な依存性はなかったということだろうか。今もスッキリ理解できているわけではないのだが、飲酒を止めることは案外簡単にできた。
周囲でお酒を飲む人を見て、「楽しいのだろうなあ」とか「あの酒はこんな香りと味がするはずだ」とかは思うが、どうしても自分も飲みたいというような生理的な欲求は湧かない。
現在、禁酒によって生じた精神的な「穴」は、珈琲と各種のお茶を、趣味的な要素も含めて熱心に飲むことで一部を埋めている。
一方、幸い医師に禁止されなかったので飲むことが出来たのだが、珈琲を我慢することはかなり辛いと感じた。実はお酒よりも強い習慣性があったのだろう。珈琲は趣味性の強い嗜好品なので、人によって好みがある。病院の入り口には、世間的には有名な珈琲チェーン店があるのだが、その珈琲はとても飲みたい気がしない。
入院中は、妻にしばしば珈琲を差し入れて貰った。当時、新型コロナの感染症の問題があって、家族も含めて外部者は一切病室に入ることが出来ず、荷物の手渡しだけが可能だった。
ある日、妻が珈琲を持って来てくれたのだが、入院フロアの事務職さんが「たぶん、娘さんが珈琲を持ってくれました」と間違えて報告してくれた。このことの効果は絶大で、間違いが時に人を幸せにする場合があることを知った。差し入れの珈琲の頻度と品質が上がることで、筆者もその恩恵を受けた。
退院すると、いつでも好きな時に、自分の好きなように珈琲を淹れることが出来るのは大変幸せである。
何でも「お金だけ」で考えるのは良くない習慣だが、ヘアスタイル、ファッション、飲酒、趣味、人付き合い、など様々なものを、潜在的なコストも含めて「お金でも」考えてみると、生活習慣を見直すきっかけになる。「実はどうでもいいこと」を一つ見つけるだけで、生活を大きく改善できる場合がある。
因みに、筆者は、お酒を止めたことで、大学生の子供一人分の仕送りくらいの費用が浮いたと計算している。子供が大学に行っている間は禁酒すると決めるのが、中間目標としてちょうどいいかも知れない。



















































![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)
![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)
![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)
![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

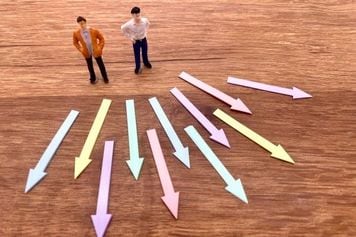
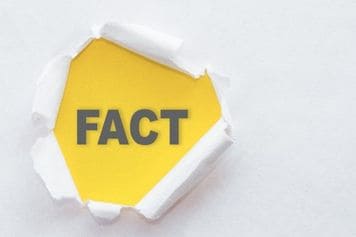














![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)











![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)












![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)
![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)
![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)





