日銀はリーマン危機後も東日本大震災後も大胆な金融緩和に動かなかった。しかし、日本の家電産業の崩壊、国策企業エルピーダメモリの倒産などによって、「円高とデフレ」を日銀のせいにする政治家の声がうるさくなり、遅すぎた緩和と言われながらも2月14日にはインフレ目標を掲げ日銀はデフレ脱却を宣言した。
「日銀法を改正し、総裁を国会で決める(政府が人事権をもつ)」などの政治的圧力がかかったため、仕方なく動いたという感じだ。しかし、2月14日の決定は市場にとって大きなサプライズとなり、ECBによる100兆円のバラマキに次ぐ「バブル相場の号砲」として投資家の注目を集めた。
欧・米が大規模な量的緩和を終えて様子見となっている地合で、海外投資家は日銀が「周回遅れの量的緩和をこれから行う」というという感触を持ったため、円売りと日本株買いに動いた。これが2012年1Qの日本のバブル相場の背景である。
日本の量的緩和をあてにしていた海外勢を驚かせたのが、2月14日以降のマネタリーベース(日銀当座預金+日銀券残高)の収縮である。日銀が供給するマネタリーベースが落ちている事実を3月23日付の英フィナンシャルタイムズ紙が「円安基調は本物か、日銀次第で反転も」と報道し、日銀の姿勢に外人投資家は疑心暗鬼となった。
それ以来、「日銀はデフレ下の増税(やっても効果がないけど…)を標榜する財務省や政府から圧力を受けて追加の緩和を発表したものの、見せ金(枠)だけ増やして実際の紙幣増刷は行わず政府の緩和要請に抵抗している」というネガティブな観測が増えている。
ドル/円(日足)支持線・抵抗線
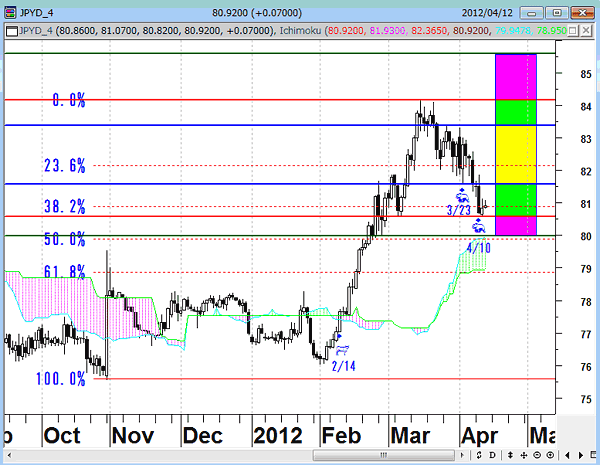
(出所:石原順)
日銀は3月の追加緩和を見送ったが、3月中から「4月27日の展望レポートの発表とあわせて追加緩和を行う」という観測が一人歩きし、半ば織り込み済みとなっている。こうしたなか、4月10日の日銀政策決定会合は上記の日銀に対するネガティブな見方を覆す絶好のチャンスであった。ここで追加緩和のサプライズあれば、株高と円安に切り返したと思われるが、日銀は「現状維持」を決めて市場の緩和期待を牽制した。為替関係者の間では、「4月27日の会合で小出しの緩和しかないようだと、しばらく円相場は79~82円程度のレンジ相場になるのではないか」と言われている。
日本のマネタリーベースと日経平均株価の推移(2005~2012年月足)
マネタリーベースが増加しないと、円高・株安に逆戻り?
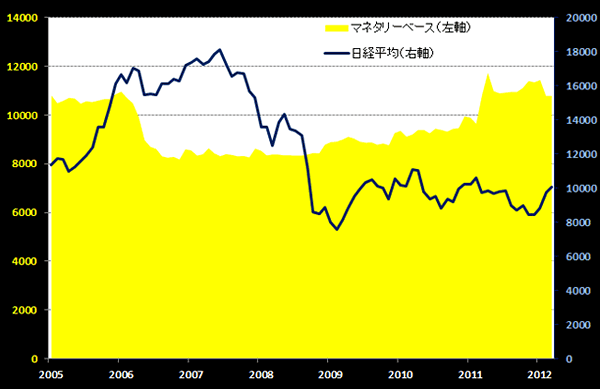
(出所:石原順)
リーマン危機後の市場は、中央銀行によるバラマキで維持されているだけだ。それで景気回復までの「時間稼ぎ」をしているのである。したがって、「催促相場の連続」できりがないが、仕方がないだろう。この中央銀行相場におけるポイントは、中央銀行が市場の期待を裏切ると催促相場が展開されることだ。追加の金融政策が出るまで市場は催促相場を続けるので、可能性は低いが4月27日の日銀金融政策決定会合で追加緩和が見送られるようなことになれば注意が必要である。
公共事業などの財政政策と違って、金融政策など所詮「見せ金」の世界だ。どんどん緩和すればよい。2012年に入りやっと日本株もドル/円も上昇基調になり始めたのに、日銀が動かないことに海外投資家は失望している。「日本は20年も不景気をやってきて、何を考えているのか」と…。米国では雇用統計の悪化から6月QE3観測が再燃している。欧州もスペインやイタリアで金融危機が囁かれている。市場が嫌う「催促の後の予定調和」という路線を歩んでいる日銀だが、追加緩和が後手にまわるようだと緩和効果は限られ、周回遅れの緩和での円安アピールが薄れてしまう可能性がある。
既に海外の新聞では1年後の日銀総裁の候補が取り沙汰されている。候補者は財務省のOBばかりだ。このような観測記事を誰が流しているのか知らないが、「組織防衛」のため後手に廻りながらも日銀は緩和に動かざるを得ない。したがって、今のところ日本株の大幅な下落や急激な円高の再開を予想する声は少ない。
日銀への過度の期待がしぼんできたなかで、わかりにくい相場の流れが続いている。どの市場も「場味のいいところ」を買ったり売ったりすると報われず、投げと踏みの応酬(買い方も売り方も損)という相場つきだ。
4月26日の米FOMCや4月27日の日銀金融政策決定会合までまだ時間がある。この端境期に我々は何を頼りに相場に参戦すればいいのだろうか? 多くの運用者が4月後半の米・日の政策会合までは、NYダウ連動の相場が続くと観ている。日本株も円相場も株次第だ。それしか、頼りになる指標はない。
NYダウ(日足) 2011年7月~2012年4月
フィボナッチのリトレースメント(青・点線)とファンライン
上昇トレンドライン(赤)を割り込み調整中
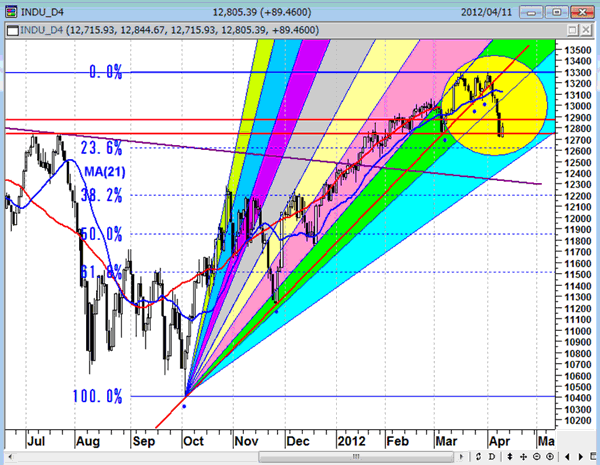
(出所:石原順)
NYダウ(週足) 米国の量的緩和政策とNYダウの推移 2008年~2012年
量的緩和効果の息切れ感が漂う中、米株関係者のQE3に期待する声は多い
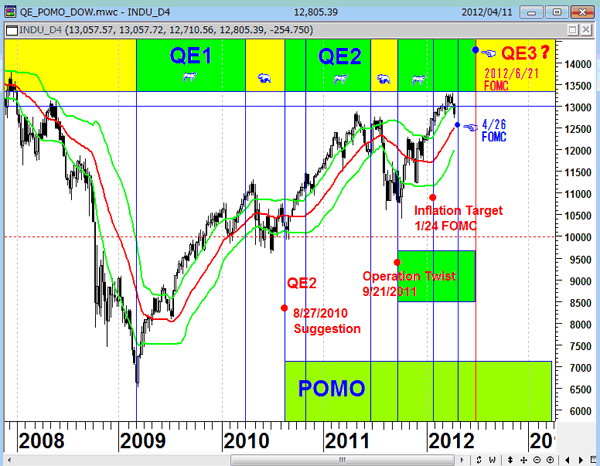
(出所:石原順)
欧州の危機再燃観測、中国の景気不透明感、米国の雇用・住宅問題など、相場の「不確実性」や「複雑さ」を増幅する材料が増えている。これらを払拭し世界規模で相場を上にもっていけるのは、米国のQE3の発動だけである。
為替の歴史は米国の政治の歴史、日本株も概ね米国株連動相場だ。欧州・日本と続いた量的緩和の流れは、自然と米国のQE3期待へと波及していく。「不胎化QEで過度のドル安を避けつつ、株高に持って行く」というのがバーナンキFRB議長のシナリオだが、4~6月期の相場はその手前の過渡期と言えるだろう。米国の量的緩和は本来ドル安要因だが、円相場に関しては米国の株が上がればクロス円やドル/円も上がることになろう。
さて、ドル/円相場の動向である。日銀の優柔不断な決定で上値も重くなっている。そのため理想的な円安循環の流れは断たれたが、日銀は「政治的圧力で量的緩和を継続しなければならない状況」にある。したがって、大幅な円高というのも想定しにくい。
3月14日高値84円17銭からの下落は一旦止まるところにきている。市場が注目している一目均衡表週足の<雲>の上限まで下がったからだ。長年にわたりドル/円相場の<抵抗帯>となってきたこの雲は、2012年2月から<支持帯>に変化している。その下の80円20銭付近には最強のサポートである20カ月移動平均線が控えており、NY終値でこれらの支持線が破られない限りは80~82円といったレンジ調整が続くだろう。
ドル/円(週足)と一目均衡表の<雲> 強力な支持帯
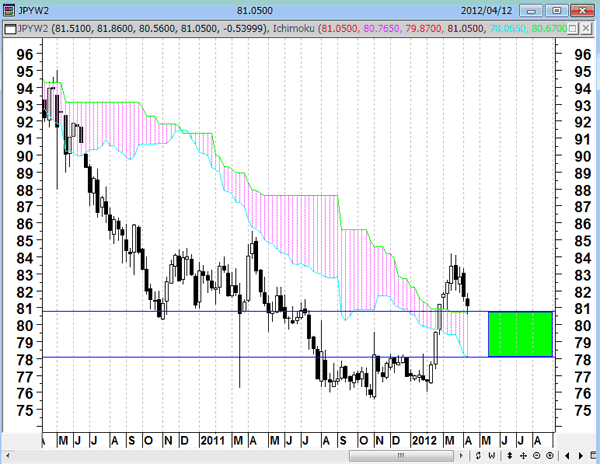
(出所:石原順)
ドル/円(月足) 20カ月移動平均線 4月12日現在、80円20銭付近に位置している
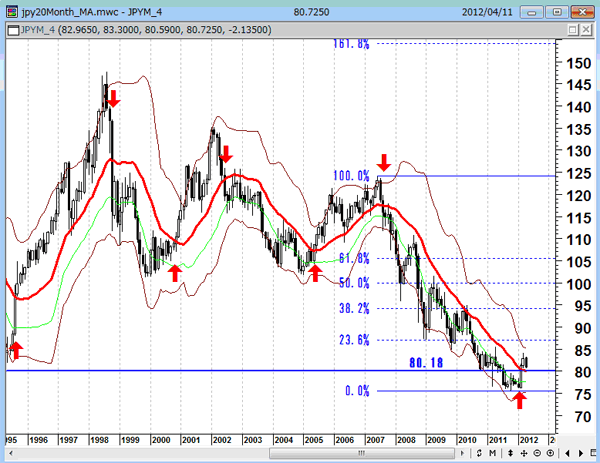
(出所:石原順)
ドル/円(日足) フィボナッチとギャンのファンライン
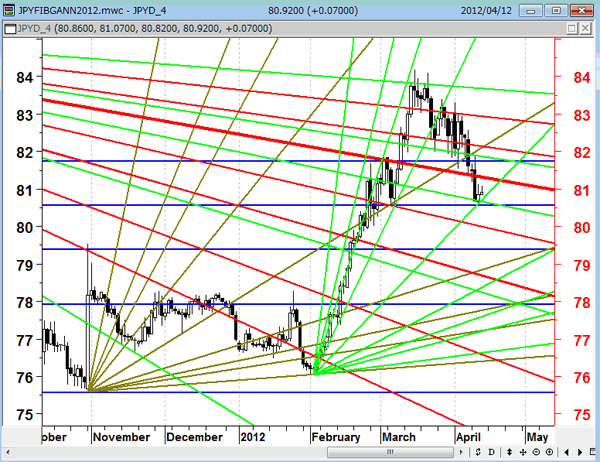
(出所:石原順)


















































![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)
![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)
![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)
![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)





















![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/356m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)
![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/356m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)






![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

















![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)
![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)
![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)



