大間違いその2:運用期間でリスクを決める
運用でどれだけ大きなリスクを取っていいかを決める主な要因は、個人でも企業年金のような機関投資家でも、「運用期間の長さ」ではなく、「財務的な強さ」だ。
若い人が運用する金融資産の中で株式などのリスクを取る資産の割合を大きくしていい「傾向」があるのは、若くて健康な方はこれから長年稼ぐことが予期できるので「人的資本」が手厚いことと、そもそも金融資産の額が小さい場合が多いことの2点が主な理由だ。
一部で信じられている「運用期間が長くなると、リスクが縮小するから」という理由は、その説明自体が間違いだ。運用期間が長期化するほど、運用資産額が取り得る上下の値の範囲は拡大する。
もちろん、期待される平均額もリターンがプラスなら時間と共に増えていくと考えられるから、運用期間が長期化した場合に、リスクが拡大するから、リスク資産への配分を減らす方がいいということではない。リターンの現れ方がランダムで、投資家のリスクに対する拒否度が一定であれば、運用期間の長短はリスク資産への配分に対して中立である。
しかし、運用期間によってリスクの大きさが変わるべきだと書いている運用の入門書は世の中に多いし、ロボアドバイザーを標榜する資産運用アドバイスのエンジンには、運用期間によってリスク拒否度を操作していると思しきものがある。
運用期間の長さをリスク許容度に相関させて大失敗した例としては、1990年代から2000年代前半にかけての、日本の企業年金がある。多くの厚生年金基金が、「御基金はまだ成熟度が低いので、リスクを取ることができます」という運用会社のセールスに乗せられて、過大なリスクを取って苦境に陥った。正しくは、基金の財政状態と母体企業の財務的強さこそが、リスク許容度の決定要因だったのだ。
では、個人投資家は、リスクをどのように考えたらいいか。一つのヒントとして、本講演では、「360」(65歳から95歳までの月数)で資産の増減額を割り算し、たとえば360万円損をした場合に、「老後に取り崩すことができるお金が月に1万円減った」と考えるやり方を紹介している(図1参照)。
(図1)

ストックの損得を、老後の毎月のお金というフローに換算して、実感を想像しやすくしてみた。




![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)








![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

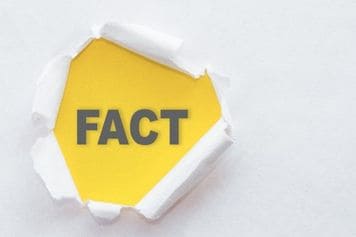














![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)






















![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




