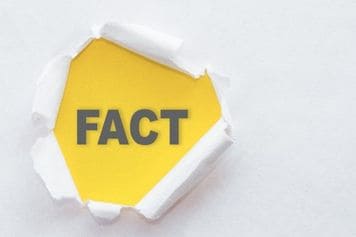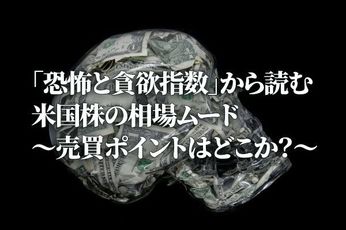※本記事は2015年11月20日に公開したものです。
「好み」と「アドバイス」は異なる
人間は後悔することが嫌いな動物であり、特に自分の努力の価値を後から否定するのは苦痛だから、この種の価値観は修正されにくい。加えて、運用には「運」の要素が多大に入り込むから、自分の仮説に合った事例と出会うことが多々あって、方法論が丸ごと否定されることが少ないという事情もある。
筆者も例外ではない。筆者の大袈裟にいうと「運用観」の原点は、最初の転職で入社した投資信託運用会社でファンドマネージャーの仕事を始めた頃に形成された。商社に勤めていた時に小さいながら自分でポジションを持った外国為替の売買でマーケットの経験はあったが、株式投資はそれが初めてだった。ちなみに、本稿では詳しく触れないが外国為替のトレーディングと株式投資には、似ている点と大いに異なる点がある。
株式でのポートフォリオ運用を始めるにあたって、筆者は、初心者向きの入門書から当時は少なかった投資の教科書まで含めて株式投資に関連する本を数十冊読んだが、本よりも参考になったのが、同僚(9割以上が先輩)のファンドマネージャー及びアナリスト諸氏の行動とその結果だった。
筆者が勤めた投信会社は、当時業界最大手だったし、何よりも親会社が最大手の証券会社であったから、アナリスト、ストラテジストなどの手になる情報が豊富に入ったし、会社も当時としては運用組織の体をなしていた。相対的な「情報環境」は悪くなかったと思う。
しかし、この情報環境の優位性は、運用成果の優位性にはさっぱりつながっていなかったのだ。当時、この会社では、社内の管理システムを通じて、他のファンドマネージャーのポートフォリオを見ることが出来た。
すると、(1)親会社や自社のアナリスト情報を売買に活発に反映させ、(2)会議でも良く発言し概して社内評価が高い、(3)仕事へのモチベーションが高い真面目な、ファンドマネージャーの成績が、平均よりも悪いことに気づいた。
また、ある時、当時の社長さんが「お前らみんな積み立て株式ファンドに負けているのはどういうことだ」と言っているのを耳にしたのだが、「積み立て株式ファンド」とは、日経平均をターゲットにしたインデックス運用をするファンドだったのだ。筆者の心の中で、「我が社でやっているような、オーソドックスなアクティブ運用はどうやらうまく行きにくいようだ」という直感が、「たぶん、そうなのだ。それにはもっともらしい理由があるはずだ」という強い仮説(「皮肉屋仮説」とでも名付けておこう)に変わった。
先輩達のポートフォリオを見て感じたことは、(1)集中投資よりも分散投資の方が好成績であること、(2)売買回転率の高いポートフォリオの成績が良くないこと、(3)市場で話題の銘柄、親会社が推奨している銘柄のリターンが市場平均並みかむしろ低いことなどであり、市場平均に積極的に勝ちに行くことが難しいことだという実感だった。
アナリストと共に企業を訪問したり、会議に出たり、レポートを読んだりといったことももちろんやらされたが、「企業を訪問して社長の話なんて聞いていても表面的な事しか分からないのではないか」という実感を持つことが多かったし(元商社マンなので、商社のレポートを読むと特にそう思った)、加えて「企業も自社の株価について分かっているわけではないのだから、社長や財務部長(当時は「CFO」という言葉が未だ普及していない)と話しても無駄だ」とも思うようになった。
この時にリサーチして投資した銘柄でたまたま成功体験でもあれば、筆者はバリバリのファンダメンタル分析主義者になったのかも知れないが、幸か不幸か、ファンダメンタル分析主義者のミスや盲点を探す方にむしろ興味を持った。
当時、新米ファンドマネージャーとしてバランスファンドの運用を担当していた筆者が取った戦略は、(1)日本株は市場平均に近い業種構成に近づける(つまり当時のアクティブマネージャーが大好きだった「ハイテク株」のウェイトはライバルよりも下がる)、(2)株式部分のパフォーマンスでは積極的に勝負せずに得意(だと当時思っていた)の外国為替と外国債券で差を付ける、というものだった。後者は円高と外債の利回り低下のお陰で大いに奏功し、円高の恩恵もあって前者も好結果だった。
また、米国株への投資では、NYダウの30銘柄から、企業としてピークを過ぎたように見えるのに内外のファンドマネージャー(ピーター・リンチなども含めて)が大好きだったIBMだけを外して29銘柄を買うような調子でポートフォリオを作ったが、これも上手く行った。
新米ファンドマネージャー時代には大いにビギナーズ・ラックに恵まれたが、そのお陰で、筆者の「皮肉屋仮説」は否定されることなく、すくすくと育った。






















































![[動画で解説]日銀、12月利上げへの準備進める~10月「主な意見」でここまで分かる~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/6/498m/img_86a553b9b7b1414e097c04666bbf745b97077.jpg)
![[動画で解説]トランプ2.0で退場を迫られそうな人の特徴(吉田 哲)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/498m/img_187bb160d07a9e42a994f631d324e5f856871.jpg)
![[動画で解説]米国株最高値の裏に、5つのトランプ・リスク(窪田 真之)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/498m/img_87e1489c5344018fcc304b5d65fe09da43349.jpg)
![[動画で解説]銘柄レポート:スーパー・マイクロ・コンピューター(NASDAQから10K提出期限延長の承認を得る必要がある)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/9/498m/img_39f7e5c7ac86401ea69f3be820f888f797328.jpg)