2.リスクを過小評価させる仕掛け
バブルが形成され拡大するためには、投資の主体が「リスクの割に儲かるだろう」、或いはそれ以上に「損はしないだろう」と思って、投資にのめり込むことを正当化するような、「リスクを過小評価させる仕掛け」があるといい。
米国のサブプライム問題の場合、リスクのある住宅ローンでも地域も含めて分散投資するとリスクは小さくなるはずだと説明され、格付け会社もAAA、AAなどの高格付けを与えた証券化商品が住宅ローンへのリスクを過小評価させる仕組みとしてバブルの形成に寄与した。実際には、住宅ローンの物件や地域を分散しても、米国の不動産価格が全般的に下落するリスクは解消できなかった。
また、証券化商品の高格付けは、次の商品の格付け依頼を貰って手数料を稼ぎたい格付け会社による利益相反でゆがんだ不適切な情報だった(注:格付け会社は格付け対象の発行体から格付け手数料を貰う。これは、大きな欠陥を持った仕組みだ)。
日本のバブルの背景にも、日本の地価は下がらないのだという「土地神話」、企業が行った資金運用を受注する際に信託銀行や証券会社が行った利回り保証(俗に「握り」。当時も違法だったが広範に行われた)、などが地価と株価の両方をバブルに導く効果を持った。
現状では、かつての「握り」のようなひどい仕組みがある訳ではないが、政策当局が株価下落を好まないことが「暗黙のプットオプション」のように、投資家にとってのリスクテイク支援材料になっている面がある。
日本の投資家は、「株価が大きく急落したら、日銀がETF(上場投資信託)を買って支えてくれるだろう」と幾らか思っているし、世界の投資家にあっても、日銀のように中央銀行が直接株式を買わないまでも、経済や市場の調子が悪くなれば金融緩和と財政支出を合わせた政策的支援材料が発動されると期待している面がありそうだ。
「リスクを過小評価させる仕組み」については、現状で、かつてのバブルほど露骨な誤認へ誘導する仕組みがあるわけではないが、市場参加者が認識する「政策プット」がリスクの過小評価を生んでいる面があるかも知れない。
尚、バブル期にしばしば登場する特徴的な現象として、高い資産価格を正当化しようとする珍説の登場が挙げられる。
日本のバブルの最中(1988年)には、ある東大教授が「Qレシオ」(時価評価した純資産によるPBR[株価純資産倍率]のようなもの)なる指標を使って、日本の株価は高すぎないと論じた。企業が保有する不動産価値を考えると株式の時価総額は過大でないとの議論だったが、両方がバブル状態にある地価と株価を比較しても、株価がバブルでないことの根拠にならなかった。また、土地よりも株式の方が頻繁に取引されて価格形成が行われているのだから、土地の価格形成が株価よりも情報を先読みするかのような解釈は不自然だった。その後、先に下がり始めたのは株価で、地価の下落は後に続いた。
2000年にかけての、米国のネットバブルでも、ネット企業の成長が無限に可能であるかのような「ネット企業神話」があったし、高すぎるPER(株価収益率)を正当化する「PEG」(PERを成長率の「%」で割る)といった、理論的根拠が薄弱な株価指標が登場するような現象があった。




![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)








![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

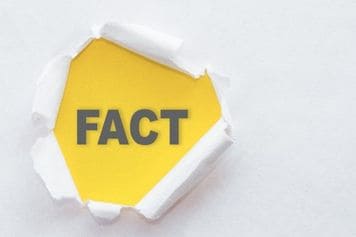














![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)






















![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




