掟その3:目指すリスクとリターンは同時に決める
年金運用では、前提として、年金制度があり、将来の支払い義務としてのライアビリティを意識しなければならない。しかし、年金制度が一方的に年金運用に達成すべき目的を与えられるのかというと、それはちがう。
たとえば、日本の公的年金の運用で行われているように、いくらのリスクを取るのかを明示的に検討することなく、「賃金上昇率+1.7%」といった形で、年金運用の目標リターンを決めることは、全く不適当である。
この件に関しては、1990年代から2000年代にかけて、企業の厚生年金基金の多くが、「5.5%」という予定利率で設計されて、低金利の環境下にもかかわらず基金がこの利回りの達成を目指して、無理なリスクを取って、多くが大失敗した歴史が、典型的な悪しき先例として参考になる。
運用で負うリスクと、求めうるリターンとを考慮した上で、年金そのものの制度設計を行ったり、財政検証を行ったりする必要があるのは当然のことだ。
掟その 4:運用期間ではなく財務体力がリスク耐性を決める
企業年金でどのくらいの大きさのリスクを取っていいかを決める主たる要素は、母体企業の財務的な体力と、リスク負担の意思だ。
ところが、日本の企業年金基金では「基金の成熟度が低いと、運用期間が長く、期間が長いと大きなリスクを取ることができる」と誤解をして、過大なリスクテイクに走ってしまった。「運用期間が長期になると、リスクは縮小する(ので、より大きなリスクを取っていい)」というのは、金融論的には完全に誤りだ。
1990年代から2000年代にかけての、低金利や株価の低迷といった不運な環境の問題はあったが、日本企業が企業年金で巨額の損失を出し、代行返上や基金の解散に至ったことの大きな原因がここにある。
積立方式ではなく、賦課方式の日本の公的年金の場合、企業年金の母体企業に相当するリスク負担の主体は誰であろうか。現在の年金加入者のようでもあるが、当面の運用失敗の影響は、将来の年金保険料を負担したり、年金給付を削られたりする、もう少し若い方に重心をずらした世代が真の負担者のようでもある。賦課方式であり、広義の社会保障の一部であることを考えると、将来世代もある程度含めて納税者一般がオーナーであると考えるのが妥当かもしれない。
そう考えると、年金に関するあれこれを、全面的に厚生労働省に任せる仕組みは不適切なのだろう。




![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)








![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

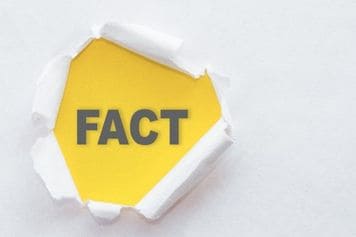













![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)






















![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




