インデックス・ファンド運用方法のあれこれ
インデックス・ファンドは、運用資金が大きくなった今では、ターゲットとする指数の構成通りに全銘柄を買う「全数法」とでも言うべき方法が主流だが、1980年代後半くらいの時代は、ターゲットとする指数にもよるが、全銘柄を買うのは大変だし、売買手数料などの上でも効率が悪かった。
インデックス・ファンドには、簡便法的な運用方法があった。
ある外資系の運用会社のファンドマネージャーが、「層化抽出法」と呼ばれる運用方法を得意げに説明してくれたことがある。時価総額ウェイトの指数を構成する、時価総額上位の銘柄を100銘柄くらい指数の比率通りに持って、残りの銘柄は、時価総額の順番に並べて数銘柄おきにポートフォリオに加えるような簡便法だった。残念ながら有難味を感じなかったのだが、そのような方法が「ノウハウ」だった時代もあったのだ。
その後、「全数法」以外のインデックス運用を行う場合は、BARRAモデルを代表とする、株式ポートフォリオのリスクを分析するマルチ・ファクターモデルと呼ばれるツールが普及して、最適化計算で大小のインデックス・ファンドを作ることが出来るようになった。例えば、当時1,000銘柄を少し超えていたTOPIX(東証株価指数)のインデックス・ファンドを、100銘柄、200銘柄、300銘柄と、希望の銘柄数に応じて最適な銘柄と株数を計算できた。
筆者は、自分がインデックス・ファンドを運用していた訳ではないのだが、マルチ・ファクターモデルの使い方に習熟していたので、いろいろな条件でファンドの銘柄とウェイトを計算してみた。
因みに、当時のBARRAモデルでは、ターゲットとするインデックスを選び、銘柄数を決めて、PCの「F6」のキーを押すと簡単にインデックス・ファンドのポートフォリオが計算できた。尚、当時のPCでは計算に数分掛かった。
当時の筆者の興味は、100%アクティブ運用にあったので、さまざまな条件で「インデックスからほどよい乖離のリスクを持つアクティブ・ファンド」を計算して、調べることが、ファンドマネージャーとしての実質的な仕事だった(ファンドの運用自体は、保有する株式が勝手に稼いでくれる。研究こそが運用だったし、研究の応用は上手く行った)。
現在の「スマート・ベータ」と呼ばれるような運用は、当時の筆者が研究したり運用したりしていたポートフォリオの運用を、単純化して雑にしたようなポートフォリオだ。「バリュー効果」、「高配当」、「最小分散」、「小型株効果」、「リターンリバーサル」、「アーニング・サプライズ」など、今ではポピュラーになったアイデアをあれこれ試していた。
当時を振り返り、今と比較してみると、ファンドの運用に関する理論や応用が意外なくらい進歩していない。利用できるデータの量と処理ツールは大いに進歩しているはずなのに、アイデア自体はそう簡単には進歩しないものらしい。
ファンドマネージャーである当時の筆者にとっては、「インデックス」は手強い評価基準であるところの「ベンチマーク」としての意味が大きかった。投資理論の教科書を読んだり、海外の論文を調べたりするほどに、米国でも、日本でも、「アクティブ運用の平均は、インデックス運用に負けている」という事実の重みを感じた。
インデックス運用による株価の「歪み」
1990年代に入って、まだ今ほどではないが、インデックス運用がそこそこの規模を持つようになった。
すると、インデックスの構成銘柄で、市場で流通する浮動株が少ない銘柄が、インデックス・ファンドの買いによって、実力以上に株価が上昇する「歪み」が時に目に付くようになった。代表的な銘柄としては、当時の日経平均採用銘柄の片倉や、ネットバブルの時期(1990年代末期)のソフトバンク、光通信などが、挙げられる。
インデックス運用が株価を歪めることがあるのか、との認識を持った。
この種の株価の「歪み」は、いかにも空売りのチャンスに見えるのだが、なかなか「しぶとい」ものなので、注意が必要だ。
筆者と一緒に外資系証券会社で株式トレーディングを行った有能なトレーダーのN氏(現在は引退して「数百億り人」らしい)から、こうした銘柄の空売りでピンチに立ったことがあると、後日、「恐怖の物語」を聞いたことがある。













![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

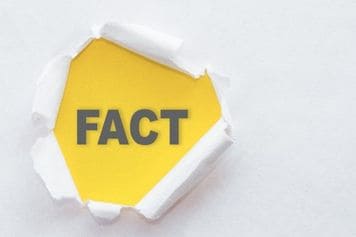















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)




















![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




