筆者は、30数年間に亘って何らかの形で資産運用に関わる仕事をしてきた。その間に、「インデックス・ファンド」とは、仕事で関係したり、著作や記事などで取り上げたり、印象的な関わりがいくつかあった。
但し、筆者は、インデックス・ファンドを直接運用したことはないし、インデックス・ファンドのセールスを仕事にしたこともない。以下、当事者ではないけれども至近距離にいた観察者のメモである。
初対面は1985年。「インデックス・ファンド、なかなかやるなあ」
筆者が、インデックス・ファンドというものを直接知ったのは、大手証券会社系の投資信託会社に転職して、しばらく経ってからのことだ。確か、「積立株式ファンド」という名前だったと思うが、その会社には、日経平均(当時の呼び名は「日経ダウ」)をターゲットにインデックス運用を行うオープン投信があった。少し皮肉屋で、親切な先輩ファンドマネージャーが運用していた(筆者に「株式を分割して買うことは無意味だ」と教えてくれた恩人でもある)。
さて、他の会社でもそうだが、当時の投信会社では特に社内で社長が「偉い」。その社長が、社内の会議で「お前ら、みんな、積立株式ファンドに負けているとは、いったいどういうことだ」とアクティブ・ファンドを運用している運用者達にカミナリを落としたことがある。年間の収益率の数字の上で負けているので、反論できるファンドマネージャーがいるはずもなく、かつては口八丁だったはずの元証券マンたち(当時、投信会社の社員は親会社からの転籍者が多かった)は、無言でうなだれていた。その中には、社内の会議で、株式市場の見通しや、投資候補銘柄の分析について活発に発言する先輩ファンドマネージャー達も含まれていた。
転職して間もない若手社員(当時26歳)だった筆者は、2つのことを思った。
「市場や企業を分析したつもりになって仕事をしている運用会社の社員たちの、運用パフォーマンス自体は案外たいしたことがないのだなあ。尊敬したり、憧れたりしない方がいいぞ」が1つ、もう1つは「それにしても、10人以上のファンドマネージャーが皆負けるのだから、何か共通の原因があるのだろう。たぶん、それは、売買手数料の重さではないか」という直感だった。サラリーマンとして適切な感想かどうかはともかく、事実としては、何れも正しかった。補足すると、当時は、株式の委託売買手数料が固定手数料の時代で、現在よりもずっと大きかった。加えて、証券系の投信会社としては、親会社である証券会社に、なるべく大きな手数料を落とすような売買を行うことが期待されていた。
インデックス・ファンドに対する初見の印象は、「インデックス・ファンドは、面白そうではないけれども、なかなかやるな」であった。
尚、当時、米国では既にインデックス・ファンドが複数運用されていたが、運用の主流からはまだ遠かった。米国の運用業界視察を名目とする投信協会の旅行に参加して、逆張りを売り物とするある運用会社を訪ねたとき、その会社が、S&P500のインデックス・ファンドも商品としていて、当時としては先進的な自動売買のシステムで運用していることの説明を聞いた。インデックス・ファンドの運用自体には興味を持たなかったが、説明者が、自動売買システムについて、「コンピューターのいいところは、人間のファンドマネージャーとちがって、証券会社の接待でメシを食わないことだよ」と言っていたのが印象的だった。



















































![[今週の日経平均と株式市場]バイデン撤退で荒れる米国市場、「カオス」相場の乗り切り方](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]【米日株/ドル円】金利大転換 負のスパイラル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/f/498m/img_8fbfc279050ee52c4455a50cb255123266911.jpg)
![[動画で解説]【再現性あり】新NISAで毎月10万円の不労所得戦略!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/498m/img_712b2a3f8e92e675a04bea2219b5a6f289395.gif)
![[動画で解説]次の節目は2029年?中国「三中全会」で見えた8つのポイント](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/1/498m/img_511b8885e7a23cb985eaf2cbedd16f0b44407.jpg)
![[動画で解説]投資詐欺にだまされないで!怪しい投資話のありがちポイント3選](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/498m/img_2d310c68f0e43c0c8d7958574e373aea44780.jpg)



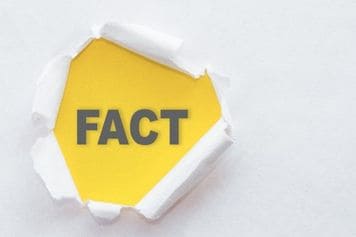













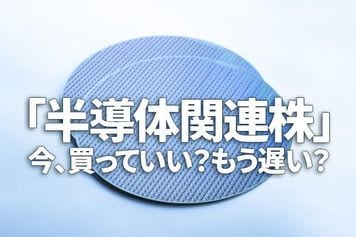





























![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#2 ~桐谷さん、パンパンの優待財布、中身を見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/5/160m/img_e524c4f2812a5f8075a30476512fbf6a66116.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が小幅回復。会社側は2025年への強い見方を示す)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_ce6a4295321b1700868a384a3e2aa8d944219.jpg)



