座談会での強気派と弱気派の意見
たまには相場の話をしよう。現在(2021年3月)の株価はバブルなのだろうか?
先日、ある雑誌の企画で、昨今の日米の株価がバブルであるか否かをテーマとする座談会に参加した。参加者は強気派の証券会社経営者(以下「強気氏」)、弱気派の学者(以下「弱気氏」)、そして両論の中間の筆者の3人だった。現在及び今後の株価について考える上でなかなか示唆的だった。
強気氏の意見は、現在、中央銀行の金融緩和とコロナ対策としての政府の財政支出により市中にお金が大量に出回り、「お金の価値に対する逆バブル」が起こっていて、株式や暗号資産のような供給の限られた資産の価格が上昇しており、現在の世界の主な中央銀行や経済閣僚のメンバーをこの「カネ余り」状況がしばらく変化するとは思えないので、株価は上昇しやすいはずであり、現状はバブルではない、というものだった。
一方、弱気氏は、バブルとは、株価水準云々以前に、「他人がまだ買うだろうから、自分も株を買う」という動機で株が買われる状態であり、米国のゲームストップ株を巡る諸々の現象などを見ると、現在既に佳境に入っており、株価はいつ大幅に下落してもおかしくない、即ち、「現状の株価はバブルだ」と考えるべきだというものだった。彼は、株式市場における心理の要因を重視している。
筆者の意見は、現状の株価形成要因はバブルの特色を十分に備えており、また株価は高過ぎる水準に入り始めているが、バブル形成の要因が強固であることから、株価の上昇はまだ続く公算が大きいのではないか、というものだった。両者の折衷案とも言えるが、具体的な株価レベルを気にするべきだという点がお二人と異なっている。
さて、鼎談は勝ち負けを目的とするものではないが、強気氏の「お金に対する逆バブル論」は、何らかの不自然な力でお金と株価との相対関係が変化しているということを述べており、現状の株価にバブルの要素が含まれているということなので、現状の株価が「バブルである」ということについては、3人の意見が一致したと見ることができるのではないか。
また、株価上昇の原因が、先進国の金融・財政政策による「カネ余り」であるという点については、3人の意見は完全に一致していた。
以下、バブルの特徴的な要素の幾つかについて、検討してみよう。
バブルの「特徴」に関する点検
1.借金の主体
以前にこの連載でも述べたように、バブルは、過剰な借金が資産への投資に回ることで起こる現象だ。
1980年代後半の日本のバブルでは、借金で「財テク」(財務テクノロジーを略した言葉。株式等での運用で収益を稼ごうとする事業会社の行動を指す)に励んだ企業や、不動産開発に借金を重ねたデベロッパーなどが借金の大きな借り手に育ち、その後バブルが崩壊することによって返済が難しくなって、貸し手(主に銀行)の健全性に危機が及ぶようになって、日本経済の長期停滞の大きな原因になった。
サブプライム危機を経て、リーマンショックに及んだ世界金融危機の前のバブルでは、主に米国で信用力の弱い借り手が借金できる仕組みが稼働して、住宅に過剰な投資が流れたのがバブルを発生させた「無理な借金」の源だった。
信用取引などの経験のある方は実感できるだろうが、借金をして作った投資ポジションは「弱いポジション」であり、値下がりを堪えて持ち続けることが難しい。振り返ると、日本のバブル時の財テクも不動産投資も、また、米国のサブプライム層の住宅ローンも「弱いポジション」だった。
今回の株価上昇を振り返ると、2019年末くらいまでの主に米国株の上昇は「社債等で資金調達した企業の自社株買い」といった、企業が財務的な健全性を損なうような借金が見られた点に懸念があったが、この状況はコロナの問題で一変した。
特にFRB(米連邦準備制度理事会)と米国政府は、信用リスクのある債券までも購入対象とすることによって資金を供給し、その結果、借金の主体が、企業から政府(財政学的には中央銀行も政府の一部だ)に置き換わった。
言うまでもなく、借金の主体として、民間企業や個人よりも先進国政府の方が強力だ。政府がお金を借りて、お金を使い、これが株式等の資産への投資に回るという資金循環は続くのではないか(むしろ、止められないのではないか)という、先ほどの鼎談の強気氏の見解には一定の説得力がある。
2.リスクを過小評価させる仕組み
本格的なバブルが形成されるためには、投資の主体が、現実にある以上に「リスクはそれほど大きくない」と思い、リスクを過小評価するようになる仕掛けが必要だ。
かつての日本のバブルの場合、財テク運用には信託銀行や投資顧問会社による利回り保証(通称「握り」。かつても今も違法である)があったし、不動産投資には日本の地価は下がらないという「土地神話」があった。リーマンショックに至るアメリカのバブルにあっては「高度な証券化テクノロジーによって」リスク分散されているので不動産投資を証券化した商品のリスクは小さいとする金融テクノロジーへの過剰な信頼があった(格付け会社も自分たちの商売のために証券化商品への高格付けを乱発した)。また、それ以前の過程で、ネットバブル崩壊後の2000年代の前半期を通して、市場や経済の調子が悪くなれば、グリーンスパン議長(当時)が率いるFRBが金融緩和で何とかしてくれるだろうという通称「グリーンスパン・プット」が市場関係者の間で頼りにされていた。
今回はどうか。
先の鼎談の強気氏は、世界の政府や中央銀行の要人たちが「百戦錬磨の強者」たちなので、簡単にお金を引いて(=引き締めの金融政策に転じて)しまう可能性は小さいし、特にコロナ禍を背景にそれは無理だと論じていた。
「グリーンスパン・プット」に似たネーミングを考えるなら、「中銀(中央銀行)プット」とでも呼ぶべきリスクを小さく評価する仕組みが働いているように思われる。
筆者の思うに、確かに「中銀プット」は働いている。昨今話題になっている日銀のETF(上場投資信託)買い入れに関しても、市場関係者の多くは「株価が大きく下がったら、日銀がETFを買ってくれるだろう」と考えているように見える。
但し、かつての「グリーンスパン・プット」がいつまでも有効ではなかったように、「中央銀行プット」が失効することが将来起こる可能性はいくつかの場合にあり得る。
1つは、インフレ率が中央銀行の目標である「2%」を大きく上回るようになった場合だ。この場合には、中央銀行は金融緩和の理由の一部を失い、同時に将来のインフレに対する責任を意識せざるを得なくなる。
加えて、失業率が政府・中央銀行にとって十分に下がるくらい(米国だと4%割れくらいか)の景気の過熱が訪れた場合、中央銀行は金融の引き締めに動く可能性がある。
また、特に「財政再建」に熱心な官僚や国会議員の多い日本の場合、財政を引き締める可能性があり、この場合には金融環境が実質的に引き締めに向かうリスクがある。
強気派の論者が「中銀プット」に強い信頼を寄せているらしい現状は、定性的に見てバブルの性格を持っていると言える。



![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)










![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)


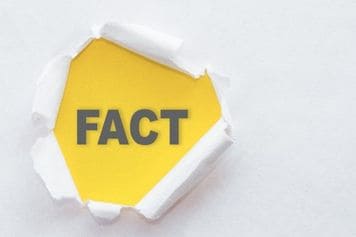












![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)
























![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




