学習による修正可能性とゴールの在処(ありか)
先の本の著者ジェイソン・ツヴァイクは、投資分野に詳しい著名な金融コラムニストなので、投資家である読者が自分の脳のおかげで間違いを犯さないための具体的な方法をさまざまに提案している。
彼の述べる方針の中で同意できるのは、「コントロールできるものを、コントロール」することに集中しようということだ。
たとえば、投資信託の選択にあたって、ファイナンシャル・アドバイザーは「経費」を8番目(!)に重要な考慮のポイントとしていると述べている(前掲書p43)。これは、一見投資の先進国である米国にして、ファイナンシャル・アドバイザーが所詮(しょせん)セールスの手先でしかないことを語る絶望的な事実だ。しかし、彼は、過去の運用成果や、リスク、ファンドの運用期間等の他の要素について、「これらの要素のどれも、最高のリターンを稼ぐファンドを見極めるうえでは役に立たない。投資信託の将来成果に対する唯一最も重要な要素は、相対的に固定的で小さな数字・手数料と経費であることが、何十もの綿密な調査で証明されてきた」と語り、投資家の行動を改善することを諦めてはいない。
彼は、本の「付録」にあるように、投資をルール化したり、投資の内容を投資家が認識したりするための「チェック・リスト」の活用を提案したりしているが、本で紹介する脳の研究自体は、投資家が学習やセルフ・チェックによって行動を修正することがどの程度可能なことなのかについて十分語っているようには思えない。
この点は、金融市場の規制や金融商品販売のルールの設定にあたって、重要な問題だ。
たとえば、投資信託の投資家の少なからぬ一部分が「分配金」のみに対する過剰な注視から脱し得ないのだとすれば、現在日本で流行(はや)っているような高金利通貨を使った通貨選択型ファンドのような投資家にとって得でない商品は、販売自体を規制すべきだろう。「ニューロ(脳神経)」の誤認傾向を利用するようなあざといマーケティングに対しては、上品な啓蒙(けいもう)だけでは不十分なのかもしれない。
また、学習の可能性の有無と共に、ニューロ・ファイナンスを弁(わきま)えた投資家が実際にどう行動するのがベストなのかについては、行動ファイナンス以前の伝統的なファイナンスによる検討が改めて必要だ。
お金の問題に関しては、目的と前提を決めると「最適」を求めることができるし、そこからの距離(自分がどれだけ「ダメ投資家」かの程度)を測ることができる。脳は自分が損をすること、負けることが嫌いな生き物のようなので、「適切な目的」を設定すれば、投資家が自分の行動を修正できる可能性はありそうだ。
いずれにせよ、投資家は、過信せず同時に甘やかさずに、自分の脳と上手に付き合っていかなければならない。
【追記】
2011年の原稿だ。当時、筆者は、行動ファイナンスと脳の関係に興味を持っていた。また、ファイナンス学会でも脳のMRI画像写真が載った論文が多数生まれていた。脳は人間の進化を反映して今日のような形・機能のものになったと考えられるが、金融的意思決定では、(1)恐怖反応、(2)儲けの喜びと刺激、(3)論理的計算、(4)公平・不公平の感覚、(5)恥の感覚、など複数の機能をつかさどる別々の箇所が関わり合っているようだ。文中にもあるように、常に正しい(損をしないという意味で合理的な)意思決定を下すことは人間にとって容易ではない。個人の側では意識的な努力が必要だし、社会の側でも脳の誤認を利用するような商品・ビジネスには規制が必要だろう。
その後も、脳の研究は進んでいる。金融との関係で脳を説明した新しい文献としては、今年になって翻訳が出版されたアンドリュー・W・ロー著『Adaptive Markets 適応的市場仮説』(望月衛訳、東洋経済新報社刊)を一読することをお勧めする。(2020年7月25日・山崎元)




![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)








![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)



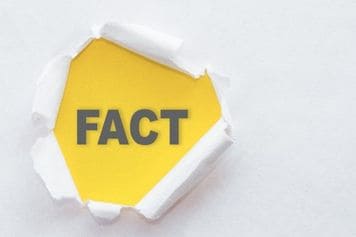














![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)






















![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




