機関投資家も個人投資家も
今回は、我が国にあって、機関投資家と個人投資家の双方で繰り返されてきた、「ダメな運用決定プロセス」について、何がダメなのかをご説明したい。
最も典型的に問題が現れたのは、1990年代後半から2000年代初頭にかけての企業年金の運用であったように思うが、個人投資家に対する投資アドバイザーのアドバイスにあっても、あるいは公的年金のような影響の大きな主体にあっても、共通にしばしば現れる誤った考え方を紹介する。
それは、一言で言うと「目標とする運用利回りから直接ポートフォリオを決定する」という運用計画策定の考え方だ。
例えば、1990年代の企業年金(主に厚生年金基金)は、「5.5%」という予定利率の下に掛け金と給付の関係が設定されていた。運用利回りがこの5.5%を下回ると、年金の積立金に不足が生じて、将来、母体企業がその不足を埋める必要が生じるという状況だった。
こうした状況下、多くの企業年金が、「名目上5.5%の利回りが得られるのではないか」と考えられる条件の下に運用計画(アセット・アロケーション等)を策定した。この時に、リスクは、「長期的には何とかなるだろう」という思い込みによって、具体的に検討されることがまれだった。
「長期投資なら、たぶん(ほぼ絶対的に…)損はしないだろう」という思い込みは、現在の個人投資家の間にも少なくないが、運用というゲームの仕組みはそこまで甘くはできていない。
資本市場の参加者が「運用では絶対に損をしない」と思うようになると、株式のようなリスク資産の価格が高くなりすぎて、リスクを補償する超過リターン(「リスク・プレミアム」と呼ばれる)が生じなくなるのが、このゲームの仕組みなのだ。
1990年代当時の企業年金は、「御基金は成熟度が低いので(=加入者が若いので)、長期の運用が可能で、リスクを取っても大丈夫です」という運用会社(信託銀行、生命保険会社、投資顧問会社)の営業マンの言葉を信じて、リスクを取った年金基金が多かった。
その結果、バブル崩壊に伴う資産価格下落と不良債権問題、そしてデフレによる金利低下の影響を真正面から受け止める形になり、多くの企業年金が苦境に陥った。
その後、国の年金の代行運用部分を返上して企業年金を縮小したり、年金基金を解散して確定拠出年金に移行したりする企業が相次いだのだが、こうした対策を取るとしても、母体企業がどれだけ損失を負担できる財務的体力を持っているか否かで、対応のための痛みの度合いが異なったり、取ることができる選択肢に差が生じたりしたのであった。
いかにも不運な運用環境ではあったのだが、通常のリスクの推定に当たって、この程度の損失状況は十分想定できるはずのものだった。いわば「リスクに対して目をつぶって」、目標リターンだけから運用計画を作ったことが、失敗の根本原因だった。
運用においても、人生においても、「想定できるワースト・ケース」が起こった時に十分対応できる余裕と、その場合にどうするのかという「プランB」(標準シナリオ「プランA」が実現しなかった場合の行動計画)を持つことが重要だ。



![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)










![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)


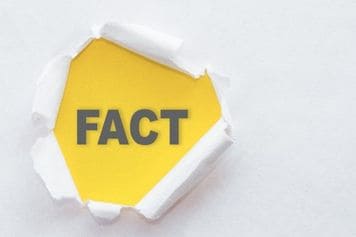












![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)























![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




