大手運用会社の手数料水準
筆者がネット証券に勤めているからそう思うのかも知れないが、ネット証券の株式の委託売買手数料がしばしば話題になるほどには、運用会社の運用手数料は話題になっていないような気がする。
しかし、運用会社の経営にとっても、投資家の運用パフォーマンスにとっても、実質的な運用手数料が幾らなのかという問題は決定的に重要だ。
さて、たとえば、レストランで食事をするとして、1人当たりの支払いが、1万円だったとしよう。原価の内訳はどのようなものだろうか。もちろん、個々の業態・店舗によって差はあるが、食材の原価が3千円、家賃が3千円、人件費が3千円で、利益が1千円というくらいであれば、まあまあ普通並み以上に立派な経営だろう。
運用会社の場合、どのような経営構造になっているのだろうか。金融関係の業界誌である『週刊金融財政事情』(4月27日−5月4日合併号)に、「国内資産運用会社のビジネス特性を読み解く」(p14〜p19、野村総合研究所金融ITイノベーション研究部 浦壁厚郎上級研究員)と題する、国内系の大手運用会社15社の経営を分析した興味深い記事があった。
数字は2014年3月期のものだが、大手15社の公募投資信託による委託者報酬は合計で4,742億円あった(記事中の表から山崎が計算。もともと表の数字は億円単位なので、数億円単位で集計誤差がありうる。以下同じ)。投資顧問料の合計は701億円なので、「名誉は年金運用で、お金は投資信託で」という運用会社の基本的な収益構造は、かつてと変わっていない。
但し、公募の投信の報酬はいったん運用会社に入金するがその後「代行手数料」という名目で投資信託の販売会社にキックバック的に支払われる。この手数料を集計してみると、2,463億円もあった。委託者報酬の50%を上回る。差し引きして、運用会社に残ったのは2,279億円であった。
これでも、やはり投資信託は投資顧問よりも儲かっているが、投資信託ビジネスにあって、相変わらず販売会社側の交渉力が強い事が分かる。もっとも、日本の大手運用各社の主な販売会社は資本関係的に親会社でもあり、立場的には「交渉力」以前の従属的な力関係である事が多い。
さて、国力を比較する時に1人当たりGDPを参照するように、1人当たりの数字で運用会社を見てみよう。
役職員1人当たりの人件費は、上が16.6百万円から下が7.5百万円の間に分布しているが、平均を計算すると11.3百万円だった。超高給というほどではないが、まずまず報酬水準の高い業界だ。
彼らは、中央値で見て1人当たり161億円の資産を運用しており、15社の運用報酬率は年率27.4bps(ベーシスポイント100bps=1%。中央値)だ。
ちなみに、先の記事で浦壁氏は、営業利益に人件費、減価償却費、不動産賃貸料、租税公課を足した「付加価値」の中央値を1人当たりで、30.3百万円と計算されている。これは、レストランでいうと、売上から概ね食材原価を除いた金額くらいに相当するが、どうやら外食産業の方が付加価値に対する人件費率は高い(運用会社の社員は不満かも知れない)。
運用会社各社の平均運用報酬率は最も高い会社で72.1bps、最も低い会社は17.5bpsであり、中央値は27.4bpsだ。運用資産に占める公募の投信の比率が高い会社は平均運用報酬率が高く、年金運用や親会社の資産運用の比率が高い会社の平均運用報酬率は低い。
運用の仕事が年金運用の方が簡単だという事はないし(顧客とのコミュニケーションがある分年金運用の方がむしろ面倒かもしれない)、投資信託の運用のパフォーマンスがより優れているなどということもない。商品に対する価格で競争的に形成されていることを考えると、この報酬率のバラツキは異様だ。
これらは、個人投資家が投資を考える上で直接的に考慮する事が必要な数字ではないが、わが国の運用会社が「こんな感じで経営されているのか」というイメージを掴んでおく事は無駄ではあるまい。
妥当な運用報酬の決まり方
筆者は、2000年から数年間、ある国立大学の社会人向け大学院で「金融資産運用論」と題する講義を行っていたことがあるが、この間、最も面白いと思った質問は「運用の手数料はどのような要因で決まるのですか?」というものだった(それ以外の質問は率直にいって「不作」であった)。
現実の運用ビジネスにあっては、「需給(競争)関係で決まる」というのが大まかな答えだ。「運用」も商品であるから、その価格が需給関係によって決まるのは当然だ。
これは、需要家側が大手で強い交渉力を持ち、複数の運用会社を競わせて運用委託先を決める年金運用のビジネスで運用手数料が安い事に如実に表れている。
他方、投資信託の運用手数料が高いのは、前述のように運用手数料の半分程度を受け取る販売会社が高い手数料率を望むからという理由が第一だろう。
加えて、大口顧客の前で複数の販売会社が競うというよりは、販売会社毎に顧客を囲い込み、顧客の関心を手数料から逸らすような形で投信の販売が行われていることがあるだろう。
もちろん、根本的な原因として、運用手数料の差を軽視する顧客側の運用リテラシーの不足(あるいは不在)がこの状況を可能にしていることを忘れてはならない。
さて、運用会社の側から見て、運用手数料の「下限」が、彼らにとっての「コスト」から決まることは明らかだ。これは、概ね、インデックスファンドに設定している手数料の少し下くらいだろう。
一方、投資家の側から見ると、仮に運用会社のアクティブ運用に価値があると判断した場合、アクティブ運用に支払っていい追加の手数料の上限は、計算の詳細は省略するが(ご興味のある方は本連載の「運用商品の選択と手数料の関係」2015年3月20日をご参照下さい)、期待されるアクティブリターンの2分の1までである。
運用手数料の、現実的な下限は運用会社にとってのコストから、理論上の上限は投資家から見たアクティブ運用の期待リターン(の半分)から決まると考えられ、現実的な運用手数料はその中間のどこかに決まるはずだ。
ただし、現実の投資信託を見ると、販売会社が顧客を誘導できているのか、あるいは顧客の側で、運用パフォーマンスを度外視して販売会社のサービスに費用を払っているのか、どう考えても合理的な「上限」を上回っているように見えるケースがしばしばある。
このような水準の手数料支払いには、「運用の中身ではなくて、セールスマンの接客に対する支払いなのだ」といった別の説明が必要なのかも知れない。そう考えるなら、確かに、投資家としては著しく非合理的でも、投信の顧客が、それを理解した上で何らかのサービスや精神的満足の対価として高い手数料を払うことにある種の合理性があるといえる。
しかし、銀座の倶楽部でお酒を飲む客が代金について「これは酒の代金というよりは、接客と家賃に対する支払いだ」と納得して支払いを済ませるような理解を、金融機関の店頭で投資信託を買っている投資家が出来ているようには思えない。彼らは、次に述べるような「市場リターン」と「手数料」を区別して評価する思考習慣を持たず、「儲かるのではないか」とただぼんやりと期待しているように見える。
商品選択と手数料
顧客にとっての運用商品のリターンは、「①市場のリターン+②運用スキルによるリターン−③手数料」で構成される。
この中で②の運用スキルを事前に有効に評価することは、顧客である個人投資家にとっても、実は運用のアドバイザーにとっても不可能だ。
だとすると、①市場リターンが同じになる同一カテゴリー(同じアセットクラス)の商品の場合、③手数料だけが、相対的な運用リターンに影響する要因となる。
つまり、手数料の安い商品がベストであり、それ以外の商品には出る幕がないという実も蓋もない結論が出る。これは、仮に国内株式に投資するファンドが100本あれば、手数料が最割安なファンドだけが検討に値するファンドで、残りの99本ははじめから考える必要がないということを意味する。99本のファンドマネジャーと運用会社には申し訳ないが、論理的には全く正しい。
そこまで徹底的に手数料だけにこだわるのもどうかと一方では思うが、運用商品を評価する時に、市場のリターンの見通し(例えば、株価が上がるか、為替レートはどうなるか等)と手数料とを混同せずに考えることが大事であり、手数料を「先に」評価することが重要だ、ということは、単純な足し算・引き算で分かる事なので、運用に関する消費者教育として、義務教育段階で教えておくべき知識だろう。
筆者は、いわゆる「投資教育」が重要である事に賛成するが、「投資」以前に、運用一般に関する「消費者教育」を国民に広く伝えることが大事だと近年強く感じるようになった。手数料の重視は、その中で伝える必要がある重要な項目の中の一つだ。



![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)










![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)




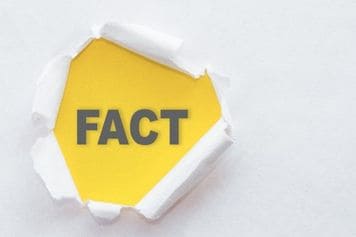












![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)
























![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




