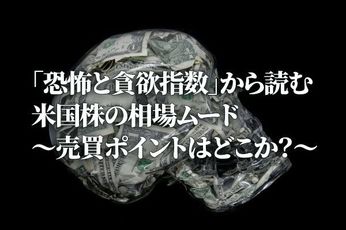<編集注>国税庁は10月7日、本記事で取り上げている『所得税基本通達』の改正案を修正すると発表しました。 新たな通達では、帳簿書類の記帳と保存があれば所得区分を『事業所得』に、ない場合は『雑所得』とします。原則として「本業」か「副業」かは区別しません。
本記事は10月6日時点の内容であり、最新情報と一部異なります。詳細は国税庁発表をご確認ください。
最新記事はこちら:「副業300万円問題」が決着!当初案からどのように変わったか?
「副業300万円問題」ってなに?
突然ですが、皆さんは副業をしていますか? 近年は副業に対する企業の姿勢がかなり柔軟になり、副業を積極的に推奨する動きもあります。
また、会社勤めをして起業を目指す方であれば、いきなり会社を辞めて独立開業するのはやはりリスクが高いので、会社勤めをしながらまずは副業レベルでスタートし、うまくいきそうだ、という手応えを感じられたら起業する、というケースも多いと思います。
そんな「副業ブーム」に水を差す事態が起きています。国税庁が今年8月に発表した文章で、副業の所得などについて定めた「所得税基本通達」の改正が行われる可能性が高いことが明らかになりました。これが今、ちまたで密かな話題になっている「副業300万円問題」です。
国税庁、「所得税基本通達」の一部改正案を発表
国税庁は2022年8月1日に「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」という文書を発表しました。
この内容を簡単にまとめると、「2022年分以後の所得税において、副業収入が300万円以下の場合は、事業所得ではなく雑所得として取り扱う」というものです。改正後は、2022年1月以降の所得税に関してさかのぼって適用されます。
この改正案に意見などがある場合は、8月31日までに電子政府の総合窓口(e-Gov)、FAX、郵便などにより国税庁へ送ることができます。
ただ、これまでの同様のケースから考えると、おそらく今回発表された改正案のとおりの内容で決定するのではないかと思います。
なお、通達というのは法律ではなく、法律だけでは実務的な扱いなどが不明なものについて、その取り扱いについて定めた行政機関の内部規定です。
法律ではないので、私たちはこの通達に従わなければいけないということにはならないはずなのですが、事実上通達は法律と同様の扱いとなっています。実際、通達と異なる処理を行い、税務署から否認され、裁判でも納税者側が負けるケースは多々生じています。
ですからこの通達の改正が実際に行われた場合、私たちは事実上これに従うことになるのです。
改正による影響は?
今回の通達改正により、どのような影響があるのでしょうか? 主なものは次の通りです。
(1)事業所得ではなくなるので、青色申告特別控除が使えなくなる
副業を事業所得として申告した場合、青色申告特別控除として、所得から10万円、55万円、もしくは65万円を差し引くことができます。しかし雑所得だとこの取り扱いがないので、その分所得が増えてしまいます。
(2)所得が赤字となった場合、他の所得と損益通算して所得総額を減らすことができない
例えば給与所得と事業所得があり、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺(損益通算)をして所得総額を減らすことができます。
しかし雑所得だと赤字となっても他の所得との損益通算ができないため、その分所得が増えてしまいます。
(3)損失の3年間繰り越し控除が使えない
青色申告をしている場合で、事業所得が赤字で、他の所得と損益通算しても赤字が残るとき、それを3年間繰り越して、翌年以降の所得と損益通算することができますが、雑所得だとこの制度が使えません。
(4)少額減価償却資産の特例が適用されない
青色申告をしている個人事業者は、1個30万円未満の減価償却資産を一度に損金処理(費用処理)することができますが、雑所得だとこの制度が使えません。
なぜこのような改正が行われることになったのか?
では、なぜこのような改正が行われることになったのでしょうか?
実は以前から、「副業で赤字をつくって節税をする」というスキームが存在していて、これを推奨していたコンサルタントもいたようです。
しかしこれは税法の隙をついたかなりグレーな手法であり、税理士である筆者もこれはいかがなものか、と思うケースが良く見受けられました。
この手法がかなり世の中に広まった結果、黙認していた国税庁もさすがに見逃すことができず、今回の改正に至ったわけです。
今回の件に限らず、税金の世界では、「税法の隙をついたスキームを思いつき節税をする」→「それがあまりに広がり過ぎると国税庁が法律改正などで封じ込める」ということがよく起こっています。
このとき、グレーな節税をする意図を全く持っていない、真面目な納税者もとばっちりを食らってしまうことがあり、今回もそのケースに該当します。
次回は、数値を用いて具体的に改正の影響をみていくとともに、対策について考えてみたいと思います。





















































![[動画で解説]「今週のドル/円は4円の円安。来週のドル/円は160円か? 」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/f/498m/img_1f3949c08c7e53f8c517668b0bca4e6a45975.jpg)
![[動画で解説]アメリカ大統領選挙から1週間「トランプトレード」はどう変化していく?~時間軸で考えてみる今後の相場展開~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/4/498m/img_34971e338ed0449f7eb54625c17b1f8071951.jpg)
![[動画で解説]【米国株】トランプ相場 ラリーとクラッシュの間](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/6/498m/img_c602ac20bd2fb9e7dd213b0a4b8be5c461311.jpg)
![[動画で解説]【2024年10月】今、上昇している市場はどこ?投資信託ランキング「注目のインド株ファンド!これから投資する人におすすめの3本」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/f/498m/img_2f095920da9b3a6e3157b834cb0947be39986.jpg)