副社長に165億円!
昨年9月にソフトバンクの代表取締役副社長に就任したニケシュ・アローラ氏が、165億円の報酬を得たことが話題になっている。
165億円のうち、約140億円がグーグル社からニケシュ氏が移籍する事に伴う移籍金だという。同氏のグーグル社に於ける報酬は約60億円だったということなので、これを失うことに対する一時金が支払われることは、金融マンなどの転職にあっても不思議なことではない。但し、普通の転職では、前職での年収の1年分程度の金額になることが多いので、140億円という金額から、ソフトバンクの孫正義社長がいかに熱心にニケシュ氏をスカウトしたかが窺える。
だが、140億円差し引いたとしても、残りの20億円近い金額は、同氏への約半年間の報酬ということになる。近年よく話題になる日産自動車のカルロス・ゴーン社長の約10億円(2015年3月期は10億3500万円)の報酬と比較しても破格の高額報酬だ。
同氏の報酬は、ソフトバンクの株主と取締役会は納得しているのだろうから、第三者が問題とするには及ばないが、日本企業における経営者への報酬額水準の引き上げという点で大変印象的な事例だ。
2015年3月期の企業役員への主な高額報酬の事例としては、日産のゴーン氏の他に、同じくソフトバンクのロナルド・フィッシャー氏への17億9千万円、セガサミー・ホールディングス里見治氏の4億7千万円、エイベックス・グループ松浦勝人氏4億4千万円、ソニー平井一夫氏3億1千万円、などがある(数字は何れも百万円台切り捨て)。
まだ今回のアローラ氏の報酬額には遠く及ばないとしても、日本企業の経営者の報酬は近年上昇傾向にある。
社長の報酬はまだ上がる
経営者、端的にいって社長の報酬を決める要素は複数ある。社員の給与とのバランス、人材としての需給関係、企業の業績、他社の社長の報酬とのバランスなどだ。
従来まで、日本企業の社長の給与は、社員の収入とのバランスを強く意識したものだった。サラリーマン社長は、もともとはサラリーマンだったのであり、社長になったからといって、急に優秀になるわけではない(当人の若い頃と比較すると能力的にはむしろ劣化していることが多かろう)。給与が能力や能力による貢献に対して支払われるものなら、従業員からあまりにかけ離れた水準の報酬を社長が取るのはいかがなものか、という感覚が働いたのだ。従業員への報酬を決める理屈の延長で社長の報酬が決まっていた。日本の社長は、まさに「社員の長」だったのである。
一方、特に経営者をスカウトする場合に、当人を巡る需給関係も大きな影響力を持つ。例えば、グーグル社の国際展開で功績のあった先のアローラ氏であれば、現実にグーグル社が数十億円レベルの報酬を支払っていたし、多額の報酬を支払ってでも同氏を迎え入れたいと考える企業が他にもあるだろう。仮に、将来、業績が悪化する場合があったとしても、同氏を引き留めるために、ソフトバンクはそれなりに競争的なレベルの報酬を支払い続ける必要があるかも知れない。
経営者として会社を渡り歩くことが多い外国人の社長が、日本人の経営者よりも多額の報酬を取る場合があるのは、当人を巡る人材市場の需給関係が影響している面があろう。
もちろん、社長の報酬は業績の良し悪しにも左右される。会社が掲げた収益目標が達成されたかどうかも問題だし、前年との比較なども報酬に影響する要因となろう。近年話題になることの多い、ROE(自己資本利益率)が、今後有力な参照指標とされることもあろう。
そして、近年、ストック・オプションや自社株による報酬の利用が拡大していることもあり、「株価」がより直接的な報酬決定要因となる面がある。「業績」そのものは、むしろ株価を上げるために操作したい間接的な対象の位置づけだ。
仮にゴーン氏が突然社長を辞任したら日産の株価はどうなるだろうか。5%くらい下落することがあっても全くおかしくないと筆者は思うが、6兆円に迫る日産の株式時価総額から計算すると、3千億円近い富を日産の株主は失うことになる。そう考えると、ゴーン氏への10億円の報酬は全く高くないのではないか。時価総額と比較すると、経営者の報酬は全く高くないと考えることもできる。もっとも、社名は挙げないが、経営者が辞める方が、株価が上がりそうなケースもあるので、経営者の高額報酬が時価総額によって常に正当化される訳ではない。
ともあれ、社員の給料とのバランス比較で考えるか、株式時価総額の増減との比較で考えるかで、妥当に見える社長の報酬水準は大きく変化する。
他社の社長の報酬とのバランスも影響しよう。これまで、日本の経営者がアローラ氏、ゴーン氏並みの報酬を取ってこなかった理由として、「我が社だけが(私だけが)突出して高いのはまずい」という配慮が社長自身の側に働いていた事情がある。
だが、これは、同時に「突出していなければいい」ということでもある。他社の社長の報酬が高くなれば、社長は自分の給料を上げやすくなるのだ。過去10年くらいに亘って、従業員の給与水準が低下する場合にあっても、日本企業の社長の給料が上昇傾向をたどってきたことの背景には、他社とのバランスを意識した面があったのではないか。場合によっては、「他社と比較して我が社の社格を考えるなら、我が社の社長の報酬はせめて○億円くらい無ければ、格好が付かない」といった論理に期待することも出来る。日本の社長たちもお金が嫌いなわけではない。そして、横比較を大変気にする人達だ。彼らは、自社の人件費を抑制しつつも、周りを見ながらじわじわと報酬水準を上げてきた。
暗黙の政策としての「経営者報酬アップ」
日本の社長の報酬は今後も上がり続けるだろう。筆者は、社長の報酬水準を引き上げることが、実は暗黙の国策になっていると考えている。そして、この国策は株価に大きく関係するかも知れない。
日本版スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードの相次ぐ制定、会社・グループから独立した社外取締役の任命を促す動き、ROE(自己資本利益率)を重視する考えの普及など、近年、一連の日本企業のコーポレートガバナンスを巡る動きの発するメッセージを一言に集約すると「企業はもっと経営の効率を上げよ」だ。
そして、このメッセージの実質的に意味するところは、企業は内部に溜め込んだ資産を、自社株買いないし配当の形で株主に還元せよということである。ビジネスそのものを上手くやって儲けたいとは、誰しも思っていて、達成出来たり、出来なかったりする。しかし、所謂「株主還元」なら、会社にお金さえあれば、特別優れた経営者でなくとも可能だ。
この「経営効率改善」の担い手は企業の経営者だが、経営効率の改善を達成することによって経営者の報酬がアップする仕組みを彼らの目の前にぶら下げて、これを促す環境整備が一連の企業統治改革を総合的に見た時に見えて来る意図だ。
機関投資家株主に要求の声を上げさせ、経営者は自社株買いや増配でROEの向上を目指す。そして、社外取締役が一連の動きを監視するような雰囲気の下で、実は、経営者の報酬増加に正当性を演出することに一役買う。
先般行われたある3月期決算企業の株主総会で、業績が悪いにもかかわらず高額の報酬を取ることについて株主に問われた某上場企業の経営者は、自分の報酬は自分が決めたのではなく、報酬委員会(社外取締役によって構成される)の勧告に従って決まったと回答した。社外取締役は、経営者の高額報酬を正当化して、世間の批判に対して防波堤の役割を果たすのである。
もともと、社外取締役が当該企業の業務や業界に精通していることは稀だ。今後、社外取締役自体の人数が急増すると益々その傾向は強化されよう。また、高額ではないとはいえ、彼らとて報酬とそこそこに心地よい地位を手にする訳で、出来れば経営者とは仲良くやりたい。「ROEを上げて、株主還元を行っていれば、経営者の報酬は高くてもいい」という世間受けする一般論に沿いながら、経営内容と経営者の報酬に「お墨付き」を与えるのが社外取締役の実質的な役割になるだろう。
そして、ROEを上げ、同時により直接的に株価を上げるのに最も簡単な手段が自社株買いだ。
ここで需給面から株価を上げる政策を考えてみよう。既に、公的年金に株式を買わせ、日銀に株式を買わせている。更に、郵貯に株式を買わせ、NISAやDC(確定拠出年金)の拡充を梃子に個人に株を買わせようとしている。その先は何があるかと考えると、株式の最大の買い手として動員を期待できるのは、実は企業自身であることに気づく。
だが、企業が内部留保を吐き出すことは、経営者にとってはリスク(例えば倒産リスク)の拡大を意味する。経営者に何らかのインセンティブを与えないとこれは実現しないだろう。
スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード、ROE目標、それに社外取締役は「飴と鞭」の「鞭」の役割も果たすが、他方で、経営者の高額報酬という「飴」を受け入れやすくするための舞台装置でもあるのだ。
こうしたコーポレートガバナンス改革は、言わば経営者を株主が買収することを通じて、株価の上昇を指向する政策であり、その副次的な効果として、日本企業の経営者の報酬水準は切り上がっていくだろう。日本の社長をアメリカのCEOに近づけながら、アメリカのように株価を上げるのだ、と考えると分かりやすいかも知れない。
日本企業の経営者達が、横並び競争的にこの流れに乗ることになると、行き着く先は「株主還元バブル」とでも呼ぶべき、意外な株価上昇となる可能性もある。
筆者は、誰かがこれらのシナリオを書いているといった「陰謀論」的推測には加担しない。株価を上げたい政府、株価上昇に賛成な諸々の株主・投資家、報酬を増やしたい経営者、こうした動きで儲かる金融機関、といった多くの関係者の利害の方向性と一致することで、個々の政策がいわば進化論的に生まれて生き残った結果だろうと推測する。
一般論として、関係する主体にとって「好都合」な話は実現しやすいが、それがどこまでも拡大出来るものではない場合に、「ほどほど」で止めて安定させることは難しい。「バブル」が起こりやすい理由である。
「いつ」と「どれくらい」は未だ分からない
投資家にとっての問題は、こうした動きがあるとして、それが何時、どのような規模で株価に影響するのかだ。
だが、残念ながら、それらについては、筆者にも分からない。
当面の金融緩和と需給対策に支えられた上昇相場をそのまま引き継ぐことが出来る可能性もある。しかし、世の中の意識や組織は急には変わらないし、今年後半に予想される米国の金融引き締めへの転換などのマクロ的要因の影響の方が大きく、いったん下げ相場に見舞われて、「株主還元バブル」の可能性が一端はすっかり遠景に遠のく可能性もある。
筆者は、今の時点では、どちらかというと金融政策の変化の影響を重視している。現在、自分に適すると思える金額で株式に投資している投資家に対しては、今後に株価上昇があれば、徐々に投資ポジションを落とすことを検討したらいいのではないかと思っているが、最終的に投資ポジションをゼロにするような投資行動が適切だとは思っていない。
株式投資はそもそも企業に資本を提供して利益を稼がせてこれを得る目的で行うものだから、長期的に株式を保有する必要があることに加えて、株主が経営者を買収することによる「株主還元バブル」のシナリオに、少なからぬ合理性があることが補足的理由である。
投資家は、個々のリスク負担能力とのバランスを測りつつ、しぶとく株式を持ち続けて、長期的な材料として「株主還元バブル」を楽しみにするといい。この流れが実現すると、社長並みとは行かないまでも、庶民も少々豊かになることができよう。



![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)










![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)




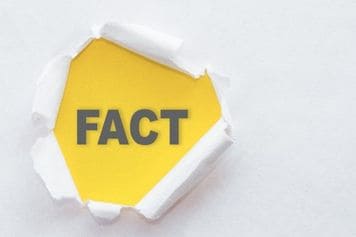












![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)
























![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




