「長期経済見通し」をどう扱うか
運用の一般論として、マクロの経済見通しで投資戦略を考えることは「殆ど有効でない」。それは、そもそも(1)運用に有効なレベルで正確に経済を見通すことが難しいからであり、次に(2)仮に見通しが当たるとしてもマクロの諸数字と資産のリターンとの関係が不安定だからであり、加えて(3)他の市場参加者もマクロ経済を予測するからだ。3番目の点に関しては、他人の予測を把握することの難しさと、他人との意味のある「差」を予測力において持つ事の難しさに分けて考えても、いいだろう。
まして、長期の経済予測などというものを基にして、資産運用を作ることは、とても「まとも」とは言い難い暴挙だ。
長期予報になると天気予報がまるで当たらなくなるように、経済予測も長期の予想が極めて難しい。そして、ポートフォリオの想定期間は主としてポートフォリオの調整コストと調整スピードから決まるので、「長期(予想)の平均」を当面のポートフォリオの想定期間にしてはいけないことの二つが理由である。
これらは運用のプロなら平易に分かる「常識」なのだが、困ったことに、その対極にある「非常識」をやろうとしているのが、昨今話題のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用する公的年金積立金(厚生年金と国民年金・基礎年金)の運用計画である。
しかし、本稿の目的は、公的年金運用の批判ではない。「一つの参考として」やや長期の経済見通しを眺めて、将来の経済と投資環境を想定した時に、現在及び近い将来に(遠い将来のことは、その時が近づいてから考えればよい)、個人がどのような運用をしたらいいのかを考えてみたい。
前記のような事情であるから、長期予想に基づく「運用方法の提言」というよりも、将来に思いを馳せるエッセイのようなものとして読んで頂けると幸いだ。
政府が描く経済の将来像
次に掲げる2つの表は、内閣府が作成した「中長期の経済財政に関する試算」(平成26年7月25日 経済財政諮問会議提出)から、数字を拾ってみたものだ。
<表1>経済再生が上手く行くケース
| (年度) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 名目GDP成長率 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 消費者物価 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 名目長期金利 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
※ データは全て「年率%」
<表2>より緩やかな成長経路となる参考ケース
| (年度) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 名目GDP成長率 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 消費者物価 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 名目長期金利 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
※ データは全て「年率%」
二つの表を、大きさを変えて掲載しようかとも思ったが(表1を小さく、表2を大きくだ)、皮肉が露骨なので止めておく。どちらかというと、表2の参考ケースを中心に、先ずは、将来の経済像をイメージするために数字を眺めてみて欲しい。
政府が見ている経済像を理解するために、話が少し込み入るが両者の前提のちがいを説明しよう。
経済再生ケースでは、通称「TFP」と呼ばれる全要素生産性(労働と資本の投入に対する生産性)の1年当たりの伸び率が0.6%で(2013年度予想が0.6%程度)、2015年度まで続き、その後に2020年代初頭にかけて1.8%程度(バブル期並みの水準だ)まで上昇すると仮定している。TFP伸び率は、大雑把には経済の「効率」の改善度合いだと考えていい。
これに対して、参考ケースは、2015年度までTFP伸び率が0.6%程度で推移し、2020年代初頭にかけて「過去の平均程度」の1.0%にまで上昇すると見ている。
もう一つの大きな違いは、経済再生ケースが女性・高齢者を中心に性別年齢階層別労働参加率が上昇すると考える一方で、参考ケースでは性別年齢階層別労働参加率が足許の水準で横ばいだと考えることだ。
両者の関係を理解するには、厚労省の年金財政検証のシナリオと対比すると分かり易い。図1は、厚労省が「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(いわゆる「財政検証」)で作成した図だ。
<図1>公的年金の経済前提イメージ
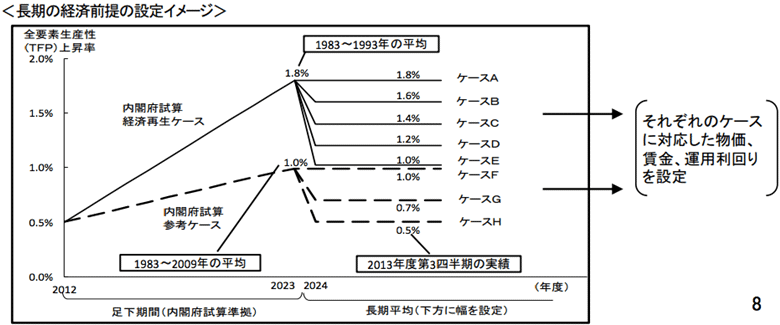
(出典:「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」厚生労働省 平成26年6月3日)
それでは、厚労省はどうしたか。内閣府の経済再生が失敗することを前提には出来ないので、2023年度までは経済再生ケースを採用し、その後は、TFP伸び率が1.0%とある程度「現実的な水準」に落ち着く、ケースEをメインシナリオとして採用した。
しかし、2013年度第3四半期までの足許のTFP伸び率は0.5%だ。果たして、これを改善させるような、技術進歩なり、社会的変化なりがあるのだろうか。
公益財団法人日本生産性本部・生産性総合研究センターが作成した「日本の生産性」(2012年12月)というレポートで、TFP伸び率(年率)の5年単位の時期毎の変化を見てみた。
先ず、1991年〜1995年の日本のTFP伸び率は年率0.5%で、この時期の米国は0.8%だ。1996年〜2000年は、日本が0.6%、米国は1.4%だ。2001年〜2005年は日本が1.2%、米国が1.8%。2006年〜2010年は日本が0.7%、米国が0.9%だ。ちなみに、これら4期間の全てで、韓国は年率3%台の高いTFP伸び率を記録した。端的にいって、TFP伸び率は成熟した先進国よりも、キャッチアップ期にある国の方が高い。加えて、イノベーションが活発かどうかという点が問題だ。
米国のTFP伸び率も合わせて見ると、2000年代前半に高い伸び率を記録しているのは、たとえばネット関連の技術進歩が経済の生産性の向上に与えた影響ではないかと考えることが出来よう。
これに匹敵するような生産性の向上が今後起こらないとは断言出来ないが、1%以上のTFP伸び率を「予定」するのは、資金運用のような重要な物事を計画するのは、些か楽観的にすぎると思う。
個人の資産運用
ちなみに、公的年金の財政検証上の運用利回りは、経済見通しで予想する長期金利に「分散投資効果」として0.4%を乗せたものだ。運用目標の説明は、賃金上昇率プラス何%といった形で行われるのが恒例だが、内容の決まり方はこうした大雑把で頼りない予想に基づくものだ。加えて、内外の株式や外国債券を運用資産に加えることで、「債券100%並のリスクの中で、長期金利+0.4%の利回りを取ることが出来る」というのが、従来の公的年金の運用計画の説明であり、そこで得られる利回りが「運用目標」として、厚労大臣からGPIFに与えられる。
いきなり目標リターンがあって、これに合わせてリスクを取るのは、かつて運用に無知なFP(ファイナンシャル・プランナー)などがよくやったような、不適切な運用計画の作り方だ。
再び公的年金運用の批判に戻ってしまったが、次に、これを離れて、先の<表2>を眺めつつ、個人の将来の資産運用を考えてみよう。
たとえば、目線を5年後に置いて、2018年の経済予想を見てみよう。実質GDP成長率は1.2%、消費者物価上昇率も1.2%だが、長期金利は2.4%に上昇している。
消費者物価上昇率は、2014年度、2015年度と消費税率の引き上げの影響を受けて大きく上昇し、2016年度に日銀のインフレ目標値である2.0%を記録した後、2017年度以降1.2%に下がる。このシナリオで、2014年度を含めて、2018年度まで5年間の消費者物価の上昇を計算してみると通算約10.5%になる。
経済全体にとってデフレ脱却はいいことだが、消費者としては、実質的な購買力を保つのに努力が必要だ。お金の価値が5年で1割以上落ちるとなると、生活にもそれなりに影響してこよう。筆者の立場としては、「運用で頑張りましょう」と言いたいところでもあるが、生活の上では、たぶん働いてより多く稼ぐことを考える方が現実的だろう。
さて、この将来像にあって、資産運用上何といっても大きな変化は、長期金利が2%台(2.4%)まで上昇していることだ。1%少々の実質成長率ではあっても、デフレ脱却の為のいわば特別な金融緩和政策が終わった段階では、長期金利が上がる。
内閣府の予想の参考ケースでは、長期金利が2016年度に2.0%に乗ることになっており、経済再生ケースでもこの年度に2%台に乗る(2.3%)。
銀行や保険会社などの機関投資家は、この時期をどう乗り切るかで、経営状態に相当の差がつくだろう。個人としては、この時期まで固定金利の長期債を持たない方がいいことに加えて、自分が取引する金融機関の経営状態にも気をつけておきたい。
歴史的に見ても、景気回復期の金利上昇で金融機関の経営が破綻するケースはよくあることだ。銀行預金に関しては、「1人、1行、1千万円まで」の預金保険の限度を意識しておくべきだ。
筆者がよく個人投資家に勧める資産運用の簡便法は「リスク資産として国内株式(ベンチマークはTOPIX)と外国株式(同MSCI-KOKUSAI)を、それぞれ50%ずつインデックス・ファンドで持ち、リスクを取りたくない資金は、個人向け国債(10年満期変動金利型)かMRF(マネー・リザーブ・ファンド)ないしは預金保険の限度内であれば銀行預金(主に普通預金)で持つ」といったスタイルのものだが(例えば、拙著「全面改定 超簡単お金の運用術」朝日新書、をご参照下さい)、政府の経済予想を前提とすると、2016年度くらいから、多少のアレンジが必要になるかも知れない。
もちろん、政府の経済見通しを頼るのではなく、内外の債券に分散投資するかどうかを、「その時の投資環境を見て」検討するのだ。ある程度以上の利回りがある場合、債券と株式の分散投資が機能するようになる可能性がある。
他方、現在のように長期金利がゼロに近づいた状態では、債券のプラス利回りが大きく出ることが期待しづらいし、普通預金のような金利が殆ど付かない金融商品を持つことの機会費用が小さい。
さて、この経済見通しでもう一つ気になるのは、将来の経済状況に見合う株価だ。2018年度の実質長期金利が1.2%で、利益の実質成長率がGDPと同じで1.2%だ、という世界が恒常的に続くと想定した場合、リスクプレミアムを6%得るには、益利回りが6%必要だ。この場合、PER(株価収益率)は16.7倍ということになる。日本経済の将来像を考慮に入れて考えるなら、株式市場全体の平均ではこのくらいのPERが上限の目処になるかも知れない。
それにしても、我が国の労働力人口の減少ペースは急激だ。内閣府の試算では、2013年度から2030年度にかけて、労働力参加に政府が期待するような変化がない場合、年率ほぼ0.9%ずつ減少する。内閣府の経済再生ケースでは、これを年率マイナス0.3%程度に減速することになっているが、実現はおそらくは難しかろう。
生産性も成長率も上がらない場合、名目長期金利が政府の予測よりも低いレベルにとどまるだろうが、それでも、たとえばTFP伸び率が現状並みの0.5%、労働力人口の減少が0.9%とすると、実質成長率はマイナス0.4%程度が「普通」となってしまう。こうした「縮む日本経済」に対する対応も、投資家としても、また生活する個人としても考えておくべきだろう。
但し、将来そのような低成長の経済が実現した状態で株式投資を考える場合、その時点で投資する株式のリターンが低いと考えると、間違いに嵌まってチャンスを逃す公算が大きい。将来の利益が、低成長であっても、高成長であっても、それが投資家の予想するところであり、株価に織り込まれていれば、株式投資のリターンはリスクに見合ったものになるはずだ。
もっとも、その時点までの利益水準が「予想以上に悪く変化した」という場合、その時点までの株式のリターンは期待に満たない可能性が大きいともいえる。
運用にあって、悲観と楽観のバランスは、人生同様、短期でも長期でも常に難しい。



![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)










![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)













![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)





















![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)
![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)
![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)
![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)




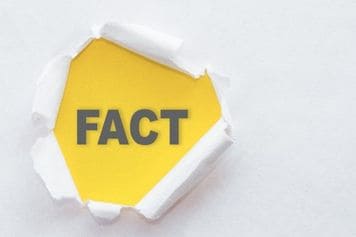












![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)
























![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)


![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)




