※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。
著者の加藤 嘉一が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。
「中国経済の鍵を握る7月「三中全会」で何が語られるのか?習近平氏の掲げる「改革」とは」
7月開催の「三中全会」、日時はいまだ発表されず
2024年の中国経済を巡る最大の注目ポイントの一つが「三中全会」だと私は考えてきました。三中全会というのは、5年に1度開かれる共産党大会の間に通常7回開かれる中央委員会全体会議の「3番目の会議」という意味です。1978年に開かれた第11期三中全会が、「建国の父」毛沢東が亡くなる1976年まで続いた「文化大革命」に別れを告げ、改革開放路線へとかじを切らせるきっかけをつくったように、歴史的に見て、重要な経済政策が発表されたり、国家としての進路や方向性にインパクトを与える決定がなされたりします。
これまで、本連載でも三中全会を巡る動向に焦点を当ててきました。
2023年最後のレポート「2024年の中国経済はどうなる?注目すべき8つのポイント」では、その4番目として「異例の遅れ、『三中全会』はいつ開催されるか?」を取り上げました。
また、約1カ月前のレポート「遅れていた『三中全会』の開催が決定。中国経済は迷走から脱却できるのか」では、中国経済に漂う不透明感の象徴と見なされていた三中全会開催の遅延にようやく一つのケリがついた、ここからの焦点はその中身、および同会議の開催が景気回復や構造改革にどうつながるのかだと指摘しました。
中国共産党指導部は、三中全会の開催を「7月」とだけ発表しています。具体的日時も、いつごろになるかも発表されていません。早ければ今から1カ月後には開催される可能性もありますが、これから約1カ月、いつどのタイミングで具体的日時が発表されるのか、その際、会議のアジェンダに関して何らかの提起があるのかどうか、注目していきたいと思います。
三中全会の「前哨戦」として開催されたある座談会
7月の三中全会を占う上で、その「前哨戦」として注目された政治イベントがあります。
5月23日、習近平(シー・ジンピン)総書記が山東省を地方視察した際、同省の省都(日本の県庁所在地に相当)済南市で、企業家や専門家を招いて座談会を行いました。中国共産党指導部は、国家として重要な決定や審議をする前に、(少なくとも建前として)市場や社会における各界の意見を聞き、参考にすべく、「座談会」を主催するのが慣例です。
例として、習近平第2次政権が発足した2017年秋以降では、2018年11月と2020年8月に座談会を開いています。2020年10月に開催された第19期五中全会前夜に行われた後者について言うと、「第14次五カ年計画」の綱要を作成するための意見聴取という色彩がにじみ出ていました。今回、5月下旬にこの座談会が開かれたことで、7月の三中全会を視野に入れた動向と解釈するのは自然な流れだといえます。
企業家、専門家の代表として、今回の座談会に招待され、プレゼンテーションをし、習近平氏と直接意見交換をした9人を整理してみました。
劉明勝:国家電力投資集団有限公司董事長 兼 党組織委員会書記
左丁:深セン市創新投資集団有限公司董事長 兼 党委員会書記
丁世忠:安踏体育用品集団有限公司董事局主席
徐冠巨:浙江伝化集団有限公司董事長
徐大全:ドイツボッシュ(チャイナ)投資有限公司総裁
馮国経:香港リー&フォングループ主席
周其仁:北京大学国家発展研究院教授
黄漢権:中国マクロ経済研究院院長
張斌:中国社会科学院世界経済政治研究所副所長
首都北京に本部を置く国有企業である中央企業1社、国有のベンチャーキャピタル企業1社、民間企業2社、外資企業1社、香港企業1社、学者3人という内訳です。参加した企業や人物にとっては、「習近平氏からお呼びがかかった」ということで名誉なことなのでしょうが、一方で、座談会に参加した面目から、中国共産党指導部として、足元どういった分野に着目しているのかの一端が見えてくるという意味で、検証する価値があります。
上記の企業の属性や学者の専門分野から、電力分野の成長と改革、ベンチャーキャピタルの実体経済や企業成長への寄与、スポーツと先端技術、民間企業の在り方と成長、香港経済と中国経済の関係と融合、経済成長と国民生活、地域格差の是正、経済政策におけるマクロコントロール、といった領域に、党指導部が関心を抱いており、政策や改革を通じて産業や業界の持続可能な発展を促そうとしている現状が透けて見えるのです。
キーワードは「改革」、問題は何をどう改革するか
座談会において、習近平氏は冒頭で次のように問題提起をしました。
「改革は発展の原動力である。改革をより一層全面的に深化させる」
座談会を受けて、国営の新華社通信は中国語で1,005字から成るプレスリリースを配信しましたが、その中で、「改革」の二文字に19回も言及しています。要するに、座談会のキーワードは「改革」であり、それはすなわち、来たる三中全会のアジェンダにもつながっていくのだと私は理解しています。
習氏は続けます。
「中国式現代化を緊密に推進し、目標だけでなく、問題に沿った政策を堅持していく。問題に立ち向かい、問題次第で政策を変えていく。中国式現代化の推進を妨げる思想観念、体制メカニズムの弊害を断固として除去していく。深い次元における体制的障害と構造的矛盾を取り除くことで、中国式現代化に強靭(きょうじん)な原動力を注入し、有力な制度的保障を提供する」
その上で、「人々がより良い生活を送れるようにすること」こそが、共産党が奮闘する目標だとうたった上で、雇用、収入、就学、医療、住居、幼児、高齢者、生命と財産の安全といった国民が関心を持ち、悩みを抱える分野に「改革の着眼点と突破口を見いだす」ことを掲げています。
座談会における習近平氏の発言からは、国民が現状に納得し、将来に希望を見いだす、言い換えれば(民主選挙を通じて選ばれたわけではない)中国共産党が正当性を持ち続けるためには、「改革」が不可欠であるという切迫感が伝わってきます。
「変えるべきところ、変えられるところをしっかり変えるべきだ。どこを変えるのかが分かったら、何としても変えるべきだ」
こういった発言からも、国民から愛想を尽かされないように、変えなければならない、変わらなければならないという危機感が伝わってきます。
中国と関わりを持つ我々外の人間から見ても、習近平氏自らが「改革」の旗を掲げている現状は歓迎できることです。問題は、習氏が言う「改革」とは何なのか、に他なりません。例として、中国当局は往々にして、「改革」という名の下で、規制を緩和ではなく強化したり、市場原理を重んずるのではなく、引き締めを強めたりします。14億の市場がこれまで以上に開放され、包容され、自由になる、それこそがあるべき「改革」だと我々は往々にして考えます。
一方、習近平氏率いる中国共産党が掲げる改革はその逆である可能性もあるのです。政治の経済に対する、政府の市場に対する、中央の地方に対する統制を強化すること、その手の政策を「改革」と呼ぶことが往々にしてあるのです。習近平政権では特にこの傾向が目立ちます。
前哨戦としての座談会のもようから判断する限り、7月の三中全会で「改革」が主な議題となり、審議の対象になるのはほぼ間違いないと思います。問題は、それがどんな改革なのか、および、三中全会を経て、中国がどの方向に変わっていくかだと思います。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

















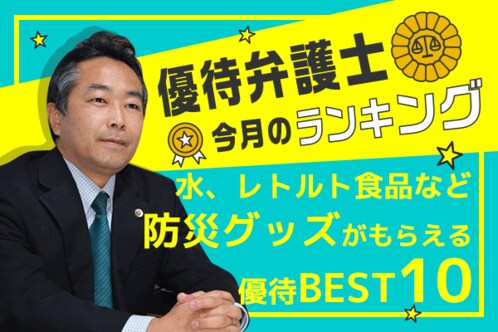
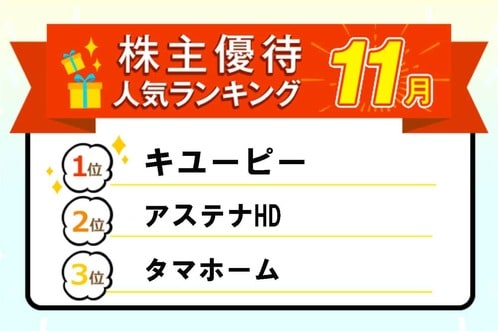





















![[今週の日本株]注目イベント控えるも、相場の行方は視界不良?~日本株の「迷い」と米国株の「強気」のはざまで~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が大幅減)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/4/498m/img_14b007ce9034324da88c6461b2cb4ac961389.jpg)
![[動画で解説]「お金持ち」は幸せか?FIREの方法?どうすればなれる?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/e/498m/img_6ece2aef258682c52604d4427bce2ff980698.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:TSMC(AI半導体の好調で大幅増収増益)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/498m/img_bc72a73e223e6f96675315f7ccc4f88865860.jpg)
![[動画で解説]10月21日【米国株は堅調、日本株は疑問符?~今週は日米企業の決算発表、27日に衆院選投開票を控える~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/7/498m/img_97549b5e9a56fb9e364e36b97d576b6690112.jpg)

























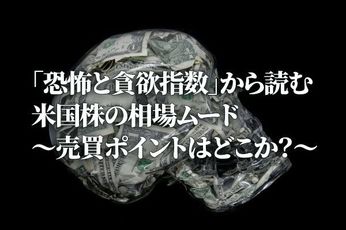







![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)







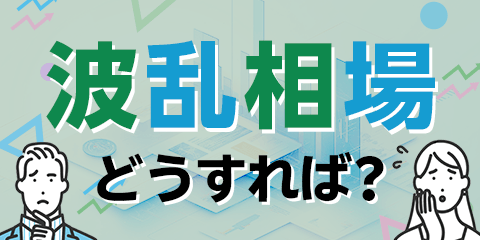



![[動画で解説]日銀、10月は利上げなし~最近の指標点検とワーキングペーパーの含意~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/160m/img_717a7a98769c2f7da8e16c8ae892451162445.jpg)
![[インタビュー] マグニフィセント・セブンが下落すれば、小型株が上昇](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/2/160m/img_d22eda29593bbc137d83f4b36948001f33849.jpg)





