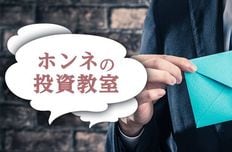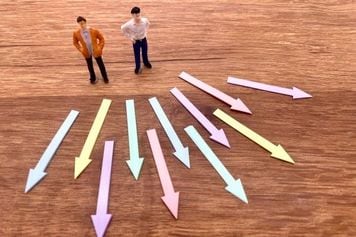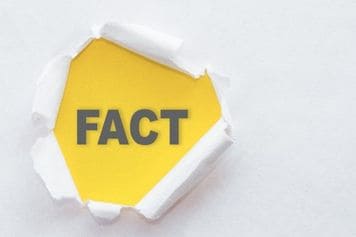「データを見て考えましょう」
近年、特に厄介だと思う「悪しき結果主義者」は、「論理で結論が出る話の手前でデータにこだわる人」だ。
これは、金融・運用業界の専門家にも少なくないし、FP(ファイナンシャルプランナー)のような準専門家やメディア関係者にも多いので、大量のもっともらしい害毒が放出されている。
思いつく例を幾つか挙げてみよう。
ドルコスト平均法が「有利だ」と言えるものでないことは、「機会費用」、「サンクコスト」の概念を知っていれば直ちに分かることだが、例えば、リーマンショックを含む期間のデータを見せることで、「有効だ」と言い張るような場合がある。運用はそもそも20年、30年と続く営みなので、リーマンショック前後の20年といったデータは、有効な原則の根拠にも証明にもならない「特定の一例」に過ぎない。将来の意思決定のためには無駄なデータだ。
インデックス運用にアクティブ運用を組み合わせる「コア・サテライト運用」のような方法は、少し考えると論理矛盾が分かりそうなものだが1、たまたま上手く行っている基金の例などを持ち出して「工夫によっては上手く行く」などと言いたがるような向きもある。
仮にポートフォリオを作る作業に意味があるとすれば、ESGで制約された運用は、無制約な運用に勝ることは論理的にはあり得ないのだが、「ESG投資が有効かどうか、データを見て検証すべきだ」と言うともっともらしく聞こえる。現実には、実際に運用されている2つのポートフォリオを較べた場合に、ESGを反映したポートフォリオがたまたま好成績を収める可能性はある訳だが、それがESG投資の優位性の根拠になるわけではない。
何れも、論理で分かることに結論を出そうとせずに、根拠にも証明にもならないデータを持ち出して思考をストップさせる点に迷惑がある。
困るのは、一つには、10年、20年、30年といった期間のデータは、運用の検証としては全く不十分であるにも拘らず(運用期間を20年と想定するなら、統計のサンプル数で言うとN=0.5〜1.5にすぎない)、人間の体感としては意味のあるデータであるように思いやすいことだ。
そして、もう一つには、データを挙げて検討した方が、本当は頭を使っていないだけなのに、立派で丁寧な検討に見えることだ。
投資や金融の世界で「正しい」と言える重要な原則の多くは、データなしでも論理で十分結論が出る話だ2。結論が分かっている話なのに、その手前でぐずぐずとデータを検討することで時間を食うのは全く非効率的だ。
データ好きの悪しき結果主義者にまともに付き合うと、時間と根気を無駄に消費する。しかも、この連中は、書籍や記事を書いたりするので、時に影響力が大きく、同類を増やすこともある。
要注意の相手だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.アクティブ運用の組み合わせでは凌駕できないからインデックス運用が「コア」とされているのだ。「サテライト」と名付けたからと言ってアクティブ運用を上手く選べるようになる訳ではない。サテライト部分は無意味且つ余計である。
2.「インデックスファンドのアクティブファンドに対する優位性」、「手数料コストの高い投資信託がダメであること」、「運用期間が20年あっても、絶対損をしないとは言えないこと」、「経済が低成長でも株式投資でリスクプレミアムが得られること」、など枚挙にいとまがない。
「私はこうして上手くいきました」
悪しき結果主義者の最後の類型は、自分の経験に固執する人物だ。これは、投資家のプロ・アマを問わず、それぞれに一定の割合で存在するようだ。
例えば、投資銘柄の選び方、売買タイミングの判断方法、アセットアロケーションのリバランスの方法などについて、自分が過去にやって来て、結果的に上手く行った方法をあたかも実証で有効性が証明された方法であるかのように語る。
プロの運用者の場合は、対顧客用のアピールがビジネス上必要なので、少々大目に見てやる必要があるかも知れないが、先ほどの比喩では「N=1」に過ぎない自分の経験が、本人にとっては無上の価値とリアリティを伴った真実のように思えるのだろう。
一般に、人がどの程度知的なのかは、その人が自分自身をどの程度客観視できるかから推測することができるが、投資にあってはスリルの体験と実際の損益が絡むので、自分の経験を「単なるN=1にすぎない」と客観視できなくなる人が少なくない。
普通の話では立派な教養人であっても、投資の話にあっては自分の経験を過大評価する愚か者になる、という人が少なくない。それだけ損得の刺激が伴う投資の経験は強烈なのだろう。
そして、そういった話を、「実際に経験したことだから価値がある」と思って聞きに来て感心する人がしばしばたくさん集まってくるので、話者には反省の契機が生まれにくい。悪しき結果主義者が再生産される。
投資には、「経験」の過大評価を通じて、時に人間の知性を劣化させる魔力がある。古今東西のマーケットが本質において進歩しにくいことの大きな原因だ。




















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)
![[動画で解説]植田総裁・名古屋講演のメッセージ~政府・日銀にとって御誂え向きの2024年7-9月期GDP~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3fb371897205e7696fbfa011f2bc1cb7104479.jpg)
![[動画で解説]「エンゲル係数」上昇の背景に世界分断あり](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d62961de68f1df741a9eba8339b2f7369057.jpg)