バランス・ファンドのファンドマネージャーに
これも詳細を省くが(上司の決算操作を見付けて社内で告発したのだ)、楽しい為替ディーラー生活は短期間で終わりとなった。財務部のプロジェクト・ファイナンスの部署に異動となった。時々刻々変化して損益が発生する「マーケット」から離れて仕事がつまらなかったので、転職を考えるようになった。
あれこれの活動の末転職を決めた先は、最大手の証券会社系列の投資信託運用会社だった。新卒で就職してから約4年での転職だった。「外国為替」にも魅力を感じていたが、ゲームのテンポが速いことと、「売る・買う」の2択でシンプルでありすぎることから、株式の運用に興味を持った。
投信会社の当時の社長さんが「ファンドマネージャーがやりたくて転職してきたのだろうから、早くやらせてやろう」と言って、入社1年で定時定型(毎月似た運用方針のファンドが設定される)のバランス・ファンドを運用する部署に異動させてくれた。
1本目の担当ファンドは「株式型エース8602」(1986年2月の設定)という国内株式40〜50%、外国株式10〜15%、外国債券10〜15%、国内債券25〜35%といった見当のバランス・ファンドだった。
約230億円のファンドのファンドマネージャーとなった。外国為替や債券については、当時の投信会社の人々よりも筆者の方が詳しかったので問題はないのだが、それまで、株式運用の経験は全く無かった。
何はともあれ、株式投資に関する知識を仕入れなければならない。書店に行って、株式投資の入門書・必勝本その他の一般向け書籍を20冊以上買い込み、更に投資理論についていくらか書かれていた「経営財務論」といったタイトルの大学生や証券アナリスト向けの教科書を買ってきて、手当たり次第に読んだ。
株式投資の入門書は、当時も今も、1.企業の評価の仕方・銘柄の選び方、2.投資タイミングの選び方(主にチャート分析による)、3.自慢話(事実の度合いは本による)、が多い。敢えて差を探すと、当時は、今よりも2.の比率が高かったように思う。
様々な本を読んで、あれこれ考えるうちに、「これは間違いに違いない」と分かる事柄、「これは使えるかも知れないので、留保条件付きでノウハウの候補にしておこう」と処理する事柄に、知識の分類が少しずつ進んだ。株式投資の前に、趣味で始めた競馬の本で、「最初に誤った先入観を持つと、後で修正に苦労する」と分かっていたので、短期間の多読だったが、慎重に読んだ。
後者の教科書的な本は、内容自体が直接役に立つものではなかったが、参考文献として紹介されている外国の(殆どは米国の)論文が後に役に立った。分野は投資に限らないが、日本人の学者が書いた教科書は、オリジナルな考えを書いたわけではなく多くの内容が外国の研究成果の紹介なので記述自体には迫力がないが、学説のバランスを考えて紹介しているので、参考文献リストが後の学習の役に立つことが多い。
「投資事始め」から1年後くらいからになるが、「外国の論文を読んで、日本の株式運用に利用する」方法はビジネス・パーソンとして、長年役に立った。投資以外の分野でも、同様の手を使って仕事の役に立った経験を持つ人は少なくあるまい。






















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

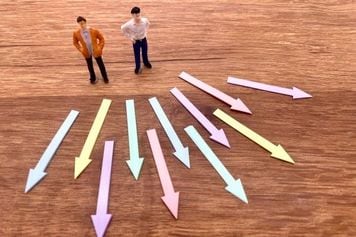
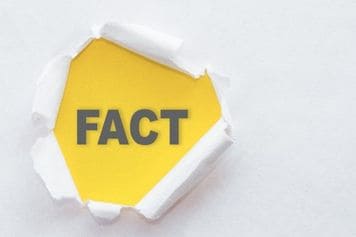








































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)





