原則は「五分と五分」
「グロース(成長)」か、「バリュー(割安)」か。運用の「スタイル」として、或いは銘柄の特徴として、投資の世界ではよく使われる言葉だ。最近では、特に米国で、グロース銘柄のパフォーマンスがバリュー銘柄に対して圧倒的であることが話題になっている。
歴史的には、運用会社、運用者の投資スタイルを表す言葉としての使われ方が先行していた。英米の運用会社やファンドが自らの運用哲学を自称する時に、「グロース」、「バリュー」或いは、その折衷案としての「グロース・アット・リーズナブル・プライス(略称・GARP)」(成長性を重視するが株価評価も重視するといった意味合い)などといった言葉を顧客向けの説明に使っていた。
日本の運用業界は10年遅れくらいで英米を真似るので、日本の運用会社も年金基金などの顧客向けにこうした言葉を使うようになった。もっとも、日本の運用会社は、親会社が大手金融機関で天下り社長が多く、運用が組織を中心に行われて個性の突出を嫌うことが多かったため、「GARP」的なスタイルを旗印にする、退屈な説明をする会社が多かった。
1990年代には、運用スタイルを巡る議論が年金運用業界を中心に盛り上がった。グロース運用、バリュー運用、それぞれの「スタイル・ベンチマーク」として、グロース指数、バリュー指数などのスタイル・インデックスが話題になった。インデックスを定義する際の「スタイル」の基準としては、PBR(株価純資産倍率)が使われる場合が多く、市場の平均よりもPBRが高い銘柄を「グロース(銘柄)」、低い銘柄を「バリュー(銘柄)」とすることが多い。
2000年代の中頃くらいまでには、「長期的にはバリュー銘柄のパフォーマンスがいいのだ」と言われることが多く、バリュー銘柄に投資していると市場平均に勝てるはずだと言う人が学者なども含めて多かったのだが、昨今のグロース銘柄の圧倒的な優勢の陰で口をつぐんでいるようだ。
グロース銘柄、バリュー銘柄に関して、原則論的に有利不利はない。
架空の例を設定する。共にEPS(一株当たりの利益)が100円で、BPS(一株純資産)が1,250円のA社とB社の株式を考えよう。ROE(自己資本利益率)は共に現在8%だ。ここで、A社の成長率が永続的に+2%で、B社の成長率が−2%で、共に割引率が6%と評価された場合の理論株価を計算してみると、A社が2,500円(100/(0.06-0.02)=2,500)、B社が1,250円になる(100/{0.06-(−0.02)}=1,250)。PBRはA社が2倍で、B社が1倍だ。PERはA社が25倍、B社が12.5倍だ。
A社の利益が予定通りに伸び、B社の利益が予定通りに縮むなら、両社の株式の投資家にとってのリターンは同じはずだ。
利益の面を考えると、例えばA社は、投資家が「かつて思っていた成長率」よりも、より高い成長率が予想されるようになれば、予想の上方修正を反映してリターンが上振れすることになる。成長株投資で典型的に起こる成功例はこうした要因によるものだと考えられる。
しかし、B社の利益がかつて考えられていたほど悪くない、という事態が将来に起こった場合も、リターンの上振れは起こる理屈だ。
どちらが起こりやすいかは、一概には何とも言えない。
割引率も影響する。割引率はリスクフリー金利とリスク・プレミアムの合計だが、例えば、バリュー株であるB社の方がA社の6%よりも投資家の要求するリスク・プレミアムが大きいとした場合、B社の現在の理論株価は1,250円よりも更に下がる。そして、この下落した株価でB社に投資する場合の期待リターンは、A社に2,500円で投資する場合の期待リターンよりも高い。こうした現象が継続的に起こるとすると、「バリュー株に投資する方が、グロース株に投資するよりも有利だ」という状況が継続し得る。
問題は、バリュー株のリスク・プレミアムの方が大きくなる理由があるかどうかだが、かつて長期的にはバリュー株が有利なのだと考えられていた頃のファイナンスの論文では、「PBRが低い銘柄には倒産リスクがあり、投資家がこれを嫌うためリスク・プレミアムが大きくなる(のではないか?)」といったやや苦しく聞こえる説明が時々あった。
もちろん、こうした状況にある銘柄に有利な投資のチャンスが隠れている可能性もあり、バリュー投資の大きなヒントになるので、覚えておいて損はない。
ただ、大きな原則を言うなら、グロース銘柄、バリュー銘柄、何れに投資するのが有利なのかは「どちらとも言えない」。有利・不利は「五分と五分」が原則だ。利益予想に有利な変化があるか、リスク・プレミアムに有利な変化があるか、リスク・プレミアムの水準自体が大きいか、何れかの場合に、その銘柄は市場平均をアウトパフォームするパフォーマンスを上げる可能性が大きい。
重要なのは、「意外な変化」と「リスク・プレミアム」だ。






















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)




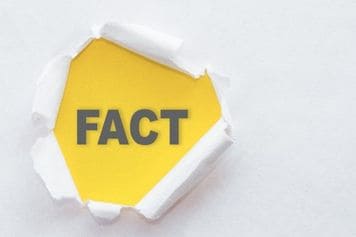








































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)





