相続税の節税相談がとにかく多い
筆者の本業は公認会計士・税理士で、相続に関する業務も数多く行っています。相続相談もよく受けるのですが、とにかく「相続税を節税したい」という相談が多いのです。
先代の相続の時に税金をたくさん払って苦労したから、自分の代ではできるだけ相続税を減らしたい、というケースも多いですし、単純に税金は少なければ少ないほどよい、とお考えの方もたくさんいます。
皆さんのお話を聞いていると思うこと、それが「具体的にではなく、漠然となんとなく税金を減らしたいと考えているなあ」ということです。
そもそも相続税はいくらかかるのかを知らない人が多すぎる
筆者は生前の相続対策を立案・実行するにあたり、最初に「現状把握」を行います。どのような財産を持っていて、その金額はいくらか、そして相続人になる人は誰なのか。
これが分かれば相続税の概算額も計算することができます。
しかし相続税を減らしたいとご相談に来る方に、現状の財産がいくらなのかを聞いてみると、「よく分からない」という返事が返ってくるケースがとても多いのです。
以前、相続税が心配でたまらないという方の財産を集計してみたら8,000万円ほどで、相続税の金額も財産の数%程度でした。現預金の割合も高いので、相続税を節税するための対策は特段必要ないですよ、とお伝えしたら安心されていました。
人間というのははっきりしない物事に対しては漠然とした不安を覚えるものです。
でも、現状の財産がいくらで、相続税がいくらかかるかが明らかになれば、その不安は解消しますし、何よりもご自身や親御さんがどのような対策が必要なのかを明らかにすることができます。
相続対策には順番がある
多くの方が、相続対策の中で最も重要なのが相続税を節税することであり、それを実現させようと税理士や金融機関、不動産業者、保険会社の営業マンなどに相談を持ち掛けます。
この相談相手が誰かというのがとても重要で、例えば節税商品を手掛ける会社や代理店の人に「相続税を節税したいんです!」と伝えれば、喜んで節税商品を持ってきてくれるでしょう。でもそれが逆効果となることも否定できません。
相続対策には大きく
- 遺産分割対策(誰にどの財産を相続させるか)
- 納税資金対策(相続税の納税資金をどのように確保するか)
- 相続税対策(相続税をどのように節税するか)
の3つがあります。
これ以外に近年では「認知症対策」も重要となっていますが、他の3つと少し毛色が異なるため今回は触れません。
実は多くの人が行いたいと思っている「相続税対策」は、順序としては最も後です。まず行うべきが「遺産分割対策」であり、その次に「納税資金対策」です。相続税対策はその後で必要があれば行うという位置付けです。
「遺産分割対策」と「納税資金対策」の後でないと相続税対策が必要かどうか分からない
ですから筆者であれば、節税商品を取り扱っている業者ではありませんから、まずは現状把握をして、どの財産を誰に渡したいのかを聞きます。渡す財産を決めたら、相続人それぞれが相続税を納税するための資金があるかを確認します。
また、渡す財産の内容によっては、代償分割(もらう財産の多い人が少ない人に金銭を渡して財産のバランスを取ること)を行うための資金が必要となります。
この段階で、納税資金や代償分割のための資金が不足するようであれば、遺産分割の内容を見直したり、生命保険を使って納税資金を確保したりします。
もしくは、生前に不動産を売却して資金を確保することもありますし、相続発生後速やかに不動産を売却して相続税納税に間に合わせるために、どの不動産を売却するかを決め、早めに境界確定のための測量手続きに取り掛かる、という場合もあります。
このように、誰にどの財産を渡すかを決め、それにより納税資金が不足するようならば手当てを施してからようやく相続税の節税に取り掛かるという流れになります。
そのため、相続税の節税などやっている場合ではなく、まずは納税資金の確保が急務、ということも多いです。
後で後悔しないためにも相続対策の順番通りに実行することが大事
でも、節税商品を扱う業者に「相続税を節税したい」と相談したら、「いやいや、まずは遺産分割の内容を決めて、その後に納税資金を確保するための対策を打って、その後でないと相続税の節税はすべきではないですよ」と果たして言ってくれるでしょうか?なかなか難しいでしょう。
その結果、節税商品を購入したことによりキャッシュが減少し、納税資金の不足に後から苦しんだり、分割しにくい節税商品であれば遺産分割の際にトラブルを引き起こす可能性もあります。
何となく「相続税を減らしたい!」と思って業者のところに行くのではなく、先に遺産分割の内容や納税資金の工面についてしっかりと対応した上で、本当に相続税を減らすことが一家にとって有用であると確信を持てるようになってから相続税対策を行うようにしましょう。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

















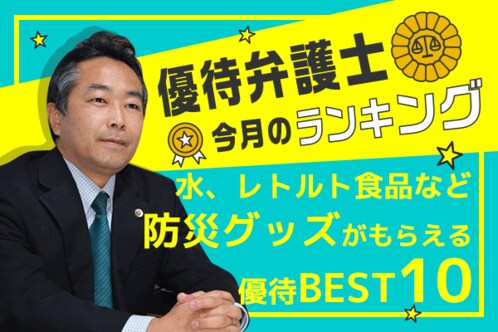
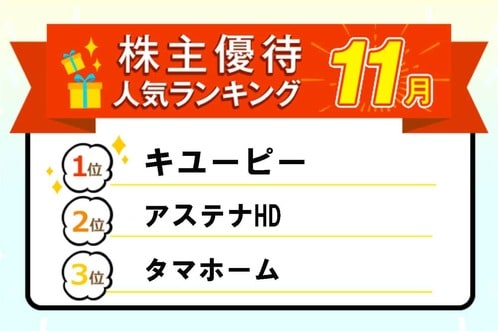





















![[今週の日本株]注目イベント控えるも、相場の行方は視界不良?~日本株の「迷い」と米国株の「強気」のはざまで~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が大幅減)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/4/498m/img_14b007ce9034324da88c6461b2cb4ac961389.jpg)
![[動画で解説]「お金持ち」は幸せか?FIREの方法?どうすればなれる?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/e/498m/img_6ece2aef258682c52604d4427bce2ff980698.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:TSMC(AI半導体の好調で大幅増収増益)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/498m/img_bc72a73e223e6f96675315f7ccc4f88865860.jpg)
![[動画で解説]10月21日【米国株は堅調、日本株は疑問符?~今週は日米企業の決算発表、27日に衆院選投開票を控える~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/7/498m/img_97549b5e9a56fb9e364e36b97d576b6690112.jpg)


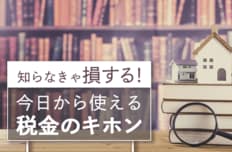






















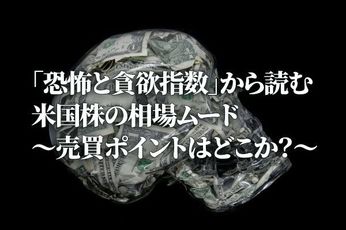







![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)







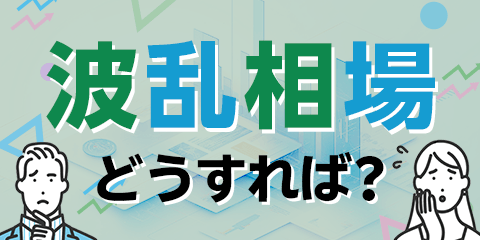



![[動画で解説]日銀、10月は利上げなし~最近の指標点検とワーキングペーパーの含意~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/160m/img_717a7a98769c2f7da8e16c8ae892451162445.jpg)
![[インタビュー] マグニフィセント・セブンが下落すれば、小型株が上昇](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/2/160m/img_d22eda29593bbc137d83f4b36948001f33849.jpg)





