先週の日本株は、日経平均株価(225種)とTOPIX(東証株価指数)が5日間ずっと上昇を続け、9月1日(金)にはTOPIXが1990年7月以来のバブル経済崩壊後最高値を更新。
日経平均が前週末比1,086円高の3万2,710円に達するなど、非常に力強い値動きでした。
上昇の要因は、8月相場の頭を押さえつけていた中国経済への不安感が後退したことや米国の長期金利の指標となる10年国債の利回りが4.3%台から一時4.0%台まで下落したことなど、海外要因が主な理由でした。
外国人投資家の売り越しが直近まで続き下落方向に行き過ぎたため、自律反発で上がったことも理由かもしれません。
1ドル=145~147円台の円安を背景に、機械、鉄鋼、輸送用機器(自動車)など外需株が買われ、原油高をきっかけに資源関連株が上昇するなど、株価が割安な日本の大型株に対する見直し買いが再開したことも大きかったようです。
それは、日経平均が6月19日に付けたバブル後最高値3万3,772円より、いまだ1,000円弱ほど低いのに対し、TOPIXは8月1日のバブル後最高値をたった1カ月で更新していることからも明らかです。日経平均は割高なハイテク株比率が高く、TOPIXは時価総額が大きな自動車、鉄鋼、商社などの外需株、銀行、情報・通信など割安な内需株の影響が強く表れます。
一方、世界中の投資家が運用指針にする米国のS&P500種指数も前週末比2.5%高と2週連続の上昇。
週明け4日の東京株式市場の日経平均は、週末の米国株が米雇用統計発表後に無難な値動きだったことから、続伸。終値は前週末比228円高の3万2,939円でした。円安を追い風にトヨタ自動車(7203)などが値を上げました。TOPIXも再びバブル後最高値を更新しました。
今週の日本株は外国人投資家による買い戻しなどで、さらに高値を更新する展開に期待が持てそうです。
先週:ジャクソンホール会議通過で相場好転、日本株に過去最高レベルの恩恵!
先週の日本株急上昇の理由は複数あり、なかなか一口では言えません。
先々週に開催された各国中央銀行関係者のシンポジウム「ジャクソンホール会議」を無難に通過したことで、米国の政策金利を決める次回9月19日(火)~20日(水)のFOMC(連邦公開市場委員会)ではとりあえず追加利上げがなさそうだという思惑が広がったことも大きいでしょう。
中国の不動産最大手の碧桂園(カントリー・ガーデン)が債務不履行(デフォルト)危機に陥るなど不振続きだった中国経済に、少し明るい材料が見えてきたことも追い風でした。
具体的には8月28日(月)に、中国政府が株式取引にかかる印紙税を引き下げる証券市場対策を実施。
31日(木)、中国国家統計局発表の8月製造業購買担当者景気指数(PMI)が好不調の境目となる50を5カ月連続で下回ったものの、予想以上に上昇したことが好感されました。
東京証券取引所の投資部門別売買動向によると外国人投資家は日本株の現物を8月第3週に7,415億円、第4週に2,046億円と1兆円近く売り越しており、その自律反発で上がったというのも大きな理由かもしれません。
サウジアラビアやロシアが先週、10月まで原油の減産や輸出削減を延長すると表明したことで原油価格が上昇し、世界各国に油田の権益を持つINPEX(1605)が前週末比4.7%高、資源に強い商社・三菱商事(8058)が6.9%高となるなど、資源株の調子がよかったことも上昇相場に貢献しました。
米国では29日(火)発表の民間調査会社コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が予想を下回るなど、景気・雇用関連の指標がそれほど良くありませんでした。しかし、「悪いニュースは良いニュース」の格言通り、景気が悪化すれば、米国の中央銀行に当たるFRB(連邦準備制度理事会)が金融引き締めを緩めるだろうとの見方から好感して、株価が上昇しました。
「あまり良くない景気・雇用指標」の発表で金利が低下することで、株価の上昇に弾みがつく傾向が先週、かなり顕著でした。
弱い経済指標が連続したことで、長期金利の指標となる10年国債の金利は先週の4.3%台から、9月1日(金)には一時4.0%台まで低下。
金利低下の追い風もあって、AI(人工知能)向け高速半導体の販売が絶好調のエヌビディア(NVDA)は前週末比5.4%高と上昇に転じました。
8月23日(水)の決算発表以降、好材料出尽くしでいったん売られ、本連載でも「AIバブル打ち止め!?」と書きましたが、先週のエヌビディア株はアナリストの業績予想引き上げもあって再び株価が躍進しています。
8月31日(木)発表の7月個人消費支出の価格指数(PCEデフレーター)は年同月比3.3%の伸び、変動の激しいエネルギーと食品を除くコアPCEデフレーターは4.2%の伸びといずれも予想通りで、米国株の反応はまちまちでした。
9月1日(金)に発表された米国の8月雇用統計は、農業部門以外の新規雇用者数が前月比18.7万人増と予想を上回りましたが、新たに職を求めて労働市場に参加した人が増えたため、失業率は3.8%に上昇し、平均時給の伸びが鈍化するなど、方向性を欠くものでした。
その結果、週末を控えた1日の米国株はわずかながら上昇しました。
日本ではIT系成長株の動向がわかる株価指数・東証マザーズ指数が米長期金利上昇が一服し、前週末比1.8%高と続伸。先々週(8月21~25日)の前週末比4.3%高に続きました。
週後半は、TOPIXに対する影響力の高い重厚長大産業株が上昇したため軟化したものの、東証マザーズ指数の主力銘柄であるクラウド会計サービス・フリー(4478)の9月1日(金)終値は前週末比8.9%高、VTuber関連ビジネスのカバー(5253)は7.0%高となるなど、個人投資家に人気が高い新興成長株市場にも活気が戻ってきました。
高配当利回りで割安な重厚長大産業の株、株価の上昇力に期待できる新興成長株など、異なる視点でさまざまな有望株を発掘できる2023年の日本の個別株は、現行の一般NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)で駆け込み投資したい、貴重な投資対象といえるでしょう。
今週:実質賃金下落で株高の「皮肉」、現行NISAで日本株に駆け込み投資すべき理由
今週は9月4日(月)の米国市場がレイバー・デイ(労働者の日)で休場です。
そのため、週前半は先週の勢いが継続して、TOPIXがバブル後最高値をさらに更新し、日経平均が8月2日以来となる3万3,000円台を回復する可能性も高いと思われます。
今週は、米国で発表される経済指標に、9月6日(水)公表の全米供給管理協会(ISM)の8月非製造業景況指数以外、あまり注目度の高いものがありません。
中国に関しては、不動産最大手の碧桂園が人民元建て社債の支払いについて先延ばしで合意したものの、他のドル建て債務などの支払い期限に関する交渉は当面綱渡りの状態が続きそうです。いつ何時、不動産バブル崩壊に直結する悪いニュースが飛び込んでくるか、分かりません。
日本では8日(金)に2023年4-6月期の実質GDP(国内総生産)の改定値が発表。
8月15日に発表された同速報値は前期比年率換算で6.0%成長と、円安による自動車販売など輸出の好調とインバウンド(訪日外国人観光客)の旺盛な消費が貢献して非常に大きな伸び率でした。
ちなみに訪日外国人の国内消費は、統計上は「サービス輸出」という外需に分類されます。
しかし速報値では、GDPの過半を占める国内個人消費が前期比0.5%減と3四半期ぶりにマイナスに転じ、コロナ明けの旺盛な消費回復が早くも息切れしました。
今回の改定値でも、個人消費の伸び率の変化に注目が集まりそうです。
一般の消費者感覚としては、度重なる食品の値上げに加え、先週レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格が185.6円と過去最高値を更新するなど、消費意欲が減退しつつあるのが実感ではないでしょうか。
そんな中、8日(木)には厚生労働省が7月の毎月勤労統計を発表します。
物価上昇を加味した6月の実質賃金は前年同月比1.6%減となりました。名目賃金は2.3%増の約46万円と上昇したものの、3%を超える物価上昇率に追いついておらず、今回も実質賃金の上昇は望み薄です。
実質賃金の下落は日本銀行が金融緩和を続ける口実になるため、日本株にとってはプラス要因になっています。
物価上昇に追いつかない日本人の実質賃金の目減りが、円安を誘発し、それにともなって日本株の上昇につながるのは皮肉といえば皮肉です。
ただ、日本人からは皮肉に思える現象も外国人投資家から見ると、インフレや賃金上昇に悩むほかの国の株価に比べて日本株がはるかに割安な要因として映ります。
今週は日ごろ、あまり注目されていない日本の経済指標の発表に、外国人を含めた投資家が反応して株価が変動する可能性もあるでしょう。
日本で一生懸命働いても、物価の上昇に賃金上昇が追いつきません。
だからこそ、少額資金でもかまわないので、2023年に終了する現行NISA、2024年から非課税保有限度枠が1,800万円に大幅拡充される新しいNISAで投資を始めて、少しでも人生を豊かにする方法を独力で模索する必要があるといえるでしょう。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)
















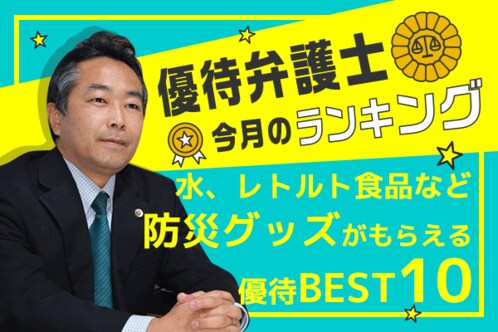
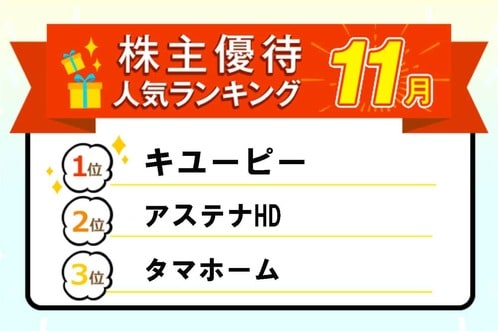























![[動画で解説]株価急騰を招いた金融政策発表から1カ月が過ぎた中国~財政政策への期待は報われるか?~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/a/498m/img_8a6c96cf4ead7b0268fe7f71a28c5fd174858.jpg)
![[動画で解説]「短期ドル/円の見通しは、「151円台をキープする限り、円安継続」!」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/498m/img_94157f1cc65cda079f19b67766ae663646051.jpg)
![[動画で解説]【日米株】年末ラリーへ 今そこにあるハードル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/6/498m/img_36b800bb6c24b2c67166a5873aae553259027.jpg)
![[動画で解説]中国GDP鈍化、デフレと不動産不況続く。それでも大規模な景気刺激策に慎重な理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/0/498m/img_505d64bd347e5f9efb94cdb4e523377b51921.jpg)


































![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)


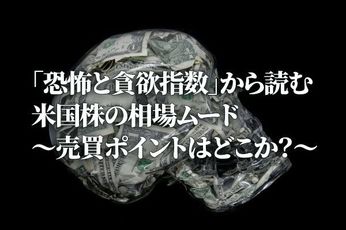


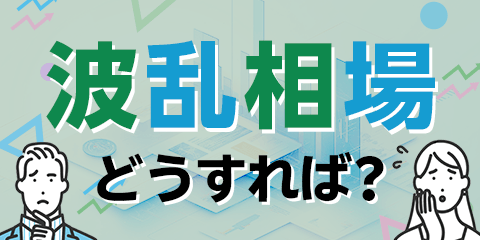



![[動画で解説]大激戦!米大統領選挙で世界分裂は直らない](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/e/160m/img_fe0df75b485762eaa90ed95b8238cdaf69929.jpg)

![[動画で解説]iDeCo(イデコ)ファースト!NISA(ニーサ)より節税メリット大!デメリットも理解して活用](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/2/160m/img_b2ffc423fe5754f6473aa1748346698d47085.jpg)
![[動画で解説]【S&P500の危機?】トランプショック到来...!?米大統領選挙の今後](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/160m/img_4d37c6668863c2c90260de7232facac5104960.gif)




