一物一価が成立しない
「一物一価の法則」という言葉がある。経済の世界では、競争と裁定が働いて同じモノに対しては同じ価格が形成されるという意味だ。
例えば家電製品のように同じ型番なら商品が同じ内容であることが確実な商品の場合、販売店間の競争や安い商品を求める顧客の行動の結果、同一商品の値段は相当程度近同一価格に収斂する。近年、競争の中には楽天市場やアマゾンのようなネット通販が、価格情報の伝播には価格コムのような価格比較サイトが、一物一価の実現を一層後押しするようになったことは、読者もご存じの通りだ。
そして、こうした競争的な価格形成は、消費者にとってプラスに働く。
一物一価の法則はサービスの価格にも働くはずだ。同じくらいの腕のマッサージ師が並んで店を出せば、時間当たりの価格が安い店の方が流行るだろうから、両者の価格設定は似たものになるだろう。
ところが、「運用」というサービスの価格はそうなっていない。
国内株式の運用を例に取ると、リテール向けの投資信託であればアクティブファンドで顧客が払う税抜きの信託報酬が年率150bp(bp:ベイシスポイント。100bp=1%)程度で、うち運用会社の取り分が70〜80bp程度であることが多い。一方、この同じ運用会社が年金基金向けに行うアクティブ運用は、「運用会社要覧」(投資顧問業協会編)にある料率表(詳しくは後述)ベースで、10億円までの小口で45bp、100億円〜200億円の間で15bp、500億円を超える金額の運用では12bpとぐっと安い。
リテール向けの投信の手数料を運用会社が取るレベルで見るとしても(顧客にとってはトータルの信託報酬が問題だが…)、数倍の差がある。
基本的に、同じ運用会社は社内でだいたい同じ情報を共有しているし、投信のファンドマネジャーの方が、年金のファンドマネジャーよりも明らかに上手い人・優秀な人がなるといった差があるわけでもない。日本の運用会社の場合、むしろ、うるさい顧客である年金基金の相手をしなければならない分、年金運用のファンドマネジャーの方により優秀な人材を回す傾向があったかも知れない。
DB年金の運用手数料の形成
主に年金基金が運用を委託するDB(確定給付)の年金資産の運用の場合、先に例示したような運用料率水準が運用会社の間のかなり広い範囲で共有されている。
ある投資顧問会社の役員から1990年代の終わり頃に聞いた話によると、投資顧問会社は、1990年から厚生年金基金の運用への参入を認められ(それ迄は信託銀行か生命保険会社でなければ年金運用の受託が出来なかった)、最初に当時の厚生年金基金連合会に料率表を提示する前に、複数の会社が運用料率のすり合わせ、有り体に言って「談合」を行った。その結果出来たのが、現在の料率表の原型であり、その料率水準は、当時から大きくは変わっていない。(当時その投資顧問会社では、この料率を「連合会料率」と呼んでいた。現在もそういう呼び方があるかどうかは、未確認だ)
当時、投資顧問会社各社の幹部が考えたのは次の二点だった。
先ず、信託・生保に対して競争力のある料率を提示しないと運用の受託額はなかなか増えないだろう。
次に、低めの料率だと当面は儲からないが、シェアを取って、残高さえ積み上げたらやがては儲かるようになるはずだ。
付け加えると、当時、21世紀の初頭にかけて日本の企業年金の資産は大きく増えることが確実視されていたし、投資顧問会社各社は当面の収益よりも親会社(証券会社、銀行など)の体面を考慮して、運用資産残高の拡大を目指した。
付け加えると、先の料率は標準価格、いわゆる「定価」であり、共済年金や大企業の年金基金など資金規模の大きな顧客には、定価の2割引程度(個別の交渉でもっと下がる場合もある)のサービス価格を提示して運用資産の受託を競っていた。
また、アクティブ運用ではなく、パッシブ運用の場合、料率を大幅に引き下げて運用を受託する場合もあった。
とはいえ、DBの年金運用では、はじめから相当に低い水準の価格が形成されていたし、顧客の側の交渉力が強かったために、「手数料を叩かれる」現象が方々で起こった。
その後、1990年代後半から2000年代前半の運用環境の悪化から、厚生年金基金の「代行返上」、基金自体の解散などがあって、年金の運用資産のパイが縮小する時期を経て、現在は、大手の運用会社では、DBの年金運用部門も黒字になっているはずである。
但し、運用資産残高に対する収入はDBの年金運用ではリテール向けの投資信託よりも圧倒的に小さく、運用会社の経営は「名誉は年金運用で得て、利益は投資信託で稼ぐ」といった構造の会社が圧倒的に多い。
リテール投信の運用手数料推移
国内株式のアクティブファンドで見る限り、1990年代に入った直後のリテール向け投資信託の信託報酬水準(販売会社に払う代行手数料等を含む)は80bp強だった。
ところが、1991年に外資系の投信会社が参入したことがきっかけで、料率水準が動く。
外資系の投信運用会社といっても日本国内で営業し、特に商品企画や証券会社(銀行が投信を売れるようになるのは1998年からだ)向けの営業を担当するのは、日本の証券業界出身の人々(殆どが日本人)だった。
彼らは、はじめに、販売手数料の方を上げようとした。投信販売の現場をよく知っている彼らは、証券会社のセールスマン、支店、本社営業企画部(支店の営業を統括している)が、手数料のより高い商品を好んで売ることをよく知っていたからだ。
しかし、さすがに、顧客から見て投信購入時に取られる手数料が上がるのは印象が悪いし、手数料の引き上げにも限界がある。そこで、次に考えた手が、信託報酬水準を引き上げて、販売会社に渡す代行手数料をアップして、証券会社に自社の投信を積極的に売って貰うことだった。信託報酬全体が上がるので、自社の取り分も増やすことが出来るから一石二鳥だ。
一方外資系の投信会社の商品を証券会社が売るようになると、証券会社系列の投資信託運用会社が競争に目覚めざるを得なくなった。彼らは、A証券にはA投信、B証券にはB投信、といった形で、基本的に親証券に一対一対応でぶら下がっていた。親証券会社に、資本も、商品の企画・販売も、さらには人事まで握られつつ、あたかも親証券会社の一部署のようにのんびりと経営していた。しかし、自社の親証券の販売力の一部を外資系等の新参者に取られるに及んで、対抗上、信託報酬水準を上げざるを得なかったのだ。
こうしてリテール向け投信の信託報酬水準が徐々に上がり始め、1994年に1%を超え、1998年前後に1.5%を超えてほぼ今日の水準に達した。
普通は、供給者どうしが競争するようになると、顧客に対して低い価格を提示するようになるのだが、日本のリテール投信の場合、商品の実質的な選択者が販売会社であり、顧客は手数料に鈍感だったので(端的に言って、鈍感だからこそ投信の顧客だったというのが本当の事情だが)、このような歪な競争が起こり、もともとDB年金の運用報酬水準よりも高かったリテール投信の手数料がさらに上昇するという顧客にとっての不幸が起こった。
この状況は、通貨選択型をはじめとする近年の売れ筋投信の多くにあっても継続しており、高分配を売り物にする商品にあっては、国内株式のアクティブファンドの信託報酬水準よりも高い信託報酬水準が設定されているものが多い。
DC年金の手数料水準
さて、確定拠出年金(以下「DC」)が始まったのは2001年からだが、確定拠出年金の運用手数料の水準はどう決まって来たか。
前述のように、運用会社にとってDB年金の手数料水準は「儲けにくい」厳しいものだった。DCを導入するにあたって、同じ失敗は避けたかった。運用会社にとっては、リベンジの機会が訪れた。
DCの導入当初は、リテール向け投信とDCの資産を一緒に運用して、リテール向け投信の信託報酬をDCの運用商品としても取るような商品がラインナップされている会社型DCもあった。
概して言えば、取引の力関係で金融機関側が有利だったり、DCを導入する部署に運用知識が無かったりするケースで、金融機関の言いなりの運用商品をラインナップしたケースでこうした例が多かった。場合によっては、ラインナップの中にまだこうした商品が混じっているケースがあるかも知れない。
年金の加入者にとっては、この低金利の世の中にあって多くが予定利率(積立金の想定運用利回り)5.5%程度で設計されていたDBの企業年金の方が、DCよりも明らかに得だったし、加えて、DCの運用商品ラインナップの中に手数料の高い、あたかも「社員の年金資産を金融機関に売り渡す」商品が混じるのだから、「踏んだり、蹴ったり」だった。
ところが、DCにあっても、さすがに競争原理が働き、また、150bpといった手数料水準では、想定利回りが目立って低下するので、もう少し何とかならないかという声が、DCの顧客側からも上がるようになり、運用会社は、リテール向け投信の代行手数料部分(典型的には信託報酬の半分程度)を除外した、アクティブファンド(国内株式)でも70bp〜80bpの手数料を提示するようになった。
さらに、多くの従業員を抱えていて、金融機関グループ(DCの運営管理機関と運用会社の両方を含む)に対して交渉力が強い大企業がDCを導入するようになり、自社向けDCの商品ラインナップにあって、運用手数料を厳しく交渉するようになり、内外の株式のインデックスファンドで20bp〜30bp程度の商品をラインナップに加えるケースが出て来た(日本を代表する「あの会社」の影響が大きかったと言われている)。
また、ある会社が手数料の引き下げ交渉に成功したという噂が伝わると、他の企業でも手数料引き下げを試みるという連鎖が起こり、DCの運用手数料は低下に向かった。
運用結果は自己責任であるDCといえども、全般的な手数料が高いことは、社員の福祉水準の実質的な引き下げであり、会社から社員に提供出来る価値の減少であり、ひいては会社にとっても損であることが、企業側にも(やっと!)理解されたのだろう。
DCの運用手数料水準は、インデックス・ファンドを中心に、時間をかけて、リテール投信の水準から、DB年金の運用手数料率に近い水準まで低下してきた。
尚、近年、DCにあっては、「アクティブ運用の内容・評価方法を、加入者に十分教えることは、投資教育上無理だ」ということを、正しくも理解する企業が出て来ている(本当は企業の年金基金や共済でも無理なのだが)。金融機関に好都合な手数料の高いアクティブファンドやバランスファンドを漫然と並べている企業型DCは「問題あり」と言えると思う。
大切な余談:会社型DCの評価方法
さて、現在、会社型DCでは、会社によって運用商品のラインナップに大差がある。余談だが、大切なことなので、評価の仕方を伝授しよう。
会社型DCが導入されている会社にお勤めの読者は、先ず自社のDCの運用商品ラインナップをよく見て欲しい。
リスク商品がインデックスファンドだけで、それらが20bp前後の信託報酬である会社にお勤めの方は幸せだ。良い運用対象があるし、間違える可能性がより小さい。DCを担当し、金融機関と交渉した社内の部署・担当者に感謝しよう。
よくあるのは、20~30個くらいの商品が並んでいて、インデックス・ファンドも、アクティブ・ファンドも、運用会社がDCに好適だと称するライフサイクル・ファンド(ターゲット・イヤー別、リスクの大小別などで複数タイプがあることが多い。しかし、実はDCの税制優遇を最大限に活かせない点で、明らかにDCに不向きなダメ・ファンドなのだ)などが雑多に並んでいるケースだ。「あれも、これも型」と名付けようと思う。
「あれも、これも型」のDC商品ラインナップは、中にはいいファンドもある点で「まあまあ」かも知れないが、加入者が間違って不適切な商品を選択する余地を残している点でよろしくない。
選択肢が多いことは、一見悪いことではないように思われるかも知れないが、行動経済学の研究から、人間は選択肢が多すぎる場合、選択行為を放棄したり、選択が雑になったりすることがしばしばあることが知られてきた。
特に不適切なのは、DCで義務づけられている投資教育を、DCを取り扱う取引金融機関に丸投げしているケースだ。前述の「あれも、これも型」商品ラインナップの中で、金融機関に好都合な商品(手数料の高いバランスファンドなど)にDCを取り扱う金融機関が無料で提供する投資教育を通じて加入者が誘導される場合が少なくない。これは、「タダほど高いものはない」の好例だろう。
ただ、商品ラインナップの急速な整理縮小は現実的に難しいかも知れない。当面、社員の側でできることとしては、「投資教育はDCの取り扱い金融機関グループの者ではなく、有料であるとしても、その金融機関グループと利害のない外部の講師を頼むべきだ」と強く要望するといいだろう。筆者は、その種の講師を務めたことがあるが、加入者の多くがDCを的確に使えていないことに驚いた。しがらみのない講師による「正しい投資教育」の効果は大きい筈だ。
新しい動き
さて、リテール向けの投信の手数料がDB年金の運用手数料よりも著しく高いこと、DC年金の運用手数料がリテール向け投信の運用手数料を基準にしたものから特にインデックスファンドに於いてDB年金並みに低下して来たことをご理解頂いたと思う。
ここで、新たな動きが生じたので、ご報告したい。
三井住友アセットマネジメント株式会社は、9月18日より(嬉しいことに)楽天証券を通じて、これまでDC用に提供してきた4つのインデックスファンドを(明細は表1)、DCと同水準の信託報酬(もちろん販売手数料はゼロだ)で通常の公募の投資信託として、リテール向けに販売することを発表した。 プレスリリース
筆者は、個人の資産運用にとって、特に、「三井住友DC全外国株式インデックスファンド」が「優秀な部品」として魅力的な場合が多い筈だと考えるが、リテール向けの投資信託の場合、毎月定額の積立投資がしやすいし、ノーロードなので売買手数料も掛からない。ETFと比較しても遜色のない低コストな運用選択肢だといえる。
今回の動きによって、リテール向けの投信の運用管理手数料水準が、名実共にDC並となり、既にDCの料率がDB年金に近づいていることから、ついにDB年金とリテール投信の巨大な価格差が解消されたと言えるのではないか。消費者にとって、望ましい「一物一価」の実現である。
表1.新たに取り扱う投資信託4本の内容と信託報酬
| 銘柄名 | 内容 | 信託報酬 (税込) |
|---|---|---|
| 三井住友・日本債券 インデックスファンド |
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンドを投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 | 年 0.1728% |
| 三井住友・DC 外国債券 インデックスファンド |
主として「パッシブ外国債券マザーファンド」への投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 | 年 0.2268% |
| 三井住友・DC 全海外株式 インデックスファンド |
主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。 | 年 0.2700% |
| 三井住友・DC 新興国株式 インデックスファンド |
主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。 | 年 0.6048% |
今回の三井住友アセットマネジメント株式会社の判断は、個人投資家にとって画期的だと評価したいが、同様の運用の規模を拡大できれば比較的小さな追加コストで追加的な収入を得られるという点で、既存のDC商品の運用会社にとっても合理的な選択だ。こうした形で、DC向け商品の運用資産残高と運用報酬を拡大したいと考える運用会社は他にもあるのではないか。
また、今回の販売会社である楽天証券以外にも、顧客にとって明らかなメリットと競争力がある商品を取り扱いたいと考える販売会社が出てくるのではないだろうか(楽天証券にとっては、競争条件が厳しくなることを意味するが)。
はじめはインデックスファンドからだろうが、近い将来、アクティブファンドを含む全ての商品にも、こうした動きは拡がる可能性がある。
もちろん、こうした動きは、傾向として投資家にとって好ましい事だ。大いに進んで欲しい。




















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)
![[動画で解説]植田総裁・名古屋講演のメッセージ~政府・日銀にとって御誂え向きの2024年7-9月期GDP~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3fb371897205e7696fbfa011f2bc1cb7104479.jpg)
![[動画で解説]「エンゲル係数」上昇の背景に世界分断あり](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d62961de68f1df741a9eba8339b2f7369057.jpg)




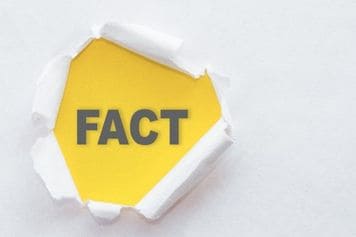











































![[動画で解説]11/22「リスクオフで円高。週末はドル/円の下値探る動きか」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/160m/img_7e50191db2a159e1ee44be91523a403e47243.jpg)

![[動画で解説]株式市場の「強気の終焉」に備える~「買い遅れる恐れ」と「強気の罠」のはざまで~(土信田 雅之)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/9/160m/img_1979020be6c833ae6a0b21d1c7955a1670673.jpg)



