今週は、6月18日(火)発表の5月小売売上高をはじめ米国で景気指標の発表が相次ぎます。
高金利政策が続く中、果たして米国経済がソフトランディング(軟着陸)できるか、それともハードランディング(景気後退)に陥ってしまうかが注目を浴びそうです。
ここ最近、際立っている「AI(人工知能)関連株を中心に力強い米国株、いまひとつ波に乗れない日本株」という構図は今週も続きそうな気配です。
日本株低調の一因は、国の認証試験で不正があった車種の生産停止を表明するなど自動車大手の業績悪化懸念が高まっていることもあります。
トヨタ自動車(7203)が先週1週間で3.2%安となり2週連続の下落となりましたが、今週はさすがにリバウンド上昇に期待できるかもしれません。
しかし、日本株の売買高の約7割を占める外国人投資家は6月第1週(3~7日)に日本の現物株を3週連続となる1,986億円売り越し。
材料難や高値圏にある大型株の利食い売りなどもあり、今後も外国人投資家がいきなり日本株を大規模に買い越す流れに転換するのは難しいかもしれません。
日本銀行の金融政策に対する不透明感も市場の足を引っ張りそうです。
先週14日(金)には日銀の金融政策決定会合が終了し、量的緩和策の一貫として行ってきた日本国債の買い入れ額の減額方針を決定しました。
市場の一部には月間6兆円前後だった買い入れ額の具体的な減額計画が示されるのではないかという見通しもありましたが、減額の具体的な規模や短期の政策金利の追加引き上げに関しては次回7月31日(水)終了の会合以降に見送られました。
これを受けて日銀の金融緩和継続が業績の足を引っ張りかねない銀行株などが、週間の業種別騰落率ランキング下位に沈みました。
14日(金)に系列の証券会社と違法な情報共有を行っていたことが発覚した主力の三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)は2.7%安と高値圏から反落。
先週末の14日(金)日経平均株価(225種)の終値は、銀行株をはじめ上値が重く、見切り売りされる大型株が目立ったものの、前週末比130円(0.3%)高の3万8,814円と2週連続の小幅高でした。
しかし、14日(金)夜間の日経平均先物の価格は大幅に下落。
日銀の植田和男総裁が14日の金融政策決定会合後の記者会見で「(国債買い入れ額を)減額する以上は相応の規模になる」、「データ次第では7月に利上げの可能性もある」と発言したことがタカ派的と受け止められたようです。
週明け17日(月)の日経平均終値は前週末比712円安の3万8,102円まで下げました。植田総裁の発言に加え、フランス下院選挙を巡る極右政党台頭による政局不安から先週末の先物市場が下落した流れを受けて、一時800円以上値下がりしました。半導体関連の値下がりも影響しました。
一方、先週の米国では物価高の鈍化を示す明るい経済指標の発表が相次ぎました。
12日(水)発表の5月CPI(消費者物価指数)は前年同月比3.3%上昇と市場予想を下回り、13日(木)発表の5月PPI(卸売物価指数)は前年同月比2.2%の上昇、前月比では0.2%のマイナスとなり、予想を大幅に下回りました。
物価高の鈍化が鮮明になったことで、機関投資家が運用指針にするS&P500種指数は前週比1.58%高と大幅に上昇しました。
先週:米国の物価高鈍化でAI関連株躍進!日本株は銀行株はじめ内需株が停滞
先週は12日(水)に5月の米国CPIが予想を下回る伸び率となり、ハイテク株を中心に米国株が勢いよく上昇しました。
その直後に終了したFOMC(米連邦公開市場委員会)では参加理事らの今後の政策金利の予想水準を示した「ドットチャート」が発表され、2024年中の利下げ回数の中央値が従来の3回から1回に引き下げられたものの、あまり深刻視されませんでした。
今回発表のドットチャートでは、2025年と2026年の利下げ予想回数が従来の3回から4回に増え、今年に関しても多くの参加者が年2回を予想するなど、実質的にはかなり金融緩和に理解のあるハト派的な見通しでした。
FOMC声明でも、2%の物価目標達成に向けた状況について前回の「一段の進展は見られなかった」という文言が、今回は「緩やかながら一段の進展が見られた」にかわり、市場では9月利下げ観測がより一層、強まる結果になりました。
また10日(月)にはAI(人工知能)関連技術の導入でライバルのマイクロソフト(MSFT)などから遅れをとっていたアップル(AAPL)が、iPhoneなどに独自のAI技術「アップル・インテリジェンス(Apple Intelligence)」を導入すると発表。
アップル株は翌11日(火)に前日比7.26%上昇して史上最高値を更新。週間でも7.92%高と躍進しました。
5月CPI・PPIなど物価高の鈍化を示す指標が相次いだこともあり、米国の長期金利の指標である10年国債の利回りは週初めの4.4%台半ばから14日(金)には一時4.2%を割り込む水準まで急低下しています。
そのため、金利低下が追い風となる半導体関連株やハイテク株が絶好調で、AI関連の主力株である高速半導体メーカー・エヌビディア(NVDA)は前週比9.09%高と続伸しました。
一方、日本株ではアップル株の躍進を受けてiPhoneに電子部品を供給するTDK(6762)が前週末比6.7%高、太陽誘電(6976)が12.0%高するなど、アップル関連株が盛り上がりました。
半導体切断装置のディスコ(6146)が9.7%高、半導体検査装置のアドバンテスト(6857)が4.7%高となるなど、半導体関連株も堅調でした。
ただJR東日本(9020)が5.5%安、大和証券グループ本社(8601)が7.3%安となるなど、陸運や金融など内需株に不調な銘柄が目立ちました。
日本株の命運を握る外国人投資家が再び買い越し基調に転じるには、政策面やインバウンド(訪日外国人)関連以外の内需面で新たな材料が必要になりそうです。
今週:円安と金利低下でも日本株大幅上昇は見込み薄?自動車株や東証グロース市場銘柄に期待!
今週は先週の物価指標やFOMCほど重要ではないものの、米国景気指標の発表が相次ぎます。
17日(月)には6月のニューヨーク連邦準備銀行製造業景気指数、18日(火)には米国のGDP(国内総生産)の7割を占める個人消費の動向が分かる5月の小売売上高が発表。
20日(木)には米国の5月住宅着工件数、21日(金)には製造業やサービス部門などの6月PMI(購買担当者指数)も発表されます。
国内では、日銀の植田総裁が7月追加利上げの可能性は「データ次第」と発言したこともあり、21日(金)に発表される5月CPIに注目が集まりそうです。
国内の物価上昇率が上振れすると7月利上げの可能性が視野に入り、日本株の足を引っ張るかもしれません。
米国では、エヌビディアを強力なけん引役にAI関連株が「バブル」といっていいほど上昇しています。
エヌビディア株は5月の月間上昇率26.9%に続き、14日(金)終値時点の6月上昇率が20.3%に達するなど、まさに破竹の勢いです。
ただ、エヌビディア株を指数に組み入れていないダウ工業株30種平均は先週の1週間で前週比0.54%の下落と逆行安。
極論すると米国株においても「エヌビディアvsその他大勢」の二極化が進んでいます。これほど一部の銘柄だけに依存した米国株価指数の上昇には米国内でも警戒感が強まっています。
為替市場では日銀の金融政策正常化の先行き見通しが不透明になったこともあり、14日夕には一時1ドル=158円20銭台まで円安が進み、ニューヨーク外国為替市場の先週終値も1ドル=157円30銭台で高止まりしています。
米国の金利低下や円安トレンドの継続は本来、日本株にとって朗報のはず。
そのため、今週の日経平均は超えても押し戻されていた3万9,000円の壁を大きく突破する可能性もありそうです。
さらに、中小型の成長株の動向を反映した先週の東証グロース市場250指数は前週比2.7%高と3週連続で最安値圏から反転上昇しています。
業績黒字転換や自社開発の再生医療製品の厚生労働省による製造販売承認の審議入りが報じられたバイオ株のサンバイオ(4592)が3日連続でストップ高。前週末比58.5%も急騰するなど材料株が健闘。
また、資産運用ロボアドバイザー業務を行うウェルスナビ(7342)が前週末比17.3%高するなど、東証グロース市場250指数に対する影響力が高い主力成長株の上昇も目立ちました。
一部には「早くも夏枯れ相場」という指摘もある日本株ですが、再び米国株にツレ高して本格上昇に転じる展開に期待しましょう。











![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

















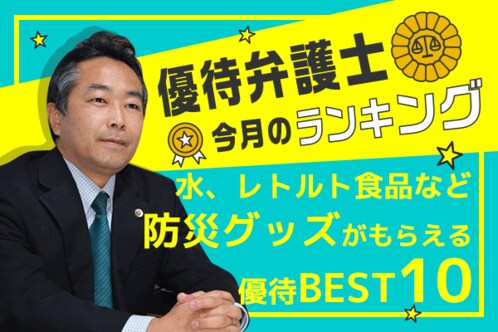
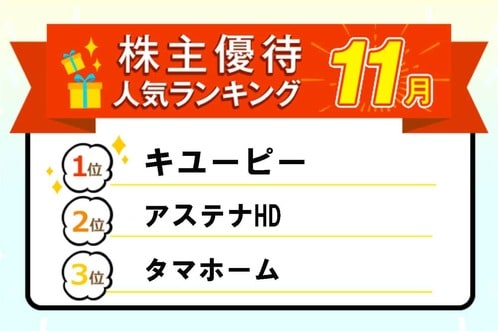





















![[今週の日本株]注目イベント控えるも、相場の行方は視界不良?~日本株の「迷い」と米国株の「強気」のはざまで~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)


![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が大幅減)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/4/498m/img_14b007ce9034324da88c6461b2cb4ac961389.jpg)
![[動画で解説]「お金持ち」は幸せか?FIREの方法?どうすればなれる?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/e/498m/img_6ece2aef258682c52604d4427bce2ff980698.jpg)
![[動画で解説]決算レポート:TSMC(AI半導体の好調で大幅増収増益)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/498m/img_bc72a73e223e6f96675315f7ccc4f88865860.jpg)
![[動画で解説]10月21日【米国株は堅調、日本株は疑問符?~今週は日米企業の決算発表、27日に衆院選投開票を控える~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/7/498m/img_97549b5e9a56fb9e364e36b97d576b6690112.jpg)

























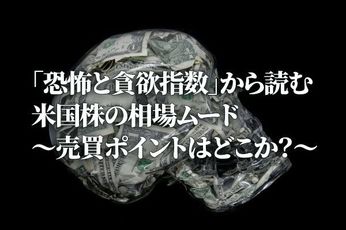







![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)







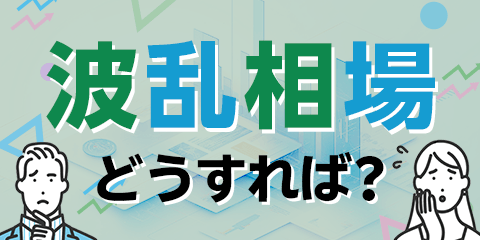



![[動画で解説]日銀、10月は利上げなし~最近の指標点検とワーキングペーパーの含意~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/160m/img_717a7a98769c2f7da8e16c8ae892451162445.jpg)
![[インタビュー] マグニフィセント・セブンが下落すれば、小型株が上昇](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/2/160m/img_d22eda29593bbc137d83f4b36948001f33849.jpg)





