投資家のための金融ビジネスの教科書として
久しぶりに、読書のすすめを書く。取り上げるのは、人気ブログ「金融日記」の管理人であり外資系金融機関でトレーダーの仕事をされている筆名・藤沢数希氏の著書「外資系金融の終わり」(ダイヤモンド社)だ。
本を出す場合、著者と編集者は、タイトルと共にサブタイトルにも大いに悩むので、サブタイトルも紹介する。「年収5000万円トレーダーの悩ましき日々」とある。これが、本のセールスにつながるかどうかは、かなり微妙だろう。年収という下世話な具体性があって興味をひく反面、自分の年収と比べて反感を持って「引いて」しまう潜在読者がいるのではないか。加えて、このサブタイトルで本書が、自慢話や暴露話中心の「きわもの」的な書物であると推測されるリスクを懸念する。
実は、この本は、投資家が金融ビジネスの仕組みを無理なく過不足無く理解ための格好のテキストブックになっている。
金融ビジネスの仕組みを学ぶテキストということになると、民間銀行と中央銀行の関係図が出てきて、「あなたが預金したお金が、巡り巡って産業の資金として生かされています…」といった、中学校の社会科の教科書のようなまだるっこしい話に付き合わされたり、あるいは、いきなり投資の理論や銀行行動の理論モデルが出てくるような教科としての「金融論」に近い教科書になったりしてしまうが、投資家が知っておきたい金融ビジネス知識は、金融機関がどのようにビジネスを営んでいるのか、つまりはどうやって儲けているのか、彼らにはどんなリスクがあるのか、だから何に気をつけなければならないのか、といった話であって、これらはつまるところ、金融ビジネスに関わる「人」の行動に集約される。
金融ビジネスにはどのような人が関わっていて、それぞれがどのような役割とインセンティブ(誘因)をもって、どのように行動しているのか、ということが分かれば、マーケットに関する情報を解釈する上で見通しが良くなるし、証券会社や銀行と付き合う上で何に注意したらいいのかがよく分かる。
金融は「ふつうの人」がやっている
「外資系金融の終わり」は、読者の興味を逸らさない構成で書かれているので、はじめから読んでもいいのだが、投資家のためのテキストとして読むなら、第3章「金融ほど素敵なビジネスはない」と第4章「サル山の名前は外資系投資銀行」から先に読むのがいいかも知れない。
第3章では、宝くじは確実に儲かる素晴らしいビジネスモデルだという話から説き起こして、金融ビジネスの儲けの仕組みと、いかにそれが「美味しい」のかということが、分かりやすく説かれている。大量の国債を抱え込む日本の銀行ビジネスの背景や、「大きすぎて潰せない」巨大金融機関が「世界経済を人質に取る」仕組みがさらさらと説明される。
第4章では、とかくブラックボックスになりやすく、その故に過度に尊敬されたり恐れられたりすることが多い金融機関の仕組みを、外資系投資銀行を例に取って、人間にフォーカスして説明している。
セルサイド(証券会社)とバイサイド(運用会社)といった金融業界の基本的な構図とともに、例えば、プロップ・トレーダー(会社のお金でリスクを取る)、エージェンシー・トレーダー(顧客の注文を市場につなぐ)、バイサイド・トレーダー(運用会社の売買執行係)、といった一口に「トレーダー」といっても行動パターンも経済的条件も全く異なる人たちがいることも説明してくれるので、読者は、いわゆる「市場参加者」の実像をつかむことができる。
文中、一流のトレーダー(プロップ・トレーダー)・投資家が一様にケチであることが書かれているが、確かに、筆者の知る元外資金融のトレーダー氏にも似たようなところがあった。ケチな人全てが一流トレーダーになるわけではないが、質素な生活をしている読者には、一流のトレーダーになる素質があるのかも知れない。
また、アナリストが所属するリサーチ部門の抱える微妙な問題(投資銀行部門との癒着やリサーチ・フロントランニングなど)や、セールス部隊のビジネスの実態、証券会社にとって誰が上客なのか、といった投資家にとって大事なことも分かる。
このパート、そして筆者の思うに、この本の最も重要なメッセージは、「外資系投資銀行も含めて、金融ビジネスは、普通の人がやっているのだ」ということだろう。「凄い人たちがやっているのだ」というイメージは間違っている。彼らにお金の面倒を見て貰うと「いいこと」があるだろうと考えるのは大きな誤解だ。
この誤解で最近の例は、同書の67ページ以下に出てくる野村證券によるリーマンブラザーズ買収の際の、旧リーマン社員に対する前年給与の2年間保証だろう。著者は「野村證券は、欧米の『インベストメント・バンク』に大変なコンプレックスを持っており、何千万円、何億円の給料をもらっている外国人は凄いと勘違いしていたので、そんな凄い連中に見切りをつけられて他社に転職されては困ると考えた」、さらに「本当に大きな勘違いをしたものだ」と、しみじみ、あきれている。
金融コングロマリットの終焉
本の内容を紹介しすぎてしまうと、今後の読者の読書の楽しみを奪うので、藤沢氏の日本国債への見解、欧州経済、米国経済に関する見通しなどについては、投資家の関心の強いテーマだと思うが触れないことにしよう。ちなみに、筆者は、日本国債と欧州経済に関しては同意見、米国経済に関しては藤沢氏よりも幾分楽観的だ。
本書「外資系金融の終わり」で、著者は、「大きくて潰せない」金融コングロマリットを強く批判している。
G-SIFIs(国際金融システム上重要な金融機関)に代表される巨大金融機関は、預金のお金を使ってリスクを取り、自らの顧客と同様の仕事(ポジション・トレード)を収益源にする利益相反を抱えながら、経営危機に陥ると政府に救済される、巨大なモラルハザードの塊のような存在になっている。
藤沢氏は、投資銀行(といっても単なる証券会社だが)、特に欧州のユニバーサルバンク的な何でもありの金融機関を、リスクを取った投資、売買の仲介、顧客資産の運用、調査、預金と単純な融資(伝統的金融業務)といった機能別に解体してこれらの業務を一体に組み合わせた時に起こる利益相反の弊害をなくすべきだと主張し、さらに、いざというときには政府が助けなければならないようなサイズの金融機関は大きすぎるのだという。こうしたメガ金融分割論は、経済学的な議論としてはオーソドックスなものだが、現実は、逆方向に向かっている(それで得する人間がいるからだ)。
おそらくは、こうした仕組みのメリットを少なからず得ていて、その制御の難しさを当事者として実感している筈の著者の主張なので説得力がある。
また、著者は、潰せない大きさの金融機関が、金融を規制して権限を持ちたい金融監督当局にとっては好都合で、金融コングロマリットと規制当局の人間が利害共同体となることによって、金融ビジネスに社会主義経済のような悪弊が生じることを指摘している。こうした金融機関が暗黙の公的なサポートをビジネスに使うことはフェアでないし、あれこれ規制する余地が出来ると、規制当局と金融機関との癒着が深化する。
また、このように「ずるい社会主義」の政府と、政府と癒着した業者のようになった外資を含む大手金融は、能力とやる気のある金融プレーヤーにとっては魅力的な職場ではなくなりつつあるという。この辺りの事情を指して、藤沢氏は、外資系金融機関に対して「終わり」といっているのだろう。事実、外資系の金融機関でも、著者がいう悪い意味での「日本化」が進んでいるようで、確かに、経済条件的に相対的にまだまだばかばかしいくらいに有利であるとしても、そんな職場なら、魅力は乏しい。著者が、ヘッジファンドの設立を準備しているというのも、もっともだ。
経済のロジックで普通に考えると、藤沢氏の主張は至極もっともだ。ただし、問題は、規制当局も含めて、この当たり前の方針を実現することに対して、金融界のロビー活動の力を上回ることが出来る強いインセンティブを持つ主体が、現実的に見当たらないことだ。
この帰結がどうなるかは、興味深い。世界は、同じ失敗を何度も経験しないと変われないのかも知れないし、失敗の経験くらいで変わるものではないのかも知れない。
少しツッコムとすれば…
良い本なので褒めたが、褒めてばかりいると、かえって嘘くさい。少し異論を唱えてみよう。
藤沢氏は、大投資銀行を、プロップ・トレーディング→ヘッジファンド、投資銀行部門→ブティック型投資銀行アドバイザー、調査部→独立系リサーチハウスのように、機能別に解体するといいと述べ、インターネットの発達で個人がローコストな情報発信の手段を持ったように、能力のある金融ビジネス人材が独立して会社を営むような社会の方向性に期待をかけているようだ。そして、ご本人は、ヘッジファンドをやってみたいらしい。
ヘッジファンドは、潰せないくらい大きい投資銀行のプロップ・トレードのごとく、失敗した時に政府に救済されるということはないので(将来は分からないが)、その点がクリーンだし、条件に納得した顧客の資金を扱うという意味では「フェアな市場参加者」だが、「成功報酬」というコール・オプションを確保しておいて、自分でボラティリティーを操作(拡大方向だが)するというマッチ・ポンプ的なビジネスに、愚かにも「引っ掛かる」顧客を相手にするという点では、胸を張って出来る商売ではない。「悪だ!」と決めつけられるほど悪いビジネスではないが、藤沢氏のような知的で感情の豊かな人がこのビジネスで成功して満足できるものだろうか。
もちろん、満足できなければ、他のことをやればいいのだし、満足してもいいのだから、全くの「お節介」ではある。
お節介ついでに、もう一つ所謂「ツッコミ」を入れるなら、博士号を取ってから外資系金融に就職してざっと10年近く経っているという著者は、最大限に若いとしても30代半ばのご年齢だろう。しかも、いくらか露悪趣味のある彼は、自分が「下心」を持ちながら女性にディナーを奢る話を押さえきれずに本に書くわけだが、こういう人物は、世間的には完全に「オヤジ」の範疇なのであり、自分を指す主語が「僕」というのはいかがなものだろうか。
一人称の「僕」は、長年なじんだ藤沢氏のスタイルであり文体なのだろうが、本書のように内容的には格調の高い本を読むと、「私」、「筆者」、「著者」といった普通の一人称がいいと思う。本書は、そう思わせるだけの、骨太の論考だし、「藤沢数希」は堂々たる大人の(若くない)論客だ。





















































![[動画で解説]決算レポート:エヌビディア(「Blackwell」の量産進む)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3f6cf27f5c1aa7cadc8014bfefe4b67157893.jpg)
![[動画で解説]11/22「リスクオフで円高。週末はドル/円の下値探る動きか」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/498m/img_7e50191db2a159e1ee44be91523a403e47243.jpg)
![[動画で解説]株式市場の「強気の終焉」に備える~「買い遅れる恐れ」と「強気の罠」のはざまで~(土信田 雅之)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/9/498m/img_1979020be6c833ae6a0b21d1c7955a1670673.jpg)
![[動画で解説]【小林亮平さん/BANK ACADEMY】「金の盾」がほしい!投資の楽しさを広めたい【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/a/498m/img_6a4fc3c2314e5a1c161010e5c1b6b72549457.jpg)




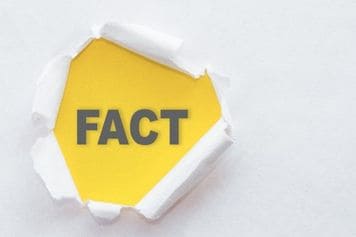









































![[動画で解説]決算レポート:エヌビディア(「Blackwell」の量産進む)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/160m/img_3f6cf27f5c1aa7cadc8014bfefe4b67157893.jpg)





