年金運用の世界でよく聞く言葉に、「マネージャー・ストラクチャー」という言葉がある。運用者の選択から資金配分、管理の仕組みなどを総称する概念で、運用のプロが外部の複数プロを使う方法を指す。
この考え方を簡単に振り返ると共に、考え方の中に、個人の運用に応用できる点はないかを検討してみよう。
全体のリスクと全体のコスト
マネージャー・ストラクチャーで大事なポイントを一つだけ挙げるとすると、「全体をコントロールする」ということになるだろう。たとえば、10社の運用会社を使って運用する場合、資金の委託者にとって問題なのは、当たり前だが、10社を合計したポートフォリオがどうなっているかだ。このリスクの大きさと、リスクの方向性が管理できないとすると大きな問題だ。特に年金基金のような主体は、第三者から預かったお金を運用するので、運用の内容に関する説明責任を負うから、この点が決定的に重要だ。
欧米でも、日本でもそうだったが、企業年金や公的年金の運用では、当初バランス型の運用が多く採用され、その後、バランス型の採用が減って、個々の資産分類毎に運用内容を指定して運用を任せる「特化型」と呼ばれる運用委託形態が主流になった。
複数のバランス運用を抱えていると、たとえば日本株への資産配分が幾らあるか、という状況の把握が容易でないし、個々の運用会社が資産配分を動かすと、日本株なら日本株といった資産への配分が、多くなりすぎたり、少なくなりすぎたりする。
また、採用した運用機関のA社が日本株を買い増しして、B社が逆に配分を減らしたというような場合、同一資産の買いと売りが委託資産の中で発生する。この場合、運用の委託者にとっての効果はゼロであるが、コストは確実にかかっている。この「相殺的売買」の問題も、バランス型の運用の委託を避ける理由になった。
加えて、バランス型の運用者が強調するマーケット・タイミングの能力(素人向けの商品だと「難しい資産配分はプロにお任せ下さい」というようなセールストークになる)が継続的に発揮されることが稀で、ほとんど信用を失ったことも、バランス運用離れの要因となった。
投資信託業界を見ると、一昨年くらいから、「資産分散型」などと言い換えて、バランス型のファンドを売っている。銀行や郵便局など投信の販売チャネルが多様化して、運用に不慣れな顧客が増えたことや、こうした販売チャネルで特定の資産に集中投資して大きく負ける可能性がある商品よりも、大負けが少ないバランス型の商品が好まれたというような事情があるようだ。
しかし、個人の資産運用の場合、一つのファンドに資産を集中することは稀だろうから、初期の年金基金がバランスファンドに投資して起こったような問題が、同様に起こることになる。また、たとえば株式50%、債券50%のファンドに投資することを考える場合、
株式のファンドを50%買い、債券ないし債券ファンドを50%買うといった、実質的に同じポートフォリオを個別に投資して作る方が、コスト(信託報酬など)が明らかに安いといったアービトラージ(裁定)が可能な場合がほとんどだ。
もちろん、バランスファンドを複数持つと、自分の運用資産内で相殺的な売買が起こる可能性もある。
加えて、確定拠出年金の場合、バランスファンドに投資すると、運用益への課税を繰り越すことができるメリットが十分に使えないという問題もある。ライフサイクル・ファンドなどと称して、確定拠出年金の運用選択肢にバランスファンドをラインナップする確定拠出年金の運営管理機関があるが、こうした会社の商品企画担当者は、目新しい商品(といっても海外の真似で、名前の響きがいいだけだが)を出すことに気を取られていて、確定拠出年金の趣旨を分かっていないのだといえる。
マネージャー・ストラクチャーの常識から個人の資産運用に応用できる教訓の第一は、「バランスファンドは買うな」だ。
スタイル区分が出てきた背景
ところで、リスクに偏りが生じたり、相殺的な売買が生じたりという問題は、アセットアロケーション(資産配分)の次元でだけで生じる訳ではない。
国内株式や外国株式など個々の資産クラスの中でもアクティブ運用を行う運用者を複数使う場合には、ポートフォリオのアクティブ・リスク(ベンチマークからずれるリスク)の大きさや内容が思うようにコントロールできない場合が出てくるし、同一銘柄を一方で買い、他方で売る、といった相殺的売買は頻繁に起こる問題だ。
そもそもアクティブ運用を採用しないか、採用するとしても一社しか採用しないなら、こうした問題は明らかに避けられる。しかし、大規模な基金の場合、複数のアクティブ運用会社を採用することが一般的だ。
やや脇道に逸れるが、世の中のアクティブ運用を見ると平均的にそれほど上手く行っている訳ではないし、事前にどの運用者が優秀であるかを見分けることはできない。こうした状況なのに、年金基金のような機関投資家は、どうしてパッシブ運用よりもマネジメント・フィー(運用手数料)が高いアクティブ運用の運用機関を、しかも複数採用したがるのだろうか。理由は複数あるだろう。一つには複数の運用会社と接触することで情報が欲しい(単なる話し相手かも知れないが)ということだろうし、多少はアクティブ運用に夢を持っているということでもあろうし、アクティブ運用を使わない場合に仕事が単純になり自分達の存在意義が乏しくなるということもあるだろう。年金加入者から見ると、年金基金と運用機関(加えて、年金コンサルタント)はグルになって自分達の仕事を作っているといえなくもない。逆に、多少余裕を持って眺めるとすると、アクティブ運用を使わないとなると、年金基金の仕事は今よりもずっとツマラナイかも知れない。どのみち人間のやることには無駄がつきものだから、無駄があまりに大きくならない範囲であれば許してもいいような気もする。
しかし、特に株式運用の世界では、リスクの偏りが問題になる場合が多い。そこで開発されたのが「スタイル(運用)」という概念だ。典型的には、一定の条件付けを行って(たとえば投資銘柄の候補群を分けて)、バリュー(割安株投資)とグロース(成長株投資)、さらにスモール(小型株)といった「運用スタイル」のカテゴリーを作り、スタイル毎に資金を配分して、その中で運用会社を選ぶという方法だ。
こうすると確かに、大きなアクティブリスクは取りにくくなるが、大きなアクティブリターンを取ることも難しくなるので、こうまでしてアクティブ運用の運用者を使う必要があるのか、という感じがしなくもない。
個人の運用に関する教訓をまとめるとすれば、「アクティブ運用は使わないか、使っても一社だけ」ということになるだろうか。個人的には、アクティブ運用は自分でやる、というのが一番楽しいように思うが、結果的にそれがいいとは限らないので、強くはお勧めしない(ネット証券にとって都合のいい話なので、気分的にお勧めしにくいということもある)。「楽しい」と思う人が、リスクの大きさを知った上で(単に概念的にではなく、数量的に、ということだが)自分でアクティブ運用を行うのであれば、それが理想的だ。
複数の情報の総合
以上は、マネージャー・ストラクチャーにあって初歩的に解決しなければならない問題だ。より積極的な意味では、(1)複数の運用会社の持つ情報を有効に使いたいし、(2)運用会社の組み合わせを適切に行うことで余計な(意図しない)リスクを抑えたい。
このためには、どうしたらいいのだろうか。
一つの考え方は、アクティブ運用に関して信頼度のより高い運用者により大きな金額の資金の運用を任せるというものだが、この場合、他の運用会社がどのように選ばれるかによって、個々に選ばれる運用会社がポートフォリオ全体に対してもたらすリスクの効果が変わってしまう。
理論的な正解は、個々の銘柄の期待リターンに関して信頼度の重みを付けて加重平均を計算して、情報を期待リターンの形に総合して、ポートフォリオ全体を最適化計算して構築するというものだ。
この観点から言うと、かつて野村アセットマネジメントが1兆円以上の資金を集めて話題になった「日本株戦略ファンド」のように、一社の中なのに資金をスタイル別に区切るような運用は、明らかに「最適」ではない、ということだ。
しかし、現実に運用者が運用の際に使っている期待リターンのデータをくれる訳ではない。実際には、個々の銘柄の期待リターンを明瞭に意識していない運用者が多いかも知れない。一つの工夫としては、運用者にある程度の金額の運用を任せて、彼(彼女)が作ったポートフォリオから個々の銘柄の期待リターンを逆算して、これを計算に使用するという方法がある。
たとえば、運用会社A社、B社、C社、D社を使う場合、これらにある程度の金額を運用させて、委託者自らが調整ファンドEを持って、このポートフォリオEが、期待リターンを逆算して作ったポートフォリオT(運用金額全体)から、A+B+C+Dを差し引いたポートフォリオに等しくなるように全体を構成するというようなことが理屈上は可能だ。
ただ、ここまでできる委託者は、すでに個々の運用会社の能力を超えているのではないか、それでも個々の運用会社を使う意味はあるのだろうか、という素朴な疑問が湧いてくる。
この問題を敢えて個人の資産運用に適用するとするなら、運用アイデア別に資金を分けるのではなくて、複数のアイデアを期待リターンの形で総合して、全体を最適化したポートフォリオを作るべきだということになる。「アクティブ運用の資金は区分するな」が教訓ということになる。
本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料の情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。




















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)
![[動画で解説]植田総裁・名古屋講演のメッセージ~政府・日銀にとって御誂え向きの2024年7-9月期GDP~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3fb371897205e7696fbfa011f2bc1cb7104479.jpg)
![[動画で解説]「エンゲル係数」上昇の背景に世界分断あり](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d62961de68f1df741a9eba8339b2f7369057.jpg)




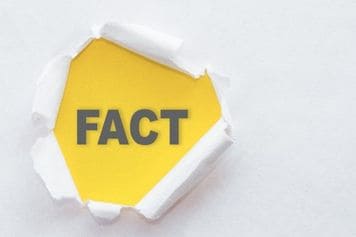












































![[動画で解説]11/22「リスクオフで円高。週末はドル/円の下値探る動きか」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/160m/img_7e50191db2a159e1ee44be91523a403e47243.jpg)

![[動画で解説]株式市場の「強気の終焉」に備える~「買い遅れる恐れ」と「強気の罠」のはざまで~(土信田 雅之)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/9/160m/img_1979020be6c833ae6a0b21d1c7955a1670673.jpg)



