株は「安く買って高く売る」のが常識だが・・・
株式投資の常識の1つといえば、「株は安く買って高く売る」こと。当たり前すぎて今さら説明する必要性もないほどです。
株だけでなく、利益を得るためには、安く買ったものをできるだけ高く売る、これは世の常識です。
ところが株式投資ではもう1つの常識が存在します。それが「高く買って安く売る」ことです。
「えっ?」と思われる方も多いと思いますが、この2つの常識、全く真逆のことを言っているようで、実は両方とも正解なのです。
投資格言の1つに「株は新高値を買い、新安値を売れ」というものがあります。「高く買って安く売る」とはまさにこのことです。
この格言は、筆者も拙著や本コラムでも繰り返し申し上げているように、「株価のトレンドに逆らわず、トレンドに沿った売買をするべきである」ことを表しています。
ではなぜ新高値を買うのか、それは、高値を更新してきた銘柄というのは、株価が上昇トレンドにあることが明確だからです。さらに、高値更新銘柄はそれまでとは異なる新たな上昇ステージに入っている可能性が大です。
新高値更新銘柄はすでに「2段上げ」に突入して株価上昇中
株価の上昇パターンとして、よく「3段上げ」という表現が使われます。これは、底値から天井をつけるまでの株価の動きとして「底値から上昇(1段上げ)⇒しばらく調整⇒再び上昇して1段上げの高値を超える(2段上げ)⇒しばらく調整⇒再び上昇して2段上げの高値を超える(3段上げ)」という動きになることが多いためです。
例えば、昨年11月中旬以降のアベノミクス相場では、多くの銘柄が大きく上昇した後、4~5月に高値をつけました。これがいわば「1段上げ」です。
多くの銘柄は現時点でもそのときの高値を超えられずにいますし、日経平均株価やTOPIXといった株価指数も同様です。その一方で、強い銘柄はすでに4~5月高値を超えて上昇しています。これらの銘柄は1段上げ後の調整を短期間で済ませ、2段上げのステージに入っていて、4~5月高値を超えたあとも順調に上値を伸ばしています。
2段上げのサインは、1段上げ時の高値を超えること。したがって、1段上げ時の高値を超えて新高値となったときが「買いタイミング」となるのです。
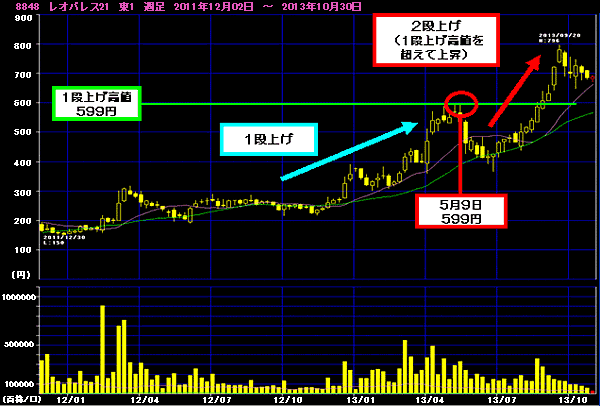
高値掴みを避けるために「安値買い」と「新高値買い」の二刀流で
ただ、個人投資家の多くは、新高値を買うことがなかなかできないといわれています。株を安く買うのは、タイミングをうまく見計らってさえいればそれほど難しくはないのですが、高いところで買うのは心理的抵抗が大いにあります。筆者も高く買うより安く買う方がはるかに簡単と感じます。
確かに、新高値買いを続けていると、どうしても高値掴みをしてしまうリスクがつきまといます。株は永遠に上げ続けるわけではないからです。特に、上昇を初めてからの期間がすでに長期間におよんでいて、株価も底値から大きく上昇している銘柄は、いつ反転下落に転じてもおかしくありません。また、「3段上げ」の上昇が必ず生じるわけではなく、新高値を更新したと思ったらすぐに急落してしまうこともあります。
そこで、筆者が実践しているのが「安値買い」と「新高値買い」の二刀流です。
まず、投資候補としている銘柄の株価が日足チャートで上昇トレンドに転じたら買います。これは「安値買い」です。その上で、順調に株価が上昇して新高値を更新してきた段階で買い増しを行います。
この二刀流を行うことで、仮に「新高値買い」が高値掴みになり、損切りの憂き目にあってしまったとしても、「安値買い」の含み益で対応することが可能となります。
損切りは「新安値」に達する前に済ませておくべき
一方、売りの方ですが、「新安値更新」は、株価の下降トレンドが続いていることを表します。ただし、「新安値を売る」というのは、持ち株を売るタイミングというよりは、新規に空売りを仕掛けるタイミングとしてとらえる方がよいでしょう。
新安値を更新するときには、すでに株価が下降トレンドに入ってからかなり時間が経過していますし、株価の下落もかなり進んでいます。
通常、新安値を更新するよりかなり以前の、もっと株価が高い段階で、株価のトレンドが下降トレンド入りしますから、その時点で持ち株の売却や損切りを実行するというのが原則です。
ただし、月足ベースで過去の安値を割り込んだような場合は、損切りを躊躇して持ち続けてしまった持ち株があるときや、十分に含み益が乗っているため保有を続けている銘柄のポジションを減らす際の「最後の逃げ場」として非常に重要となります。月足ベースで直近の安値を更新した後は、思わぬ安値まで沈むことが多々あるからです。
先日のコラムでも例示した鉄建(1815)の月足のチャートをご覧ください。1997年以降の急落の際、直近の安値である656円を割り込んだ時点で売却、損切りしていなければ、その後のさらなる下落で手も足も出なくなってしまったのです。
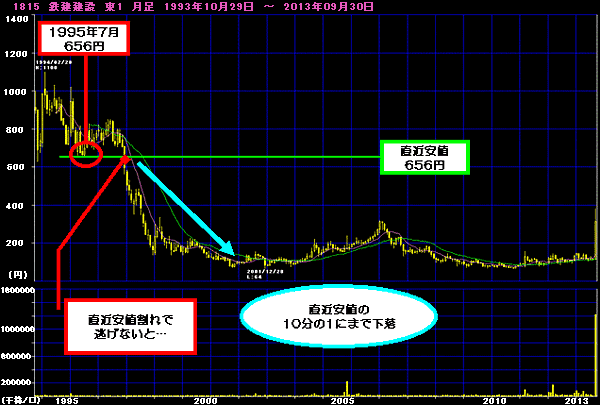




















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)
![[動画で解説]植田総裁・名古屋講演のメッセージ~政府・日銀にとって御誂え向きの2024年7-9月期GDP~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3fb371897205e7696fbfa011f2bc1cb7104479.jpg)
![[動画で解説]「エンゲル係数」上昇の背景に世界分断あり](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d62961de68f1df741a9eba8339b2f7369057.jpg)





















































