ベンチマークの三つの機能
はじめに、「大事なことが三つある」と宣言して話し始めるのは、コンサルタントなどが、よくプレゼンテーションやスピーチで使う手だ。ある使い手によると、「そう言って話を始めてから、ポイントは話ながら考えればいいし、仮に、AとBの二つしか思いつかなければ『AとBとのバランスが大切です』と言って三つ目を作ればいいし、もちろん、四つ目を思いついたら付け加えてもいい」ということだった。「三つ」という数字の具体性が注意を惹くようだ。そういえば、新刊の「スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン」(カーマイン・ガロ著、井口耕二訳、日経BP刊)にも、ポイントを三つに絞ると印象に残りやすいことが強調されていた。
冒頭から余談が長くなってしまったが、ベンチマークには機能が三つある。「情報の縮約」、「リスク測定の基点」、「パフォーマンス評価の比較相手」の三つだ。この場合は、あらかじめ「三つ」ということが分かっているので、安心して欲しい。
機能その一、「情報の縮約」
情報の縮約機能とは、たとえば、日本の株式で運用することのリスクの大きさや、どういった時にリターンが高い(低い)のかを知りたい場合、たとえばTOPIX(東証株価指数)をベンチマークにして、これらの性質を調べることができる。「日本株で運用するポートフォリオ」の標準像をベンチマークで代表させて、その振る舞いを調べることで運用に関する意思決定がやりやすくなるし、その後に続くはずの資産配分(アセット・アロケーション)の作業もやりやすくなる。
年金基金のようなプロの投資家であれば、運用しようと思う内容に合わせたベンチマークを目的に応じてその都度自分で作ることも考えられるが(「カスタマイズド・ベンチマーク」と呼ばれる)、過去にさかのぼって正確なデータを作るのに手間が掛かる。また、年金基金の場合だと、加入者に向けて運用計画の説明をしなければならないので、一般に知られている指数(インデックス)で代表されるポートフォリオをベンチマークとすることが多い。つまり、ベンチマークは、運用に関するコミュニケーションの際にも情報を縮約の機能を発揮することがあるといえる。
後述のように、個人投資家の場合は、インデックス・ファンドに投資することが合理的だ。そうした前提で考えると、そのベンチマークをターゲットにするインデックス・ファンドを過去に持っていた場合に、どんなリターンとリスクが現れていたのか、という見方でベンチマークのリターンの過去の振る舞いを見ることができる。
機能その二、「リスク測定の基点」
資産配分ができあがって、たとえば日本株の運用を始める場合、運用しているポートフォリオとベンチマークがどの程度異なっているかを把握しておく必要がある。実際に運用されるポートフォリオとベンチマークの性質が著しく異なると、運用全体のリスクの大きさやバランスが資産配分計画を作った際のものと大きく違ってしまうかも知れない。
年金基金が投資顧問会社に運用を任せる際には、ベンチマークを指定すると共に、ベンチマークに対してどのような大きさ及び傾向のリスクを取るのかを、あらかじめ合意しておくことが一般的だ。そうでないと、運用を任せる側は、委託した資金がどんな性質と大きさのリスクを取って運用されるのかが分からないし、運用を任された側も具体的なベンチマークがないと、自分が運用上取っている実質的なりスクを測ることができない。
個人投資家が投資信託を使って運用するケースでも、自分が投資しようとする投信が、ベンチマークに対してどのくらいの大きさのどんな性質のリスクを取るのかが分からないと、運用資金全体のリスクの大きさと内容をコントロールすることができない。
実際に運用されるポートフォリオとベンチマークとの相対的なリスクのことを「アクティブ・リスク」と呼ぶが、個人投資家が自分の投資している投資信託のアクティブ・リスクを把握することは簡単ではない。
現実的には、アクティブ・リスクの影響があまり大きくない場合もある。また、そもそもベンチマークのリスク推定を正確に行うことが不可能な場合もある。従って、アクティブ・ファンドを利用しても計画と実行の誤差に大差がない場合もあるとはいえる。
しかし、厳密には、「アクティブ・リスク」は運用計画上、特に資産配分を考える際には余計なリスクだし、その把握とコントロールを行うことが難しい。素人はベンチマークと同じ株価指数に連動するインデックス・ファンド以外には投資しない方がいい、と言い切ってしまう方が、アドバイスとしては良心的かも知れない。
また、プロの運用委託者の場合も、複数のアクティブ・ファンドのアクティブ・リスクを適切に管理することは簡単ではないし、仮に可能であったとしても、相当の手間とコストを要する。加えて、ベンチマークに勝つアクティブ・ファンドを事前に識別することができないのだから、プロの場合もインデックス・ファンドを使うことが自然なのだ。
現実には、年金基金などの運用では、パッシブ運用(現実にはインデックス・ファンドによる運用となる)を7-8割利用して、残りをアクティブ・ファンドに委託する「コア・サテライト型」と言われる運用スタイルを使うことが多いが、これは、そもそも優秀なアクティブ・ファンドを選択することが難しく、アクティブ・リスクのコントロールが容易でない現実に対して、それらの困難の規模を小さくするために行っている苦肉の策だ。
そうまでして、アクティブ・ファンドを使うのは、率直と皮肉の両方が混じるが、はっきり指摘すると、彼らが自分達の仕事を作るためだ。一般投資家がわざわざ真似するのは愚かな行為だ。
機能その三、「パフォーマンス評価の比較相手」
そして、ベンチマークの三番目の機能は、パフォーマンス評価の比較相手だ。一般的には、この機能が一番有名だし、分かりやすい。
たとえば、日本株のポートフォリオが10%のリターン(投資収益率)であった場合に、株価全体が大きく上げた時の運用なのか、あるいは株価が下がっていた時の運用なのかで、運用スキルに対する評価は異なっていて当然だ。
これは、運用者のスキルの評価として実感として当然だということの他に、ベンチマークのリターンで代表される日本株市場全体の平均的なリターンが運用者のコントロールの範囲外であって、運用の委託者(年金基金であったり、投信を買う個人投資家であったりする)の判断の責任範囲であることを同時に意味している。
つまり、ベンチマークを定めることによって、運用結果のどこからどこまでが誰の責任であるかの境目が確定する。ベンチマークは、運用全体の流れの中で、運用意思決定の責任を区分する役割も果たしている。
計画・実行・評価の一貫性を保つ
さて、ベンチマークの三つの機能を見ると、調査・計画の段階から、運用の実行、そして運用の評価の段階まで一つのベンチマークを継続して使うことで、運用の計画・実行・評価の一貫性が保たれる事が分かる。
たとえば、資産配分の段階と運用評価の段階とで異なるベンチマークを使うと、運用者は評価に使われるベンチマークを意識することが自然なので、資産配分計画が想定した運用と実際に行われる運用の内容が異なるものになる公算が大きくなるし、運用結果の責任についても、資産配分計画段階に原因があったのか、運用者のアクティブ運用に原因があったのかが曖昧になってしまう。
また、運用におけるベンチマークの機能が理解できると、ベンチマークそのものの良し悪しを評価することができるようになる。個人投資家の場合には、どのインデックスに連動することを目指すインデックス・ファンドに投資したらいいのかという問題に答えを与える手掛かりになる。
詳しくは、別の機会に詳述するが、筆者の結論の一部を簡単に述べるなら、ベンチマークを評価する際に重要なベンチマークの性質は、「透明性」、「再現性」、「規範性」の三つだ(再び、三つになる!)。また、日本株のベンチマークとしては、日経平均よりもTOPIXの方が優れたベンチマークである。




















































![[動画で解説]決算レポート:エヌビディア(「Blackwell」の量産進む)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3f6cf27f5c1aa7cadc8014bfefe4b67157893.jpg)
![[動画で解説]11/22「リスクオフで円高。週末はドル/円の下値探る動きか」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/498m/img_7e50191db2a159e1ee44be91523a403e47243.jpg)
![[動画で解説]株式市場の「強気の終焉」に備える~「買い遅れる恐れ」と「強気の罠」のはざまで~(土信田 雅之)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/9/498m/img_1979020be6c833ae6a0b21d1c7955a1670673.jpg)
![[動画で解説]【小林亮平さん/BANK ACADEMY】「金の盾」がほしい!投資の楽しさを広めたい【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/a/498m/img_6a4fc3c2314e5a1c161010e5c1b6b72549457.jpg)




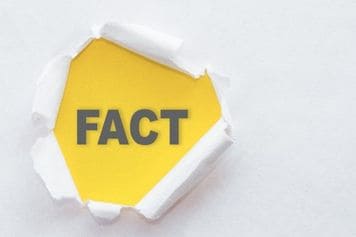









































![[動画で解説]決算レポート:エヌビディア(「Blackwell」の量産進む)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/160m/img_3f6cf27f5c1aa7cadc8014bfefe4b67157893.jpg)


![[動画で解説]11/22「リスクオフで円高。週末はドル/円の下値探る動きか」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/160m/img_7e50191db2a159e1ee44be91523a403e47243.jpg)




