知っておくべき米ドル建投資2:外貨建て資産の評価を正しく理解する
外貨建て資産への投資で代表的なものは、投資信託、米国株式、米ドル建て債券などが挙げられます。ここで注意していただきたいことは「外貨建て(例:米ドル)」「資産(例:株式、債券)」は為替とその投資対象となる資産の影響を受けています。
保有資産の残高を見ると、日本円での評価が記載されているため、きちんとそれぞれ為替と資産がどう動いたのか確認しなければ分かりません。意外かもしれませんが、お客さまと保有資産状況を確認すると、評価額だけを気にする方が多くいます。
しかし、投資で資産を増やすことを目的としているのですから、当初の運用資産または年初からいくら増減しているかなど一定期間の評価を確認する必要があります。また、保有商品の評価損益は基本的に時価評価(売買した際の譲渡所得の損益)、株式の配当(配当所得)・債券の利息(利子所得)などは含まれていません。
投資信託なら月次レポートで損益の内容を確認し、米国株式なら為替損益と株価の損益に配当、米ドル建て債券なら為替損益と債券価格(ただし満期には100円に戻るのが基本)に利息を把握しておくことが必要です。
慣れるまでは大変かもしれませんが、確認する項目は多くはないので一つずつ確認してみましょう。なお、年初に発行される「年間取引報告書」を見ると特定口座での年間取引損益を知ることができます。一般口座やNISAでの取引はまた別で確認しましょう。
知っておくべき米ドル建投資3: 投資だけでなく通貨分散の意味も考える
最近円安になることによって、私たちの生活にかかる費用も増加してきています。日本のインフレ率は円安が進んだ2022年以降明らかに上昇しており、2022年は2.50%、2023年は3.27%、2024年は2.24%(IMF[国際通貨基金]の推計値)となっています。
もちろん円安だけがインフレの原因ではありませんが、私たちの生活に密接な原油価格を代表とした化石燃料の価格上昇は光熱費に影響があります。
また、住居などに利用する資材費の上昇によって賃料や管理費・修繕積立金の増加、輸入する食料品や肥料の値上がりで食費が上がるなど、円安の影響を受けて価格転嫁が進んでいます。企業努力によって抑えられている部分もありますが、それには限界があります。
以前は外貨建て資産への投資は為替の水準を見て売買する方も多くいらっしゃいましたが、2022年に急激な円安が起きてからはこうした理由から米ドル建て資産を組入れするという方が増えてきました。
今や日本円という通貨だけで資産を保有することも一つのリスクとなりました。デフレの時代は現金のままで持つという選択肢もありますが、これからは私たちの生活の軸となる日本円と、世界の主軸通貨である米ドルの、通貨分散をすることが大切な資産を守る手段の一つとなってきています。
外貨建て資産への理解は日本人の資産運用には必須
為替への理解を深めて、慌てずに投資を継続しよう
日本人が投資をするときに購入する商品の多くが外貨建て資産です。投資信託も日本円で売買しますが、上位にラインアップされる商品のほとんどが海外への投資です。
日興リサーチセンターによると、新NISAが始まった2024年1月にはNISA対象の投資信託で1兆円以上の資金が純流入しています。1兆円以上の純流入がどこまで続くかはまだ分かりませんが、積立投資がメインであることを考えると、どちらにせよ多額の資金で毎月円売りがされていて、日本人の日本円資産が米ドルを中心に外貨建て資産にかわっています。
米ドルの値動きはさまざまな理由で変動していきますが、投資としてはきちんと投資した商品の値動きを理解する必要があります。それに加えて資産の通貨を分散して保有するという考え方も組み合わせて大切な資産を増やし、守っていきましょう。
■著者・西崎努氏の著書『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム刊)、『老後資産の一番安全な運用方法 シニア投資入門』(アスコム刊)が大好評発売中です!
【要チェック】
楽天証券「トウシルの公式YouTubeチャンネル」では、本連載「やってはいけない資産形成」のコラムを動画で視聴できます。
また、リーファス社の公式YouTubeチャンネル『ニーサ教授のお金と投資の実践講座』では、同コラムの他にも動画でお金と投資の知識を学ぶことができます。






















































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

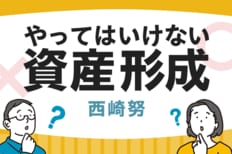











































![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)
![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)
![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)





