授業への招待
筆者は、獨協大学で週に二コマ「金融資産運用論」と題する授業を持っている。そのうちの一方は、バートン・マルキールの「ウォール街のランダムウォーカー」(井手正介訳、日本経済新聞社)を半年掛けて読む内容だが、2014年度の秋学期は進行が予想以上に順調で授業日数が1日余った。そこで、第二の課題図書として指定しておいたケインズの「一般理論」を取り上げることにした。
もちろん、「一般理論」の全体を解説するような無謀なことはしない。投資と運用に深く関わり、ケインズの株式市場に対する見方が表れている第12章のみを詳しく解説することにした。
ケインズの一般理論については、本連載でも第12章だけ読むことを推奨し、12章の内容について紹介したことがあるが、同書については、山形浩生氏が2012年に新訳(「雇用、利子、お金の一般理論」、講談社学術文庫)を出されたことでもあり、授業で話した内容に沿って、あらためてご紹介しよう。
「一般理論」の翻訳は、既に何種類もあるが、内容が「頭に入る」という点で、山形訳が抜群である。気さくな読みやすい文体でもあるので、是非、山形訳を読んでみて頂きたい。学生時代などに別の翻訳を読んで歯が立たなかった方も、案外スッキリ理解出来るかも知れない。
以下、12枚の図は、授業で使ったパワーポイントだ。予告無しの内容なので、学生は手もとに本を持っていない。内容の多くは、「雇用、利子、お金の一般理論」(山形浩生訳、講談社学術文庫)からの引用と、山崎による内容要約だ。
図の解説、補足をするスタイルで進めて行こう。ほぼ授業一回分(90分)で説明した内容だ。
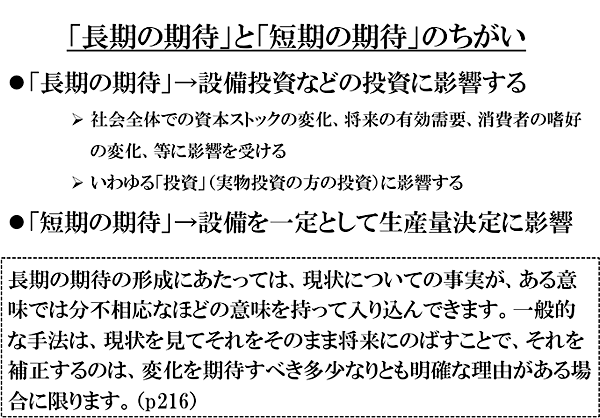
(図1)
「一般理論」では、12章の前に既にかの有名な有効需要の原理は提示されており、有効需要の決定には「投資」が重要な役割を果たすことが既に読者には理解されている。
そこで、設備投資のような長期の(実物)投資の採算見込みと金利との関係が重要になるが、前者に決定的な影響を与えるものとして「長期の期待」について解明する必要が生じる。
ここで、長期の期待は短期の期待と区別される。短期の期待は、典型的には設備が一定の下で製品の需要を予測してどれだけ製品を作るかといった意思決定の背後にある予想であり、これに対して、長期の期待とは、設備投資の採算が合うか合わないかに関わるような、長期的な見通しのことを指す。
これは、将来の社会全体の資本設備の状態や、将来の有効需要(≒景気)、諸費者の嗜好変化、将来の賃金など、多くの要因から影響を受ける。想像しただけで、難しそうだ。
人々が長期の期待を形成する一般的な方法は、現在の状況を将来に延長することだとケインズは言う。これに、変化を期待すべき多少なりとも明確な理由がある場合に修正が施されるのだ、とケインズは考える。
随分割り切った説明だが、概ね現実に合っているように思う。現代のアナリストやエコノミストの分析や予測も概ねこうしたものだ。もっとも、彼らは(「私も」だが)、変化の理由をしばしば自分の想像だけからでっち上げる。
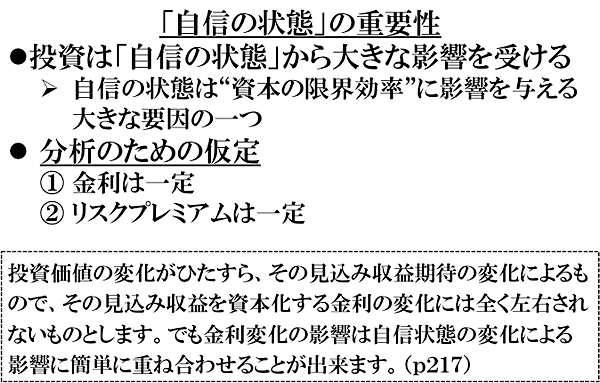
(図2)
長期の期待に基づく投資の採算計算は、経済主体が自分自身のベストな予測に対して持つ「自信の状態」から大きな影響を受ける。
同じ予想に対しても、自信がある場合とない場合では、投資の可否を判断する採算計算は大きく変化する。ある製造業企業の経営者が「製品への需要が3年で2倍になるだろう」と予想しても、その予想への自信の程度に、設備投資をするか否かの決定は大いに影響を受けるだろう。
以下、ケインズは自信の変化を分析するに当たり、与件の変化は企業の利益の獲得見込みの変化だけだとして、将来の配当や利益を割り引く際に使われる金利とリスク・プレミアムの変化は取りあえず考えないことにする。
しかし、金利の変化の影響を考えたい場合は、それを自信の状態の変化に対応させたらいいだけなので、この仮定は分析の本質には影響しない。本章の論考の目的は、予想の形成のされ方の解明にあるので、変化の要素を将来の収益変化に限定して考えるのが分かりやすい。
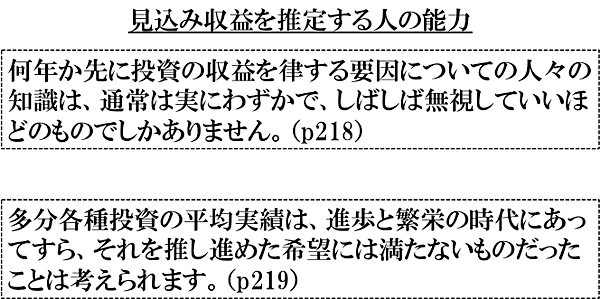
(図3)
ケインズは、建前を離れて本音でいうなら、人間が、事業の将来収益を予測する能力は情けないくらい非力なものだという。残念だが、現実は、全くその通りだろう。既存の企業の業績でさえ、3期以上先の予想など雲をつかむようなものだ。
加えて、投資一般が、全体としては、期待ほど儲かるものではないとも言っている。この後に、投資の決定要因としてアニマルスピリットを挙げているが、ケインズは、事業への投資というものが、平均的にはリスクや負担に比して、あまり儲かるものであるように見えないことについて、半ば驚き、説明に苦慮しているようだ。
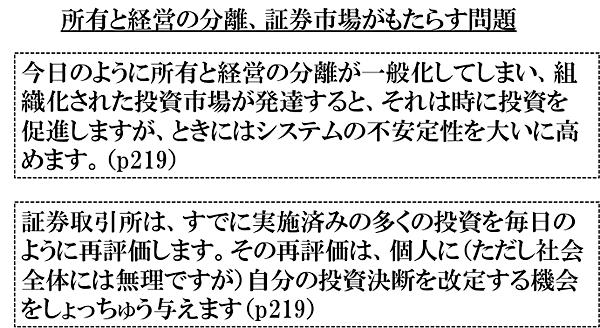
(図4)
本来の事業投資には長期の見通しに対する熟慮が必要であることに対して、資本が証券市場でもっぱら短期的な見通しに基づいて取引されることの弊害についてケインズは憂慮している。
資本市場が発達したことによって、投資が促進されるようになった面もあるが、資本市場の振る舞いがしばしば健全な投資(証券投資ではなくて、設備投資などのマクロ経済でいう「投資」だ)を混乱させることがある。
バブルが過剰投資を生んだり、バブル崩壊後に投資が過小になったりする現象に、株式市場が関わっていることは明らかだ。

(図5)
既存の企業の株価が、なぜ新規投資に影響するのかが説明されている。
ある企業と同内容の企業をその企業の取得費用(たとえば株式時価総額と考えよう)以上のコストを掛けて取得するのはバカバカしい。株価が安いときは、自分で事業に投資するよりは、既存企業の株式を買う方が得だ。
逆に、安い費用で作った企業が、株式市場で非常に高く評価される見込みがあれば、事業を興して実物投資をしようという気になる人が増えるだろう。たとえば、近年の経験で思い出すのは、1990年代後半のネット株バブルだ。当時はIPO(株式新規公開)での手っ取り早い大儲けを目指して、内外で多くの起業がなされた。
金融論を勉強した人は、設備の再取得価値と株式時価総額の比率である「トービンのq」の概念を思い出すといい。株価が投資に影響を与えるチャネルの一つが分かる。
株価は実物投資に影響を与える。それが、いいこともあれば、悪いこともある訳だが、株価の決定に関わっているのが「証券取引所で取引する連中」であることをケインズは心配している。
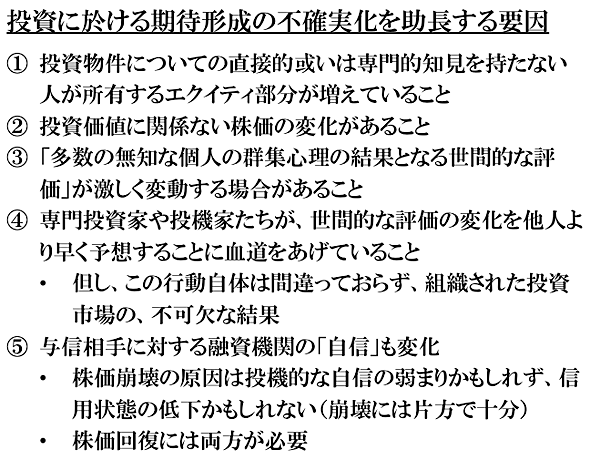
(図6)
ある企業の設備や事業の内容、持っている技術などについて、深い知識を持たない主体が企業の持ち主になる比率は、現在でも非常に大きい。
また、長期的な投資価値に関係ないはずの株価の変化についてケインズが苦々しげに指摘しているのは、アメリカの製氷会社の株価が夏の方が高い傾向がある、といった現象だ。ジンクスや金融論的に根拠の乏しいアノマリーで株を売り買いしている向きには、耳の痛い話かも知れない。また、2013年にノーベル経済学賞を取ったロバート・シラーの業績の一つには、株価の変動が、配当の変動から合理的に説明できる範囲を大きく超えていることの実証研究があった。
そして、株価は、無知な群衆の「世間的な評価」に大いに影響されて形成されるが、この「世間的な評価」なるものは、もともと「確信の強い根っこがない」(p223)ので、急変する事があり得る。
さらに、株式市場がお互いの短期的な予想を予想し合うようなゲームになっていることがある。この問題については、有名な美人投票の比喩が登場する。
①から④までは、主に株式を取引する人々に関わる問題だが、⑤に「信用」の問題が登場する。信用を与える相手に対して融資機関が自信を持てるかどうかは、実物投資にとっても証券投資にとっても重要な問題だ。
また、株価の崩壊には、市場参加者の自信と融資機関の自信の何れかの崩壊で足りるが、株価の回復には、両方の自信の回復が必要だという指摘には、自分自身が株式投資家であったケインズの、株式市場に対する深い理解を感じる。
バブルの株価は、投資家の自信の崩壊からはらはらと崩れ始めることがあるし、金融引き締めや信用取引への規制などが市場の過熱に終止符を打つこともある。
一方、バブル崩壊後の株価の回復には、金融緩和が不可欠であり、金融緩和が行き渡るためには、民間金融機関の「自信」が回復して与信が拡大するような状況になることが望ましい。そのために、金融機関の損失処理と自己資本の補填によるバランスシートの回復が必要であることは、日本のバブル崩壊後、及び金融危機後の経験が教える通りだ。
これらに加えて株価の回復には、投資家の自信回復が必要なこともその通りだろう。
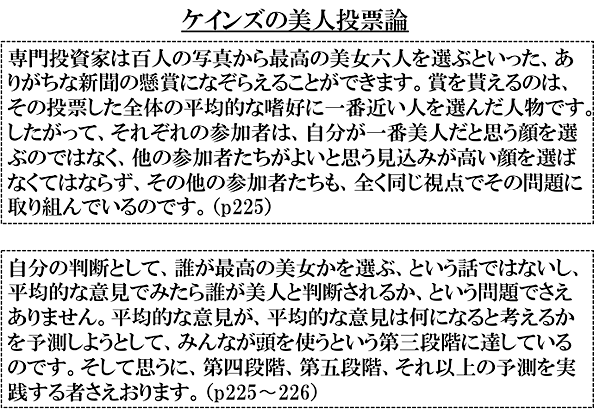
(図7)
有名な株式投資を美人投票に喩えた下りだ。「真の美人=良い長期的事業見通しのある株」、「他の参加者たちが美人だと思う美人=短期的な世評・人気が高まると予想される株」というくらいに置き換えて読むと、ケインズの言いたいことに近いのではないか。
投資家が真正面から受け取るなら、自分がいいと思う株に独りよがりで投資するのではなく、他人がいいと思う株かどうかが大事なのだ、というレッスンを読むことができる。この考えに対しては、人気の株か不人気の株かということよりも、その人気の「変化」が重要であることを指摘しておきたい。人気の美人株がもっと人気を集めるようになる可能性よりも、不人気な「不美人株」が少々改善することの方が、インパクトが大きい可能性は十分あるので、「株式投資は不美人投票だ」と考えておくくらいが丁度良いことが多い。
ケインズは、この(他人の)予想を予想するゲームが、他人の予想を予想している他人としての他人が形成する予想を予想する、といったさらに深い構造の「予想ゲーム」になりうることを付記している。クオンツ的な運用戦略を考える場合などの実感と一致する注釈だ。
一方、この章の文脈としては、ケインズは、株式投資がこうした美人投票的ゲームになることで、企業の長期的な事業見通しを真剣に評価するような行為からどんどん離れて行くことについて心配している。

(図8)
ケインズは資本市場の機能と影響に対してかなり悲観的だ。真の価値を見つけて投資しようとする投資家も、短期的な予想ゲームに血道を上げる投資家の余波を受けて、本来なら不要と思える追加的なリスクを負担しなければならない。この辺りの話は、後に、ローレンス・サマーズやアンドレイ・シュレイファーが研究した「ノイズ・トレーダー」の議論に通底しているように思われる。
正しい情報を持ったインフォームド・トレーダーが、正しい情報を持たずに市場に参加するノイズ・トレーダーの参入を知ってリスクの高まりを意識して投資を縮小する場合、結果的に、気にせずにリスクを取るノイズ・トレーダーの方がより多く富を増やす場合があり得る、といったストーリーだ。
まして、「社会的に有益な投資」を、株式市場を通じて実現するのは難しそうだと当時のケインズは考えたのだろう。
この部分に関して議論をするとすれば、「社会的に有益な投資」とは何で、誰がどうやって決めうるのか、という点が問題になるだろう。
株式市場の気まぐれな変動のリスクを吸収して長期的な価値に賭け続けるためには、余裕として大きな資金が必要だし、借金して投資してはいけない(信用取引もいけない!)とケインズは言っている。実際に熱心に株式取引をしていたケインズの実感がこもっている。
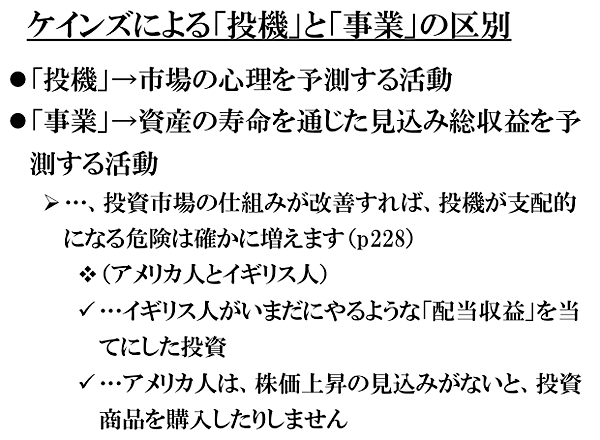
(図9)
ケインズは、短期的な心理予測ゲームを行うのが「投機」で、長期的な見通しの下で設備等の資本の収益を見積もる活動は「事業」だ、という区別を立てている。
筆者はゼロサムゲーム的に市場参加者同士の見通しの違いに賭けるリスクを取るのが「投機」(商品価格や外国為替のリスクは「投機のリスク」だ)、生産に参加する資本に資産を投じるリスクを取るのが「投資」(株式、不動産などの保有は投資)だ、という区別をすることが多いが、株式であっても短期の変動に賭けることに「投機」の要素が多く含まれることには大いに同意する。
ケインズの着眼と心配は、取引が容易に且つ低コストで成立する「流動性」の高い市場になるほど、「投機」の占める割合が高くなるのではないかという点にある。
当時のアメリカの「進んだ」(流動性の高い)市場にあって、取引がより投機的になっているようだと英・米の株式市場を比較している。
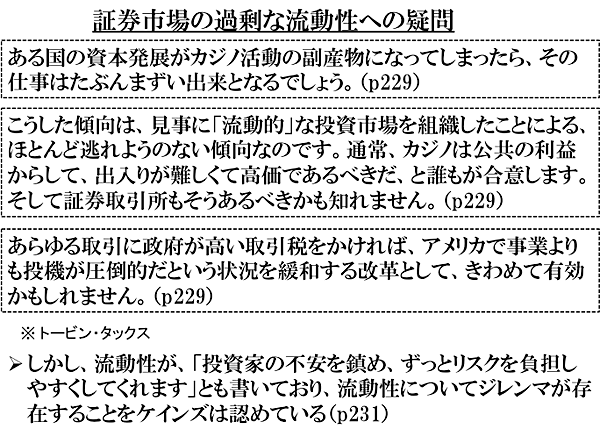
(図10)
市場がより流動的であることは、投機をよりやりやすくする。従って、流動性にある程度の歯止めをかけるといいのではないか、というのがケインズのここでの発想だ。
株式市場をカジノに喩えて、カジノは繁華街から遠い不便な場所にあり、コストが高いのが普通だと論じている辺りの説明がなかなか面白い(日本のカジノはどこに出来るのだろうか…?)。
内外の株式市場(特に取引所)は、高速取引業者にまで便宜を図って出来高を取り合う、ケインズから見ると「超流動化」した状態にある。例えばマイケル・ルイス「フラッシュ・ボーイズ」(渡会圭子訳、文藝春秋社)を読むと、高速取引業者の限りなくフロント・ランニングに近い胡散臭さと、彼らの利益が社会的に無意味なものであることが分かるが、現代の証券取引ビジネスは、ケインズの警告を無視して過剰に流動化し過ぎたのではないか。
少なくとも、多くの市場参加者に現実に取引可能な価格が見えて、投資判断が集まって株価に反映するような市場でなければ、株価の情報集約機能が有効に働かないように思われる。見かけ上の出来高で観察される流動性ではなく、取引に参加し、価格に反映する情報の量と質で、取引の仕組みの良し悪しを判断すべきだろう。
但し、筆者は、ケインズの提案のように取引税を課して取引頻度を落とすのではなく、取引のスピードを落として、多くの投資家にとって可視的に参加できるマーケットにすることが望ましいように思う。
ケインズの有力な後継者でノーベル経済学賞受賞者だった故ジェームス・トービンも市場が流動的にすぎると上手く行かないと考えていた。「摩擦のない道では自動車は走れない。アイスバーンに撒く砂のようなものが市場には必要なのだ」とトービンが話していたというエピソードを、故三木谷良一神戸大学名誉教授(当時)に生前伺った覚えがある。「それが、トービンタックスのアイデアの原型ですか」とお聞きしたところ、「そうです」と教えて頂いた。
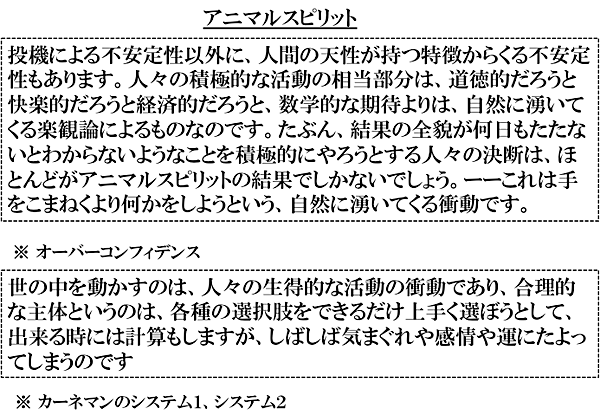
(図11)
さて、「一般理論」の文脈の本筋は、マクロ経済にあって投資(設備投資などの実物投資)がどう決定されるかだが、証券市場が投資を攪乱する効果の他に、そもそも投資が数学的な期待値の計算に基づいてなされるものであるよりは、しばしば人間の生得的な衝動に基づいて決定されるものであることにケインズは目配りする。
もともと世の中の事業投資がそれほど儲かるものではないのに、なぜかくも多くの投資が行われるのか、ケインズは不思議に思っていたのではないか。これを、「人間の生得的な活動の衝動」、「自然に湧いてくる楽観論」で説明するしかないと考えてそのまま本に書くところが、ケインズの誠実さであり潔さだ。
自然に湧いてくる楽観論には、行動経済学でよく言及される「オーバーコンフィデンス」(自信過剰)に近いものを感じる。人間には、ヤル気が必要なのだろう。
また、出来るときには計算もするが、しばしば気まぐれや感情や運に頼るというケインズがいう人間の意思決定のあり方は、ダニエル・カーネマンが「ファスト・アンド・スロー」で書いた、意思決定の「システム1」と「システム2」の使い分け(システム1が感情的で情報処理が速く、システム2が計算・論理的で処理が遅く、人間は、システム1に従ってしばしば間違える…)に近い。
これらは、経済学者の人間観察としては後の行動経済学を先取りしているような先駆性があるが、ケインズの文脈で問題となる国民経済的な投資の決定にあっては、これを不安定化させる困った要因である。
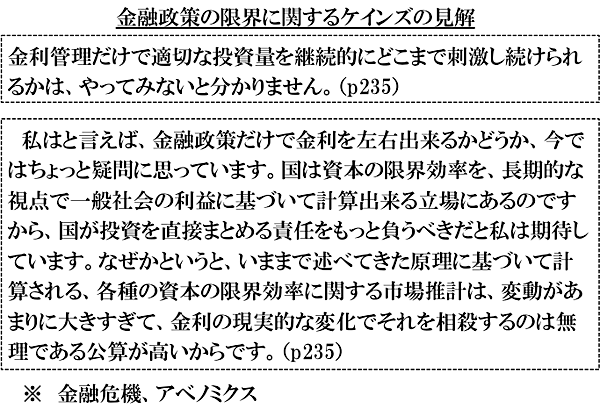
(図12)
長期的な期待は、資本市場の気まぐれや、人間のヤル気の不安定さなどもあって、非常に不安定であり、一国の投資水準を、完全雇用が可能なレベルに、金利政策だけでコントロールすることがどの程度出来るのかは、「やってみないと分からない」とケインズは述べる。これも驚くべき率直さだが、長期期待に影響を与える要因の不安定さと影響力から見て、金融政策のみの効果に対して、やや悲観的になっている印象を受ける。
また、投資について、「国が直接まとめる責任をもっと負うべきだ」という、いかにも世間で言うケインズ政策的な考えには、賛否両論があるところだろう。
たとえば、否定的な意見としては、投資は政府に決めさせるよりも民間に市場を通じて決めさせる方がいいという考え方もありうるし、「政府」自体がそれに関わる人にとって「ビジネス」であり、彼らが「一般社会の利益」に基づいて一国の投資を考えるなどということに期待するのは、政府という経済取引的にはアンフェアな枠組みを利用した活動を野放しにするに近いといった批判もできそうだ。
ケインズの「一般理論」の後、過去数十年の世界経済の展開を見ると、金融政策は案外有効に効いているし、標準的な経済政策のツールとしての地位を得ているようにも見える。また、金融政策の持つ影響の大きさは、日本のバブル崩壊後のデフレや、リーマンショック後の世界の金融危機などの推移を通じて確認されたところでもある。
但し、ゼロ金利の制約がある場合には、金融政策だけでなく財政的な政策の併用が必要になるのかも知れないし、また、ケインズが論じた資本市場の問題が解決したわけではさらさらない。
今回は第12章を読んだだけだが、「一般理論」は、現在も、おそらくこれからも大いに読む価値のある本だろうと思う。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
