売買で収益を上げるには上昇あるいは下落トレンドに乗る必要がある。トレンドにうまく乗れれば3勝7敗でも利益が上がるのが相場である。
ノーベル賞学者の言うように相場はランダム・ウォークでありカオスであるのかも知れないが、市場参加者はなんらかの形でトレンド相場(相場に方向性がある時期)と、もちあい相場(相場に方向性のないレンジ相場)の認識をしないと収益を上げることは困難となる。
もちあい(レンジ)を離れた相場につくのはトレンドフォロー取引(相場についていく取引)の基本形であるが、これを最も原始的な形で認識する方法が第12回のコラムで紹介した「トレンドライン」のブレイクである。
- ドル/円(日足) トレンドラインのブレイク
-

(出所:石原順、ブルームバーグ)
この手法だけだといわゆる「ダマシ」に遭う可能性も大きい。(統計的には2ヵ月以上の時間が経過したトレンドラインのブレイクでないと信頼性は低い)そこで筆者は相場の方向性の有無を判定するのに「標準偏差ボラティリティ」を併用している。この標準偏差ボラティリティは第14回のコラムでも紹介したが、相場のトレンド時期と保ち合い時期の判定に有効なツールである。
- ドル/円(日足) 標準偏差ボラティリティ(13日・26日・55日の1シグマ)の推移
-
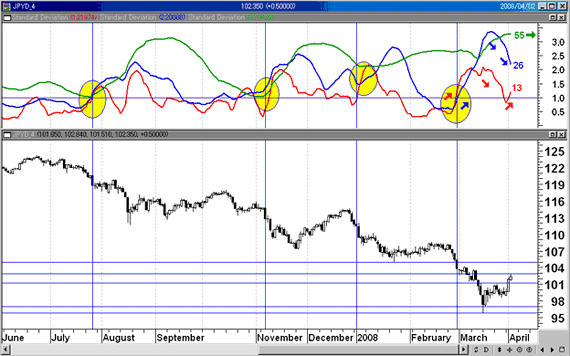
(出所:石原順、ブルームバーグ)
相場の強気・弱気の認識はタイムフレームによってどうにでも変わる。筆者は短期13日・中期26日・長期55日の異なるタイムフレームの標準偏差ボラティリティを用いて相場認識を行っている。相場に方向性が出てくると標準偏差ボラティリティは上昇する。この標準偏差ボラティリティが上昇している期間がトレンド相場である。特に13日と26日の標準偏差ボラティリティが低い位置から同時期に上昇する場合は、相場がもちあいを離れ強い方向性をもつシグナルとなる。一方、標準偏差ボラティリティがピークアウト(天井をつけ下落)すると、トレンド期とはやや逆方向にバイアスがかかった「横這いレンジ内での乱高下相場」となる。
昨年の6月以降、相場が方向性を持った時期が4回あった。上記のチャートの黄色い部分である。この4回のトレンドの発生はすべて円高方向であった。大きなトレンドの発生は最短で2~3ヵ月に1回の割合である。したがって、次の大きな方向性をともなった動きは5月以降となるだろう。
- ドル/円(日足) 標準偏差ボラティリティのピークアウトとレンジ相場
-
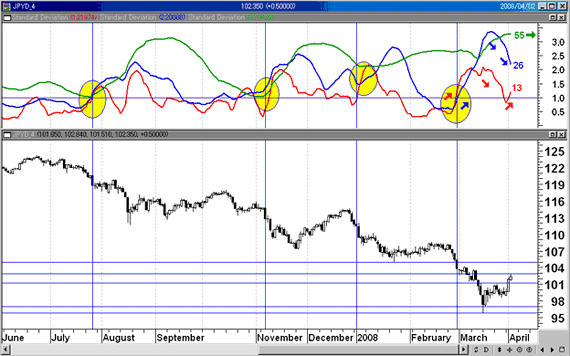
(出所:石原順、ブルームバーグ)13日・26日の標準偏差ボラティリティが両方下落すると相場はレンジ内の横ばい相場となりやすい。現在、中・長期のボラティリティはピークアウト、円高トレンドは一旦終息し、横這い乱高下相場に移行している。短期13日の標準偏差ボラティリティは短期的な円安相場を示唆している。標準偏差ボラティリティがピークアウトすると通貨オプションのトレーダーはショートストラドルやショートストラングルといったポジションを作り(ボラティリティの売り)、相場がレンジに収まっていれば収益があがる戦略をとる。
4月2日にIMFは2008年の全世界GDP成長率予想を3.7%に下方修正した。(2007年7月に5.2%を予想以来、3度目の下方修正)また、4月 2日の議会証言でバーナンキFRB議長が「米景気後退は起こりうる」と述べたように、米国経済のファンダメンタルズに特に大きな変化があったわけではない。それでも、ドル/円相場は3月17日安値95円78銭から反転し4月3日には一時102円95銭まで上昇した。
ファンダメンタルズというのは急激なマーケットテーマの変質には反応できないのである。相場はいつも後講釈でそれらしき解説がなされるが、相場は相場に聞くのが一番であろう。標準偏差ボラティリティが示唆するように、今後はレンジ内での乱高下が予想される。また例年4月の相場はよく動く。この先、4日の雇用統計、11日のG7、14日から相次ぐ欧米金融機関の決算発表と材料が目白押しである。乱気流相場に翻弄されないためには、通常の相場より小さいポジションで相場に参入するべきであろう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
