本来、円安とは「国内のインフレによって円の国内価値が減価し、それに対外価値である対円レートが追随する」という現象である。これは為替レート決定における「フロー・アプローチ」の理論である。
名目為替レートと実質為替レートの違いを考えればわかることであるが、通常、購買力平価理論では、「長期的な通貨の相場水準は相対通貨のインフレ率の格差」となる。
簡単に言うと、
[名目金利の高い通貨]→「高インフレ」→「購買力の低下」→「通貨安」
[名目金利の低い通貨]→「低インフレ」→「購買力の上昇」→「通貨高」
という法則である。
ところが、2000年以降の為替市場では為替市場の常識である「フロー・アプローチ」理論とは逆の高金利通貨が買われ低金利通貨が売られるという相場が展開されてきた。
現在の為替市場は膨大なファンドマネーをメインとする「アセット・アプローチ」理論で動いているのである。これがわからないと2000年以降新興国通貨やポンドやユーロが買われ、円やドルが売られてきたかが理解不能となる。
「アセット・アプローチ」理論、すなわち資産選択の理論における為替市場は以下のような単純なロジックで動いているのである。
なぜ円安になるのか?
世界経済の成長>日本経済の成長
なぜドル安になるのか?
新興国の成長>先進国の成長
昨今の日本経済は貿易量の多い中国経済に組み込まれ中国の経済特区のようになってしまっているのである。この結果、中国の一人あたりGDPと日本のそれが “ドル・ベース”で一致するまでデフレバイアスがかかる。つまり当面は低金利基調が続くこととなる。その結果、日本の過剰流動性資金は高い金利や高い経済成長などの効率性を求めて世界に分散される。その資金移動のなかでのユーロ/円に象徴される7年間の円の独歩安現象は日本経済の過剰流動性資金がユーロ圏より数倍大きいことの証左であろう。
一方、ドルが上がらないのは、米国の個人金融資産がユーロ圏・カナダ・英国・オーストラリア・ニュージーランドなどよりも数倍大きいためである。現在の対円を除いた歴史的なドル安は米国経済の実態が他国より悪いということではなく、より高いGDP(成長率)を求めてドルの金融資産が世界に分散されているということである。
特に30年後の年金を低所得者層であるメキシカンが支えるという年金支払に対する米国人の危機感は、401Kの運用においても多くの米国人に「債券型」でなく「国際株(新興国株投資)型」を選択させているのである。
原油価格の高騰で昨今の金融市場の一大勢力となったロシアや中東マネーは、国内に投資するインフラがないため、世界の市場に分散投資せざるを得ない。原油や天然資源の売却代金はドルで得ているが、この膨大なドル資金の一部が比較的流動性のない市場に分散投資されるとその国の通貨は急騰する。昨今のユーロやポンドの歴史的な高値示現はこのような構造が背景となっている。
- ドルインデックス(日足) 1971年~2008年の推移
-
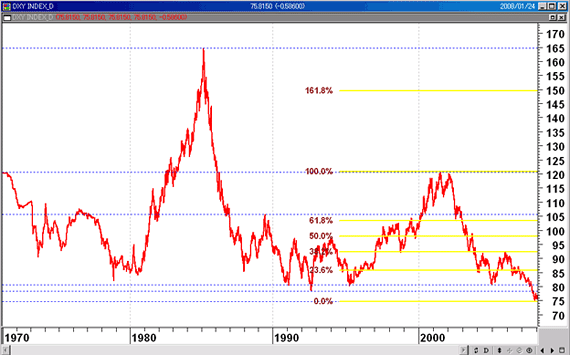
(出所:石原順、ブルームバーグ)
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
