「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」を運用している農林中金バリューインベストメンツのCIO「奥野一成」が、『ビジネスエリートになるための教養としての投資』を執筆、投資の本ながらビジネス部門で話題となっている。
投資と本来の投資のあり方とその哲学、長期投資のコツ、優良企業の見極め方などを、歴史的な背景や実例を交えながらわかりやすく解説するこの著書は、投資を今から始める人、投資の運用に困っている人にぜひ読んでほしい。
トウシルでは、この本の中から、ぜひみなさんに読んでほしい内容を10編ピックアップ。今回は10回目を紹介する。
誤解しやすい「長期潮流」
高い付加価値がある会社が、高い参入障壁を築くことによってしっかり自分たちが得る利益をプロテクトできると、利益を確保しやすくなります。そして、この2点が揃った時点で、初めて長期潮流が持つ意味が生きてきます。強いビジネスが長期潮流に乗った時に、営業利益がずっと出続けるのです。
ただ、これは非常に重要な論点なので、しっかり皆さんも整理して考えて欲しいのですが、長期潮流とは、高い付加価値と高い参入障壁によって獲得された利益を、増幅させるものです。つまり長期潮流があったとしても、付加価値や参入障壁が無かったら、長期的に利益を獲得し続けることは出来ません。
たとえば太陽光発電。再生可能エネルギーに関連したビジネスは、大勢の人たちが必要としている点で付加価値がありますし、化石燃料や核を用いたエネルギー源から、より安全でクリーンな再生可能エネルギーに切り替えていくのは、世界各国の中長期的エネルギー政策の中核ですから、何となく長期潮流も満たしているように見えます。
しかし、問題は参入障壁がほとんどないことです。日光さえあればどこでも発電できますし、技術的にも難しくありません。参入障壁が無ければ、そこに参加している会社はどんどん増え、利益の奪い合いが行われます。そのなかで利益を勝ち取る会社もありますが、大半の会社は赤字に転落します。それでも、「このビジネス分野は長期潮流があるから、何とかここを乗り越えれば」といった期待感でビジネスを続けていると、赤字がどんどん増幅されてしまいます。
では、何をもって「長期潮流」というのでしょうか。これも誤解されやすいポイントです。
よく株式市場では「これは長期的な投資テーマだ」などと言われて、環境関連やヘルスケア関連、AI関連などいろいろな投資テーマが取り沙汰されます。このように株式市場で「長期的な投資テーマ」と言われるものが長期潮流たりえるのか、ということを考えると、これは恐らく違うと思います。
株式市場でその時々に取り上げられる投資テーマは、いくら「長期的な投資テーマ」と言われていても、単なるファッションに過ぎないだろうと思うのです。ある程度のスパンで予想される社会の変化かも知れないけれども、不可逆的に世の中の構造を大きく変えるだけのインパクトがあるのかどうかを問い直すと、決してそうだとは言い切れない部分もある、ということです。
では、本物の長期潮流とは何か? これは「不可逆的であると言い切れるもの」だと思っています。不可逆、つまり元には戻れないものということですね。
たとえば人口動態はその典型例です。少なくとも2100年までの人口推計を見る限り、世界中の人口が増加していくのは間違いありません。
あるいは古今東西を問わず、人々にある絶対的な長期潮流としては、「長生きしたい」という欲求があります。生まれた瞬間から「死にたい」と思っている人はいません。太古からの歴史をたどっても、人は必ず長生きしたいと思っています。人間である以上、それは普遍的な欲求です。人口が増加するということは、健康への需要が増加するということです。
もうひとつ、思いつくままに申し上げますが、「国家財政は悪化する」というのも長期潮流のひとつでしょう。民主主義国家であればなおさらです。世界中が日本の財政悪化を批判しますが、民主主義国家である以上、米国もドイツも、イギリスも、フランスも、皆いつかは国家財政が悪化します。
特に昨今は皆、どんどん長生きになってきていますから、医療費をはじめとする社会保障負担がどんどん重くなっています。しかも民主主義国家では、年金の既得権益者である高齢者が票を握っていますから、どれだけ国家財政が悪化したとしても、既得権益者は自分が持っている既得権を絶対に手放そうとはしません。だから、国家財政は民主主義国家である以上、どの国も等しく、いつかは必ず悪化するのです。よって、国家財政が悪化するというのも長期潮流であると考えられるのです。
そして、「長生きしたい」という長期潮流と、「国家財政は悪化する」という長期潮流を掛け合わせた時、また別の長期潮流が生まれます。
それは、カテーテル治療や内視鏡治療などの「低侵襲(ていしんしゅう)医療」です。
もし、カテーテルが無かったら、心臓に病気が見つかった時、開胸手術をしなければなりません。開胸手術は時間がかかるだけでなく、患者の身体にも重い負担になります。当然、手術をしたら2週間くらいの入院生活を余儀なくされます。その分、国の医療費も出ていくことになりますから、高齢化によってこの手の患者が増えるほど、国家財政が圧迫されていきます。
もしカテーテル治療で開胸手術をせずに済めば、カテーテル治療をした2、3日後には退院できますし、それだけ患者さんの身体的負担も軽くて済みます。結果的に出ていく医療費も少なくなるので、国家財政の面でも低侵襲医療の普及は非常に有益ということになります。
このように「長生きしたい」と「国家財政は悪化する」という2つの長期潮流をかけあわせることで、低侵襲医療という別の長期潮流が生まれます。
こうして長期潮流が導き出せたら、あとはどの会社に投資するかを考えるわけですが、恐らく多くの人はここで「カテーテルを作っている会社ってどこだっけ」と探し始めるでしょう。でも、カテーテルを作っている会社がどこも儲かっているかというと、決してそんなことはありません。何よりも大事なのは、高い参入障壁を築けているかどうかです。つまり高い参入障壁を持ってカテーテルを作っている会社こそが、長期潮流に乗れるという話になるのです。
参入障壁は色褪せやすい
「参入障壁」という言葉を耳にタコ状態になるくらいしつこく繰り返していますが、強靭な構造を持った会社に投資しようと思ったら、ここは絶対に外せない大事なポイントです。
参入障壁はニュートンの「万有引力の法則」ではないけれども、何もせずに放っておくと必ず落ちます。落ちそうになっているのを、いかにして再び活性化させるかが、参入障壁を築き上げていくうえで重要になっていきます。
ではどうすれば良いのか? もちろん経営力もありますが、やはり一番大事なのは投資です。いや、「経営力=投資」と言った方が良いでしょうか。参入障壁を築くうえで必要な投資を行うための経営判断力が問われてきます。
たとえば自社の参入障壁を維持するために、競合の会社を買収するなんてことは、その典型的なケースです。買収だって立派な投資です。その他に研究開発投資や設備投資、人材投資などあらゆる投資の方法を用いて、参入障壁を維持しようとします。
今、申し上げた企業買収や研究開発投資、設備投資、人材投資など会社として行っている投資活動は、すべて参入障壁を高くするために行われるべきものと考えておくべきです。ここで変な勘違いをすると、某ステーキチェーンのようなことになります。
そもそも、ステーキハウスそのものは、何の参入障壁もないわけですよ。誰だって新規参入できます。外食産業はどこもそうで、最初のアイデア一発でバーッと店舗を拡大して売上を伸ばし、中期的な利益を大きく膨らませて上場まで持っていく。基本、そこで終わりです。いわゆる「上場ゴール」ですね。上場したところがその会社のゴールで、あとは惰性で進んでいるだけ。最初にアイデアを考えた人は先行者利得が得られるわけですが、それは決して参入障壁ではありません。いくら多額の先行者利得を得たとしても、そのビジネスがおいしいということに気づいたら、必ず後発が入ってきます。そうなると、あとは価格の引き下げ競争が始まり、レッドオーシャンになって終わりです。
別に参入障壁という概念は難しいものではありません。大学院にいかなければわからないようなものでもありません。少しの好奇心をもって街を歩いているだけで気付くものなのです。街を歩いていると、居酒屋の看板が次々に変わっていることに気づきます。そんなところに参入障壁があるわけがないということです。
ちょっと話が逸れましたが、だからこそ某ステーキチェーンは、自分のビジネスには参入障壁がないということを理解したうえで、事業拡大の投資を行うべきだったのです。そこを理解していなかったから、中途半端な多店舗展開を行った挙句、売上が頭打ちになって苦しんでいるのです。
ただこれは、某ステーキチェーンをはじめとする外食産業に限った話ではなく、基本的にどのビジネスにも参入障壁を築くことは容易ではありません。どうやったら参入障壁を築けるのかを必死に考え、どの会社を買収すれば良いのか、どのような人を入れて戦力にすれば良いのかをひたすら経営者は考えるのです。先ほど、「経営力=投資」と言ったのは、こういうことなのです。
ここ数年、米国のGAFAが話題になっていました。GAFAとはGoogle、Amazon、Facebook、Appleという、米国を代表するITプラットフォーマーのことで、まさに我が世の春を謳歌しているわけですが、これだって参入障壁という観点から厳密に見れば、それがあるところとないところに分かれます。
たとえばグーグル。ここはもう立派に参入障壁を築いています。あのグーグルの向こうを張って、同じように検索エンジンを1から作り上げて、グーグルとの競争に勝てるなどと考える人は、まずいないでしょう。
対して、GAFAのなかで最も参入障壁が低いビジネスを行っているのがフェイスブックだと思います。基本的にSNSは参入障壁が全くないビジネスです。その証拠に、日本にミクシィというSNSがありましたが、フェイスブックが普及した途端、簡単に駆逐されました。
一部では、「フェイスブックにはネットワークエフェクトがあるので、それが最大の参入障壁だ」という意見もあります。
ネットワークエフェクト、これは使う人が増えるほど便益が増えて、ネットワークの価値が高まる効果のことです。昔の電話がそうで、加入者が少ないと使うメリットがあまりありませんが、加入者が増えるほどいろいろな人と電話で連絡が取れるようになり、利用者の便益が高まっていきます。そして最後には、そのネットワークに入っていないと不便さを感じるようになり、一定の閾値に達したところで一気に加入者が急増していきます。これがネットワークエフェクトです。
でも、フェイスブックにはそれがあるでしょうか。フェイスブックは70億人という世界人口のうち30億人が使っている巨大SNSプラットフォームですが、止めようと思えばいつでも止められます。最近では「SNS疲れ」によって、フェイスブックから距離を置く人も増えてきました。実際、自分がフェイスブックでつながっている人を見ても、もう何年も更新していない人が結構います。そのうえ、リンクトインのような新しいSNSもどんどん参入してきます。そういう産業において、「70億人のうち30億人が使っているので、フェイスブックにはネットワークエフェクトがある」というのは、恐らく嘘だと思います。私に言わせれば、あの程度のものは参入障壁でも何でもありません。
それと同じ視点でいえば、ライドシェアビジネスを展開しているウーバーもリフトも、参入障壁なんかありません。あれらは単なるマッチングアプリであり、誰でもつくることが出来ます。だから、アメリカに行くとウーバーとリフトの両方に加入しているドライバーが大勢います。つまり参入障壁がないという何よりの証拠です。
でも、ウーバーとリフトのドライバーが車に積んでいるスマホやタブレットの画面に映されているグーグルマップを提供しているのは、グーグルです。これは使わざるを得ないので、高い参入障壁があることになります。
ちなみにフェイスブックは今、暗号資産である「リブラ」の発行計画を公表し、米中央銀行との間ですったもんだを繰り返しています。中央銀行としては、通貨発行権という巨大な利権を奪われたくありませんから、リブラには反対の姿勢を取っています。もし、世界30億人がリブラを使うようになったら、世界の基軸通貨である米ドルの地位が揺らぐ恐れが生じてきます。そんな訳で、まだ正式に発行できるかどうか分かりませんが、もしフェイスブックが暗号資産を発行するところまで行き着ければ、これは立派な参入障壁になるでしょう。その意味で、マーク・ザッカーバーグは経営者として優秀だと思います。
このように参入障壁について思いを巡らせると、つくづく経営は参入障壁をつくるゲームであると思えてきます。通常、何もしなければ、参入障壁が崩れるのに1年もかからないでしょう。それを出来るだけ延ばすために、さまざまな投資を選択していくのです。コカ・コーラは間違いなくその成功事例のひとつです。
<『ビジネスエリートになるための教養としての投資』より抜粋>
全編読む:『ビジネスエリートになるための教養としての投資』
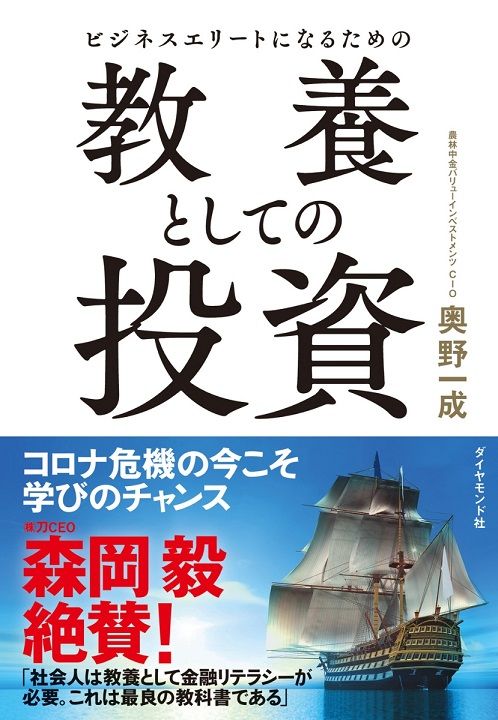
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
