まず下の写真を見てほしい、これは平成23(2011)年10月11日に実施された「第4回社会保障審議会年金部会」の資料。震災直後の2011年の時点で、すでに年金の支給開始年齢の引き上げについて議論が行われていた。
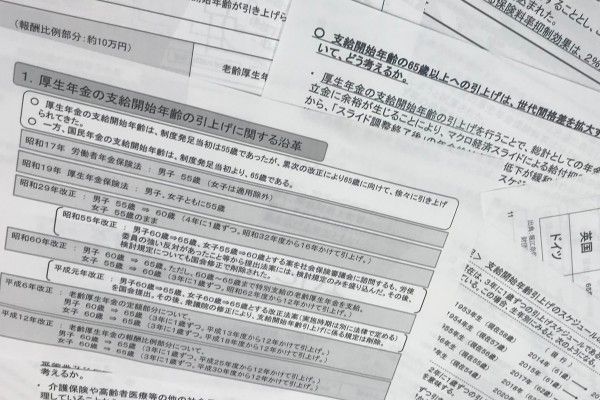
つまり、「年金問題」は何も今始まった話ではない。その上で、この8月に公表された年金の定期健診「財政検証」について見ていこう。
2019年の年金の「定期健診」。20世紀から言われていた年金財政不安
厚生労働省が8月27日に2019年版の「年金財政検証」を公表し、経済成長の度合いに応じて、およそ30年後の公的年金が実質15.9~41.7%ほど目減りするとの見通しを示した。パート労働者など月収5.8万円以上の全雇用者の年金加入や75歳までの納付期間延長を実施した場合の予想も盛り込まれた。今後、月々の掛け金増額や受給開始年齢の引き上げ、掛け金運用の再検討などの議論が本格化することになる。
財政検証は今回で3回目。小泉純一郎首相(当時)が「100年安心プラン」と打ち出した2004年の年金制度改正で、5年に1回実施することが決まっている。将来の年金保険料収入や給付額を試算するもので、次の制度改正のたたき台となる。年金制度を持続するための「定期検診」である。
発表翌日の28日には菅義偉官房長官が「長期的な社会経済の変化に合わせ、より確かなものにしていく」と述べ、制度見直しに着手する方針を示した。最大野党の立憲民主党などは「前提条件が甘い試算だ」と批判し、年金問題を次期総選挙の争点にする姿勢を強調している。
メディアの論調は老後破産の不安を強調する内容が目立つ。しかし、年金財政の厳しさは20世紀から指摘され、受給年齢引き上げの議論も突然出てきたわけではない。
たとえばパート・アルバイト従業員への厚生年金の適用拡大や就労期間の長期化などは2014年版の財政検証で「オプション」として示されている。東日本大震災直後の2011年5月には、省庁横断的に開かれた「社会保障改革に関する集中検討会議」で、基礎年金と厚生年金の支給開始を68歳に引き上げる案が検討された。
支給を1年遅らせると1兆3,000億円の財政負担軽減につながるとの試算も提示されており、2019年版は旧民主党政権時代も含めて続いてきた議論の延長線上にある。
年金問題の解決に「魔法の杖」はなく、保険料や運用による利益、税金による国庫負担を合わせた収入と毎年の給付額のバランスをどう取るかに行き着く。
経済成長「0%」だと、年金額は現役時代の収入の5割割れ
財政検証では、6つの経済成長シナリオごとに将来の受け取り水準がどう変化するか、試算が明示されている。
政府が使う指標は「所得代替率」。年金がどれだけ給与収入の代わりになるかを現役世代の収入を100%として表す。2019年版では、現役男性の手取り平均35.7万円で、夫婦2人の年金22万円(夫婦2人の基礎年金13.0万円と夫の厚生年金9.0万円を合計)を割った61.7%が所得代替率だ。
ベストシナリオは「経済成長と労働参加が進むケース」。内閣府が成長実現ケースとする年率0.9%で経済成長が続き、物価上昇率が政府・日銀目標の2.0%で推移し、女性や高齢者の就労が増える場合だ。所得代替率は51.9%に低下するが、2019年に比べて15.9%の減少にとどまる。
経済成長率を0.4%、物価上昇率を1.2%に落しても、所得代替率は50.8%と、政府が年金改革で掲げた「現役世代の半分以上」に相当する50%をクリアできる。
ただ、経済成長率が0%、物価上昇率が0.8%だと2058年度に所得代替率が44.5%に低下する。
ワーストシナリオとして設定されたのは、経済成長率マイナス0.5%が続くケース。2043年度に所得代替率が50%に低下し、その後も制度を修正しなければ2052年度に年金積立金がゼロになる。この場合はまだ生まれていない子供も含め、将来の現役世代の保険料と税金で賄える所得代替率は36~38%しかない。2019年比で最大41.7%の大幅減少だ。
今回の試算では、現役労働者による保険料収入を左右する就業率は2040年推計で60.9%。2017年実績は58.8%なので無理のない数字だろう。
就労期間の延長と対象者拡大、受給開始年齢の引き上げが改正の焦点
一方、公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)による運用利回りを4.0%(2014年版は4.2%)に引き下げられた。運用利回りは直近10年間の平均では5%を超えるが、GPIF設立後の2006年以降の平均は3%台前半にとどまり、4.0%という数字は高いとも低いとも言える微妙な水準だ。
1人の女性が産む子供の人数を示す合計特殊出生率は、2065年に1.44人と、2016年と同水準を前提としている。合計特殊出生率は2005年に1.26人まで減少。昨年は1.42人と3年連続で低下している。GPIFによる運用不振や出生率の低下が続けば、年金財政の長期推計は数10兆円単位で簡単に変わってくる。
厚労省は前回に続いて2019年版でも財政検証に「オプション」を付け加えた。「付録」でも「補足」でもなく、将来の制度改正の青写真といっていい。
オプションAは保険料収入の増加に直結する加入者拡大。月収や労働時間に応じて3段階に分け、月5.8万円以上の収入のある全ての労働者に適用を拡大すると、新たに1,050万人が保険料支払いの対象になる。所得代替率は最大56.2%と、政府目標の50%をクリアできる。
オプションBは公的年金の加入上限を現行の70歳から75歳に引き上げるなど納付期間の延長や受給開始時期の後ずれを前提とした試算で、こちらも所得代替率の向上が確認されている。
今後の制度改正の議論は、就労期間の延長と対象者拡大、受給開始年齢の引き上げに向けて進む。これは政権や政策方針がどう変わっても避けられないことだろう。厚生労働省のある中堅官僚は「政官財のうち『官』の力には限界がある。政治がリーダーシップを発揮し、財界が経済成長を実現するなど個々が役割を発揮するしかない」と話す。
政府ができるのは保険料収入の増大と給付の抑制だとしたら、個人に必要なことは老後に備えたマネープランだろう。NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した長期的な資金運用がますます重要になってくるのは間違いない。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
